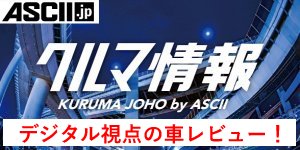■満を待しての動作確認
 |
|---|
| 組付けたガス冷装置 |
今度は以前の失敗を教訓に、強力な接合方式でCPUとガス枕を固定する。CPUに銅板を貼りつけ接触面積が大幅に増えているので安定性は抜群に良くなった。コンプレッサーはテストの途中で安全回路が作動して止まると怖いので、制御回路を切り離しAC100V直結とした。人命がかかっているのでは、というくらい厳重なチェックをして恐る恐るコンプレッサーを起動する。
 |
|---|
| 組付けたガス枕 |
CPUの冷却状態をモニターするためコアに貼りつけた銅板とCPUのセラミックパッケージの間に温度計のセンサーを取りつけた。予備運転でバッファ板温度が-20℃になるのを待ちPCの電源を投入する。CPUが動作しだすと温度がぐんぐん上昇する。1.2GHz定格動作時で最高-3℃、最低-20℃位の間で温度が変化する。CPUの高負荷時とアイドル時で激しく発熱量が変化しているようだ。
■1575MHzまでWindowsが起動
 |
|---|
| WCPU-ID(作者:H.Oda!氏)を使って調べてみた結果。1575MHz(150MHz×10.5)で起動した状態 |
ガス冷装置の威力を確認するため、クロックアップとベンチマークテストを行った。ベンチマークに使用したソフトウエアはSuperπ、3DMark 2000、3DMark 2001の3種。結果的にFSB設定クロックと倍率の組み合わせは、153MHz×10の1530MHz(1.85V)まで安定動作、150MHz×10.5の1575MHz(1.85V)までWindows 98が起動した。CPUクーラーにカニエ製Hedgehog-238Mを使用し、同一の機器構成で同じAthlon-1.2GHzのクロックアップをした場合の正常動作限界は、140MHz×9の1260MHz(1.85V)だった。
今回は残念ながら時間の関係でコア電圧の昇圧は試みなかったが、1450MHzまではコア電圧1.75Vで正常動作したので、もう少し上が狙える可能性があると思われる。
■最後に
高負荷時の温度上昇の早さと戻り配管の凍結具合から考えて、今回製作したガス枕は気化室の容積が不足ぎみであると思われる。配管の取り回しや組み込み時の簡便性から考えてもまだまだ改良の余地があり、できることならもう一度、新設計のガス枕を製作してみたいところだ。それなりの経費と労力をつぎ込んでしまったガス冷装置ではあるが、代償に見合った劇的な効果も体感できた。ガス冷装置はクロックアップのために製作しているというより、装置自体の製作過程に楽しみがあると感じずにはいられない。製作中に参考にさせて戴いた諸先輩方の記事中にもクロックやベンチ結果はあまり見受けられず、機構の新規性や到達温度、美しさ等に重点がおかれているように感じられた。自作PCは部品を集めている時や、作っている過程が楽しいのと同じように、ガス冷装置もその製作自体に不思議な魅力があると感じる。今回のガス冷マシン完全自作編は時間の関係でケース組み込みまで完成できなかったが、できれば最後まで組上げて、また機会があればご報告したい。
尻切れトンボな状態でスミマセンですがガス冷編はこれで終了。ホントガス冷は奥が深い。また修行して出なすことにしよう。そんなわけで次回はフットコントローラの製作に挑戦。えっ、フットコントローラって何って。それは次回のお楽しみ。たまには実用性のあるものも作らないとダメ。次回フットコントローラ自作編でお会い致しましょう。
参考にさせて頂いたウェブサイト
ガス冷却を実践されている諸先輩方より貴重な情報をいただきました。この場を借りてお礼を申し上げます。
ガス冷却の第一人者apkさんのページ。キャピラリーチューブの長さについて、コンプレッサーについてなど、様々な情報をいただきました。 妥協を許さない工作技術の鬼のようなmasamotoさんのページ。規制フロンについてのご指摘、代替冷媒について他、貴重な情報をいただきました。*注意
除湿機、冷蔵庫、クーラー等の冷凍機には高圧ガスが使用されており、分解すると、凍傷、失明、爆発などの危険があります。また、これらの機器を分解・改造した場合、一切の保証が受けられなくなります。さらに、CPUのメーカー規定周波数以上の動作は、CPUや関連機器を破損したり、寿命を縮める可能性があります。その結果によるいかなる損害についても、筆者およびデジタルバイヤー編集部、製造メーカー、販売店はその責を負いません。機器の分解・改造は自己の責任において行って下さい。なお、この記事中の内容は筆者の環境でテストした結果であり、記事中の結果を筆者およびデジタルバイヤー編集部が保証するものではありません。この記事についての個別のご質問・お問い合わせにお答えすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
【筆者プロフィール】森本琢司氏。本来はペルチェなどを使ったオーバークロック系、冷却系に一番関心があるのだが、趣味でPC改造も数多く手がけている。ハンドニプラーやその他工具を使っての改造は得意中の得意

この連載の記事
-
第3回
ゲーム・ホビー
ガス冷マシン完全自作編 ~その3~ -
第2回
ゲーム・ホビー
ガス冷マシン完全自作編 ~その2~ -
第1回
ゲーム・ホビー
ガス冷マシン完全自作編 ~その1~ - この連載の一覧へ