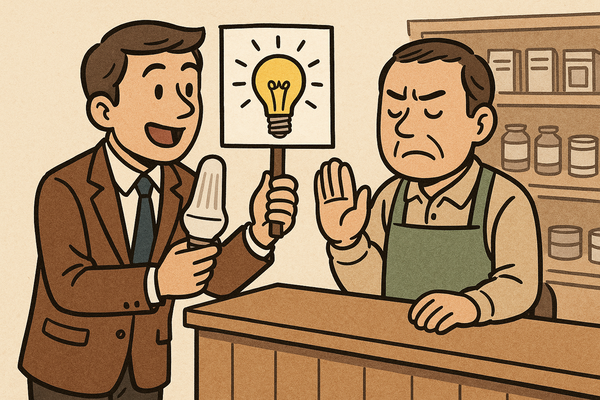著者紹介●羽山 友治(はやま・ともはる)
スイス・ビジネス・ハブ 投資促進部 イノベーション・アドバイザー。10年以上にわたり、世界中のオープンイノベーションの研究論文を精査し、体系化。戦略策定・現場・仲介それぞれの立場での経験を持つ。著書に『オープンイノベーション担当者が最初に読む本:外部を活用して成果を生み出すための手引きと実践ガイド』がある。
「技術はすごいのに、なぜ売れないのか?」
そんな悩みは、新規事業に関わる人なら一度は直面したことがあるはずだ。優れた技術と市場のあいだには、越えるべき“翻訳の壁”がある。今回は、技術を製品・市場にどうつなげるか、その基本モデルと実践のヒントを紹介する。
技術から市場への「翻訳」を誰が担うのか
技術から市場へのギャップをどう埋めるかを考えるうえで、参考になるのがTPM(Technology → Product → Market)という基本モデルである。これは、技術(T)を製品(P)に転換し、市場(M)とつなげるという考え方である。研究開発の成果を、そのまま顧客に届けることはできない。どんなに優れた技術でも、「誰のどんな課題を解決するのか」という問いに答えられなければ、価値にはなり得ない。
このプロセスで重要なのが、“チャンピオン”の存在である。チャンピオンとは、その技術を信じ、なんとか事業化に結びつけようと動き続ける推進者のことを指す。必ずしも役職者である必要はないが、社内外の関係者を説得し、必要なリソースを確保し、プロジェクトを前に進める役割を果たす。特に不確実性の高い初期段階では、このような「誰かが信じて動く」存在が不可欠である。
汎用技術こそ、使い道の選定が難しい
技術の商業化を難しくするもう1つの要因が、応用範囲が広すぎる技術──いわゆる汎用技術の扱いである。素材系やナノテクノロジー、AIのような技術は、多くの産業に活用できる一方で、「結局どの市場に使うべきか」が定まらず、事業化の優先順位が見えにくくなる。
こうした技術を持つベンチャー・スタートアップ企業では、短期的に収益を見込める用途に集中しつつ、将来の有望市場に向けた知財の確保やパートナー探索を進めるという「二段構え」の戦略が効果的だとされている。この考え方は、大企業の新規事業部門にも応用できる。
技術と市場の適合性をどう見極めるか
では、どうすれば「この技術は、どの市場に向いているのか」が見えるようになるのか。その鍵は、実際の市場ニーズとのフィットを見極める探索行動にある。例えば、近年では大規模言語モデル(LLM)を使い、仮想的なユーザーインタビューを大量に生成して仮説検証を行うようなアプローチも登場している。
従来であれば数カ月かけて行っていた用途探索が、数日で済むようになる可能性もある。これは大企業にとっても朗報であり、社内の研究成果や保有技術の活用を検討する際に、迅速かつ低コストで市場との接点を探る手段として活用できる。
技術を「起点」にせず「接点」から考える
技術の商業化は、「良い技術があるから何かできるはずだ」といった期待感だけでは進まない。むしろ、「どのような市場課題に対して、自社の技術が貢献できるか」という逆算の思考が必要である。技術を起点とするのではなく、市場との接点を設計する──この視点こそが、技術の商業化における第一歩となる。
次回は、このような技術が「ディープテック」と呼ばれるようになった背景や、その事業化に特有のリスク、そして企業としての関わり方について考えていく。
■本記事をもとに、生成AI(Notebook LM)を活用して構成したPodcastを配信中
「オープンイノベーションや新規事業開発まわりの共通言語を理解する1冊」
社内での「イノベーション活動」に関わる中で、おさまりの悪さを感じたことはないでしょうか。数々の取り組みの概念のつながりや位置づけを理解し、実践できる著者による書籍『オープンイノベーション担当者が最初に読む本:外部を活用して成果を生み出すための手引きと実践ガイド』(羽山友治 著、ASCII STARTUP/角川アスキー総合研究所刊)では、何から始めればよいかがわかります。興味のある方はぜひチェックしてみてください。
■Amazon.co.jpで購入
-
オープンイノベーション担当者が最初に読む本 外部を活用して成果を生み出すための手引きと実践ガイド羽山 友治、ASCII STARTUP KADOKAWA