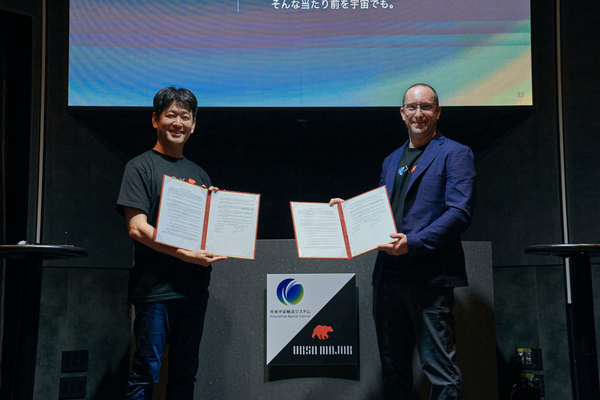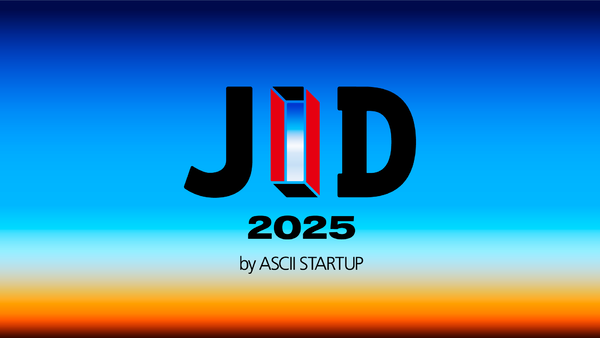Moatを作るための大きな武器に知財がある。求められるスタートアップ支援の現在
「IPナレッジカンファレンス for Startup 2024」レポート
Moatを作るための大きな武器として知財がある
知財でスタートアップが大きく伸びる世界を作る
2つ目のテーマ「識者が見据える次世代のコーポレートベンチャリングと知財のあり方」のパネリストには、選考委員から鮫島 正洋氏と藤木 実氏(株式会社IP Bridge 代表取締役)、グランプリ受賞者として川名 弘志氏と増島 雅和氏が登壇した。モデレータは引き続き清野氏が担当した。
清野:選考委員のお二人は川名様と増島様の取り組みのどのような点を評価されたのか。
藤木:大企業のスタートアップ支援では、オープンイノベーションをやり切っていくということが重要。大企業がスタートアップに対してマウントを取ってしまうといったことがあればそれはもはやオープンイノベーションではない。川名さんは本当の意味でのスタートアップ支援を推進してきた、そういう取り組みを大手企業の立場で実現できたというところが本当に素晴らしいなと感じた。
増島先生は経産省の産業構造審議会の知財分科会でもご一緒させていただいているが、知財活用という視点からさまざまな発言をされている。例えば大企業とスタートアップとの共同特許の活用に関しても、現状非常に使いづらい権利になってしまっている。そういったものを本当に活用できるようなものにする取り組みをされているというところは本当に素晴らしい。
鮫島:従来の日本のやり方では発明をした人が発明者になり、KDDIがそのいくらかをもらうというやり方だが、スタートアップ支援というのは短期的な利益ではなくて、スタートアップの成長に鑑みた長期的な視野で行われるべきものという理由で権利を放棄している。それは正しいのだろうけど最初にそれをやるということは非常に勇気のいることだし、どれだけ社内説得の労力やエネルギーがかかったか、というのは想像に難くない。素晴らしい実績だ。
増島先生については、スタートアップとの法務の仕事ということになると、単に特許を取るとか、訴訟をやるとかだけでは全然足りない。資金調達をどうするかなどのコーポレートの話が絡んでくる。私は知財専門以外の弁護士が入ってくると良いなとずっと思ってきた。増島さんはコーポレート出身でかつ知財も専門にして二刀流になった。これが受賞理由。
清野:選考委員からのコメントを受けての感想はあるか。
増島:スタートアップは生き残って勝たなくてはいけない。そのためにMoat(堀)を作らなくてはいけない。そうしないと他のスタートアップに奪われてしまうリアルな状況がある。Moatを作るための大きな武器として知財があるという位置づけになる。ただ単に知財を持ちましょう、などと言われるのには全体的に違和感がある中で、知財をMoatとして使ってどこまで大きくなれるのか。生き残り勝つためにスタートアップにコーポレートのアドバイスをしていくと、知財をどうするかまでアドバイスしていかなければ目的が達成できない。二刀流は必要に迫られた必然だった。
川名:当時、発明発掘したものをどちらに帰属するのかについては悩みながらずっと進めてきた。しかしスタートアップを支援するという姿勢を(スタートアップから)評価してもらえたし、KDDI社内でもCVC運営や事業支援をしている部隊からは支援メニューの1つとして知財支援があることを非常に感謝された。数年続けてきて社内でもじわじわと評価されるようになって初めて確信に変わった。スタートアップは知財で稼がないと成長しないし、成長して初めて大企業との事業共創の中心が大きくなってくる。それがあるから大企業は成長できる、スタートアップ支援とはそういう大きな仕組みだ。
清野:スタートアップは大企業との連携がないと急激な成長は難しいという側面がある。スタートアップ側はどのような姿勢で大企業と向き合っていくべきか。
増島:自分が得をする方法を考えるというのは誰にでもできるが、相手が何を大事にしているか、自分は相手にどういう価値を提供できるかをきちんと打ち出していくところが大事なポイントになる。そのストーリーや座組を作ることが上手い起業家がオープンイノベーションが得意な起業家だと言える。それに加えて冷静な頭も大事で、大企業と組むということは自社のビジョンを実現するための手段・戦略であることを忘れてはならない。Win-Winの関係である限り誠実であるという戦略的な発想を忘れてはならず、単に相手が話を聞いてくれるからといって、自社にとってクリティカルな秘密情報をしゃべってしまってはもはや戦略と言えない。侵害などがあれば戦うということも必要になる。冷静な計算と相手のためになる価値提供の両立がすごく大事。
清野:選考委員の方から補足のコメントなどはあるか。
鮫島:私の事務所にも数か月に1度くらい地球を変えるのではないかと思える技術が持ち込まれる。しかし実際に地球を変えるためには社会実装をしなくてはいけない。米国に比べて投資額の小さい日本では大企業の力を借りるしかない。それが大企業とのオープンイノベーションだと位置づけている。オープンイノベーションは世界中で行われているが、日本のオープンイノベーションはユニークなものであり、これの成否が日本の技術が世界に出ていくかを担っている。
このオープンイノベーションの成功率をどうやって高めるのかが特許庁と経済産業省とのモデル契約プロジェクトの委員長を受けた時の問題意識だった。モデル契約の本質的な要素があるはずだと思っていた。スタートアップと大企業の企業価値の最大化を目指すというものがそれで、実現できれば日本から世界にどんどん広がっていく。
清野:本日グランプリを受賞されたお二方から、スタートアップや知財業界の将来についてここで話しておきたいことはあるか。
増島:シリコンバレーでも韓国でも中国でも、どちらが知財を持っているかなどは二の次で、その知財からいかに稼ぐかを考えている。なぜ日本だけ協業して作った知財で相手の使い方を制限するようなことをするのか。
知財はあくまで経済財の1つで、使わなければ1円もお金を生まない。発想の転換や実務の転換、さらにその後ろにある考え方や哲学まで踏み込まなくてはいけない。そういったものは10年同じことを言い続けていると結構変わっていくというところがある。私は2017年くらいから言い始めているので、2030年の日本が勝負をかけなくてはいけないと言われている年に向けてがんばっていきたい。
川名:以前は大企業からスタートアップを支援するという色合いが濃かったが、今ではKDDIも新規事業のほとんどにスタートアップが入っていて、大企業の成長のコアをスタートアップが担っていると言っても良い。大企業はスタートアップの技術の社会実装プラットフォームとなっている。
大企業の成長コアをスタートアップが担っている以上、大企業の知財部門の人間はスタートアップに行った方が良い。KDDIでは業務委託で受ける場合もあるが、スタートアップからどういう人材が欲しいかを聞いて兼務出向で行くこともある。大企業の若手社員が知財担当としてスタートアップに行って大きく成長するということが当たり前の世界を作ることが今後の日本のためにもなると感じている。
清野:選考委員のお二人からスタートアップや知財専門家へ伝えておきたいことはあるか。
藤木:スタートアップの成長のためには資金や人やマーケットへのアクセスなどさまざまなリソースを融合する必要がある。知財は融合のためのドライビングフォースになりうる。今回受賞されたスタートアップや知財専門家もまさにそういう視点で取り組んでいたからこそ受賞に至ったということだ。
また、大手企業は実はなかなか特許の活用がしづらい組織になっている。顧客やパートナーが多すぎてタコつぼ化し、知財活用の意思決定ができない。良い特許を持っているスタートアップは大企業との連携で係争になっても勝ちきることができる。我々知財の専門家はそこを支援していくことが役割の1つではないか。
鮫島:ずっと民間人として政策に関わってきた中で、どうしてもやらなくてはいけない課題が2つ日本にはある。1つは地方の人材がその地方のスタートアップのインキュベーションができるようにならなくてはいけない。これは今年度関東経済産業局などが取り組もうとしている。
もう1つは大企業のアントレプレナーシップを回復していかなくてはいけないということ。大企業は何十年にもわたって10を100にする仕事をしてきた。ゼロから1を作れる人材や風土を作っていかなくてはいけない。先ほど川名さんがおっしゃったオープンイノベーションを通じた人材交流なども非常に重要な手法だし、経済産業省では大企業で作った技術シーズを開発者自身がスピンアウトしてスタートアップを作り、社会実装するというカーブアウトプロジェクトを始めた。こういったさまざまな政策を含めて大企業のアントレプレナーシップ、ゼロから1を作る気風を作っていくことができれば、日本はまた復活することができる。