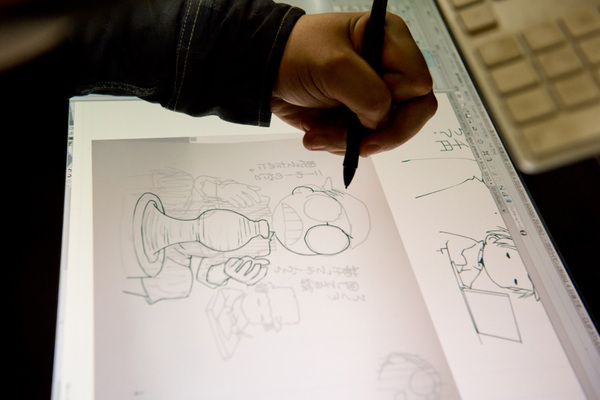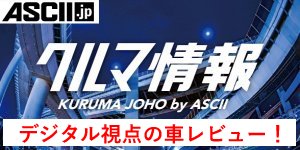ソシャゲ課金マンガプロジェクトの裏側を探る(後編)
1本のマンガを描くにはどれだけのコストがかかるのか
2016年05月01日 17時00分更新
マンガの流通手段は電子でもファンディングでも、なんでもいい
――その1/4000人にどうマンガを届けるかという手段は?
はまむら:それが難しいんですよね。「こんなマンガ、誰が読むんだろう?」と思うような作品を「こんなマンガを待っていた!」と喜んでくれる読者につなぐことができれば、出版物としては大成功。その手段は流通でも電子でもクラウドファンディングでも、なんでもいいんです。
漫画家は自分の作品を望んでくれる読者に届けられるよう、最適な方法を模索する必要があります。今回僕らはクラウドファンディングをやってみましたが、万人にオススメとは言いません。「出版社が相手をしてくれないし、自分で出したほうが儲かるんじゃないか?」みたいな安易なキモチで始めると、痛い目を見るはずです。
ミリオンセラー作家でもない限り、むやみやたらと出版しても1/4000の人に届くわけがないので、少しでも自分に向いていて、売れる確率の高い流通を引き当てるようにするのが、デジタル時代の漫画家として食べていくコツだと思います。
――流通方法の重要性はわかりました。マンガ自体の価格設定は?
はまむら:マンガに限らず、娯楽の価値は作品そのものに存在しているのではなく、受け取る人が「どれだけ楽しんだか」によって決まります。500円の人気マンガを一切読まない人が、3000円もする薄い同人誌をポンと買っちゃうことってよくありますよね。つまり、娯楽の価値とはそういうことなんです。「エロければ売れる」「旬なネタだから売れる」は否定しませんが、僕はそれだけではなくて、読者が見出す「楽しさ」にマッチするから売れるんだと思います。
――マンガの制作費はどれくらいだと黒字か
はまむら:マンガの制作費は20年前と今では状況が違います。昔はペンで紙に描いていたため、紙代や画材、トーンなどの部材費がかかります。でも、現在僕らはデジタルで作業しているので、それらはPCや液晶タブレットなどの機材費に代わりました。
――昔より今のほうが経費はかからない?
はまむら:一概には言えません。デジタルでマンガを制作するとなると、昔に比べたら高額な初期投資が必要になります。少し前、〆切に追われて忙しいときに突然液晶タブレットが壊れたんです。あのときは大急ぎで修理に出して、とてもお金がかかりました。それに、ふだんからパソコンのトラブルにもきちんと対応しておかなければなりません。
――もしトラブルが起きたら
はまむら:泣きながら修正するしかないです……。本来であれば何ページも描ける時間を、パソコンの修理に取られるのはストレスです。そうならないためにも、昔は考えなかったデータ共有用のサーバーを運用したりと、バカにならないコストがかかります。漫画家がみんなパソコンに詳しいわけではないので、苦手な人にとってはめんどうな時代です。
――はまむらさんたちは、パソコンは得意ですね?
はまむら:昔からパソコン大好き&アスキー大好き少年でしたから、ほかの漫画家さんたちより有利かもしれませんね。
――ありがとうございます(笑)。そのほか制作にかかる費用は
はまむら:マンガを描くためには取材が必要ですが、取材にかかる交通費などは、すべて原稿料の中から捻出しています。僕らは写真の資料をよく使うので、自分で撮影したり、カメラマンから提供を受けたりします。それらに発生するコストも、すべて原稿料から払います。

この連載の記事
-
第2回
エンタメ
漫画家がクラウドファンディングを始めてからわかったこと -
第1回
エンタメ
「エロゲの太陽」作者がクラウドファンディングでマンガを描く理由 - この連載の一覧へ