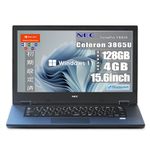ネットが封建時代になってきた
たとえばクックパッドや食べログなどの投稿サイトは従来、検索エンジンと密接なつながりがあったサービス。しかしスマートフォンで「アプリ」単位になったことで、コミュニケーションはサービスの中に閉じこめられつつある。
むかしといまを比べると、検索からやってくるお客さんは激減したという。結果、見知らぬ人との出会いが限定的になりつつあるという話になっている。
それまではウェブブラウザーをプラットホームとしてつながっていたウェブサービスが、アップルやグーグルのストアによってバラバラに分断された。結果コミュニケーションはそれぞれのサービスに閉じたものになり、Facebookのような巨人が“巨大な村”を作ることになっていったわけだ。
LINEのように自分たちの中でふたたびプラットホームを作りなおそうとするプレイヤーもいるが、基本的にはアップルやグーグルが引いたルールの中で勝負しなければならない。土俵そのものが変えられないのだ。
講演の中では「ネットのデモクラシーがスマホとアプリで封建時代になった」なんて表現も使われていたが、実際そんな感じもする。
そんな中「インターネットの可能性に魅了された人たちの夢はどちらかというとパブリックなサービスだったんじゃないか」と近藤会長は振り返る。
「ブログを書いていたら作家になるとか、その人の本来持っている力を最大化して広げてくれるのではないか、というところに可能性を感じたんじゃないか。そういう可能性に魅せられた人がユーザー投稿型サービスを作ったのが前半の歴史。権威のある先生ではなく、いち個人が書くことでも人の役に立つ。可能性みたいなものを引き出そうというところに前半の流れがあったんじゃないか」(近藤会長)
インターネットで情報の発信と受信の効率を高めるため、はてなはさまざまなサービスを開発してきた。サービスが媒介する情報をめぐって発信者と受信者がコミュニケーションをしたことで、やがてコミュニティができあがった。
ふりかえれば、ハロプロファンとはてなアンテナの関係性も、まさに近藤会長が言った「インターネットの可能性に魅了された人たちの夢」に近いものがある。コミュニティとは、IT起業家たちがめざした理想のことなのかもしれない。
※お詫びと訂正:初出時、近藤淳也会長の肩書を社長としていましたが、会長の誤りです。関係者の皆様にお詫びするとともに訂正いたします。(15日)