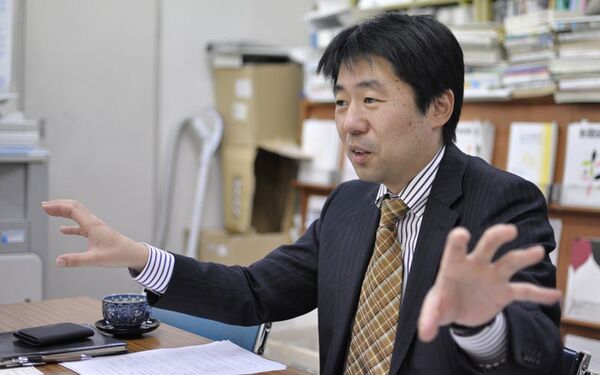電子出版は雑誌書籍の“抱き合わせ販売”を解体する
――「本」の買われ方も変化しそうです。iTunesが「音楽の聴き方」を変えたように、来るべき電子出版も「本の読み方」を変えてしまうかもしれません。iTunesではCDのように複数の曲がセットで売れるのではなく、1曲単位で購入される傾向があります。本も1巻、2巻といった単位ではなく、1話、1章という具合に細分化して販売される方向もありえます。そうなった場合、出版社はどのようにモノ作りをし、マーケティングを行なっていけば良いのでしょうか?
星野 これは電子化全般に言えますが、コンテンツや機能は細分化される傾向にあります。わかりやすい例で言えば、週刊誌はいわば「抱き合わせ販売」でした。
グラビアがあり、ゴシップがあり、コラムもある、そういったコンテンツのバンドル型モデルで消費されてきたのですが、ネットの世界ではそのようなモデルはあり得ません。ネットでは目的のコンテンツだけをピックアップして消費していくわけです。
産業の規模=価格×流通量と考えると、コンテンツがアンバンドル(分解)された結果、価格や流通量にどのような影響を与えるのか、というとらえ方をする必要があります。
グーテンベルクの印刷技術の普及によってコンテンツの流通量は爆発的に向上しました。一方でひとつひとつのコンテンツの価格は、生産コストが下がる訳ですから必然的に下降しますが、産業規模としては飛躍的に大きくなったわけです。
私はこれから電子出版で起こる変化も同様であると考えています。ただし、これまで見てきたように、現在出版に関わっているプレイヤーがそのまま電子出版にも関われるとは限りませんが……。
Googleブックスは絶版書籍の公開から進む?
――広告レベニューシェアモデルについてはいかがでしょうか? 例えばGoogle ブックスは、本の内容をネット上に公開し、読まれた量に応じて広告収益を分配するとしています。
星野 これまでの商習慣からするとちょっと馴染みにくいかもしれませんね。モノを作って動かすことでビジネスが成立するという感覚を持つプレイヤーが多いなかでは、異質に感じてしまいます。実際、個人ならともかく会社組織が満足する予測可能な売上げが上がるかどうかもまだよく分かりません。
――Google自身が提案しているように、絶版となっていて、現状全くビジネスが動いていない書籍を委ねることで、多少なりとも収益を上げることを期待する、ということならばありかもしれませんね。
星野 そういう方向ならば。また、無名な書籍をまずは知ってもらうために無料(広告分配モデル)で、という方法もあるかと思います。ただ、新刊など数字(売上げ)を求められる商品を載せるには、まだまだ既存のプレイヤーがうまく使いこなすイメージが持てないのも事実です。あまりにも市場原理主義のような気もします……。むしろ、絶版という形で権利を死蔵させない工夫と努力を出版社に求めたいところです。
出版社の本質に立ち返るべき
――出版社をある意味支えてきた取次のキャパシティが限界を迎えつつある、というお話が先ほどありました。そうなると、出版社が持つ重要な機能=著者というクリエイターを育成する機能が損なわれないのかも心配です。
星野 欧米との違いとして、アドバンス(印税の前払い)の有無があります。欧米の場合は、企画から実際の支払いまで2年近くかかることもあり、著者を押さえるためにアドバンスを支払っている意味合いが大きいのです。日本は支払いが比較的短い周期で行なわれますので、アドバンスという考え方がありません。
取次からの前倒し入金に依存していては自転車操業となってしまう、というのは先ほどお話しした通りですので、たとえ電子販売に移行していき、取次の存在感が小さくなったとしても、出版社はそのクリエイティブの源泉である著者に対する報酬をいかに確保していくかを最優先課題として解決する必要があります。そういった観点からも取次に依存していてはいけないのです。
電子出版によって、限界コストが下がることは間違いありません。しかし、いまの出版社は紙の出版を前提にしたコスト構造になっています。先日、池田信夫氏・西和彦氏が電子出版専業の「アゴラブックス」を設立しましたが、そういった新進の組織とどうコスト面で競争していくのかは大きな課題であると言えます。
講談社もベンチャー企業だった
――先ほどの価格×流通量のお話しで言えば、電子書籍専業であるからと言って、著者に還元される利益が急激に大きくなることはなさそうですが、一方でリストラなどに頭を悩ませるよりも、いろいろなチャレンジができてやりがいはありそうです。
星野 講談社(1909年設立・当初の社名は大日本雄辯會<ゆうべんかい>)を創業した野間清治氏のエピソードが思い起こされますね。
講談社さんは現在、国内最大手の出版社ですが、創業当時は博文館という巨大な出版社が存在し、取次・印刷・広告・紙業などを垂直統合した強大なビジネスモデルを構築していました。それに対して野間氏は、「講談倶楽部」に代表される大衆誌や辞典を断続的に創刊・展開するコンテンツの水平展開モデルで攻めていき、ついには勝利したのです。
つまり、講談社さんも巨大な既存のプレイヤーに対して、新しい手法で戦い勝利を収めたベンチャー企業だった訳です。では、いまの講談社さんはいったいどちらの立場にいるんだろうか、と考えると……(笑)。
――同様のことは、IT業界でも起こっていますね。Microsoft→Yahoo!→Google→Twitterとイノベーションが受け継がれてゆく様にも似ています。
星野 出版社はもともとアウトソース型の事業構造でした。私は電子出版でも印刷会社の協力が欠かせないと考えています。EPUBへの対応、そして複数のデバイス・メディアへの展開を行なう際には、そういった「外の力を上手く使う」という出版社の強みは今後も有効だと思います。
国内出版社の強みは、著者との近さ
――ウェブでいうところのマッシュアップ型のビジネスモデルとも通じるところがあるかもしれません。ところで、書籍は例えば映像化の際の原作として、権利ビジネスの源泉でもあります。私自身、映像業界にいたこともあり、外から見るとその潜在力は相当あると感じられるのですが、そういった面での改善策はあるのでしょうか。
星野 中長期のトレンドとして、書籍単体では下降傾向が続くのは間違いありませんので、それに抗うには、映像化のようなマルチ展開、そして海外展開で一コンテンツからの収益を拡大するしかないと思いますね。集英社が2008年度の段階で、広告収入とそのほか売上げが150億円で拮抗するようになりました。週刊少年ジャンプから生まれるコンテンツの権利の活用を積極的に進めた結果だとみています。
日本の出版社の強みは、エージェントを介す海外の出版社と比較して、著者と直接やり取りをする、その距離の近さです。したがって、権利を死蔵させるのではなく、著者と密にコミュニケーションをとって、著作物、つまり権利の再活用を積極的に図ることが本来できるはずなのです。
「コンテンツを再生産する構造を回すために利益を最大化することを常に考えている」という出版社の本質に立ち返って、この先の変化に立ち向かい、逆に活用していくことに期待しています。

この連載の記事
-
第102回
ビジネス
70歳以上の伝説級アニメーターが集結! かつての『ドラえもん』チーム中心に木上益治さんの遺作をアニメ化 -
第101回
ビジネス
アニメーター木上益治さんの遺作絵本が35年の時を経てアニメになるまで -
第100回
ビジネス
『THE FIRST SLAM DUNK』で契約トラブルは一切なし! アニメスタジオはリーガルテック導入で契約を武器にする -
第99回
ビジネス
『THE FIRST SLAM DUNK』を手掛けたダンデライオン代表が語る「契約データベース」をアニメスタジオで導入した理由 -
第98回
ビジネス
生成AIはいずれ創造性を獲得する。そのときクリエイターに価値はある? -
第97回
ビジネス
生成AIへの違和感と私たちはどう向き合うべき? AI倫理の基本書の訳者はこう考える -
第96回
ビジネス
AIとWeb3が日本の音楽業界を次世代に進化させる -
第95回
ビジネス
なぜ日本の音楽業界は(海外のように)ストリーミングでV字回復しないのか? -
第94回
ビジネス
縦読みマンガにはノベルゲーム的な楽しさがある――ジャンプTOON 浅田統括編集長に聞いた -
第93回
ビジネス
縦読みマンガにジャンプが見いだした勝機――ジャンプTOON 浅田統括編集長が語る -
第92回
ビジネス
深刻なアニメの原画マン不足「100人に声をかけて1人確保がやっと」 - この連載の一覧へ