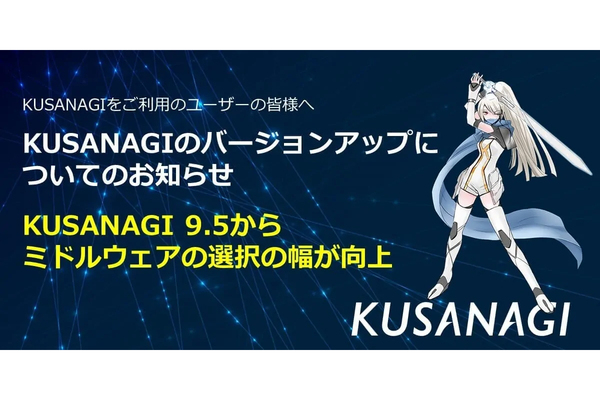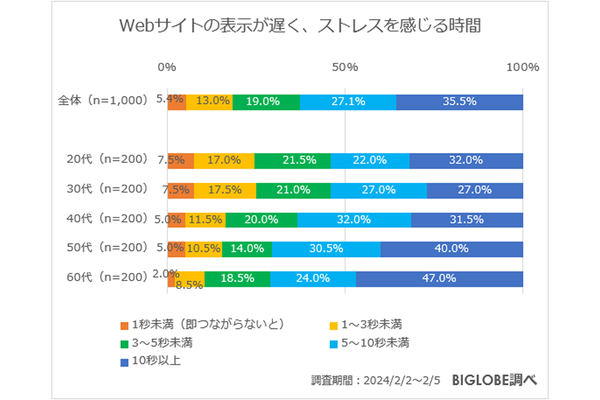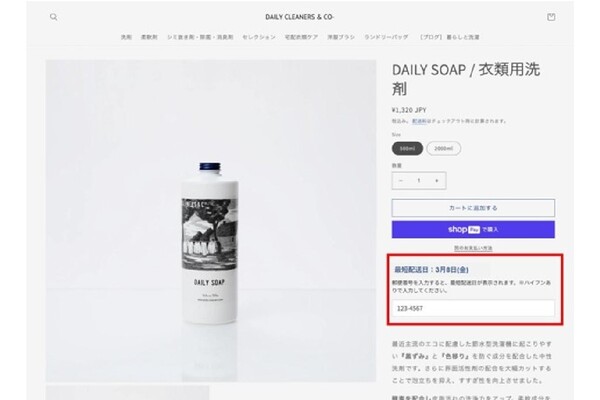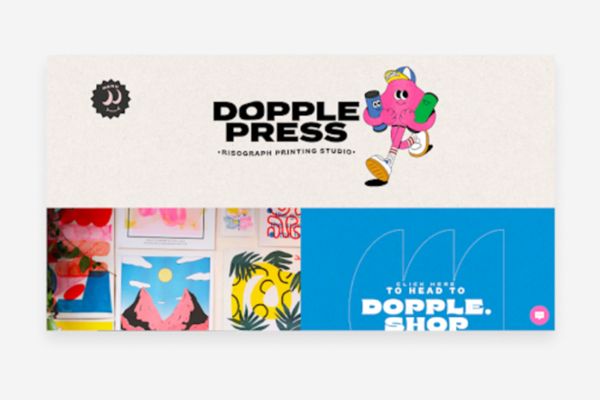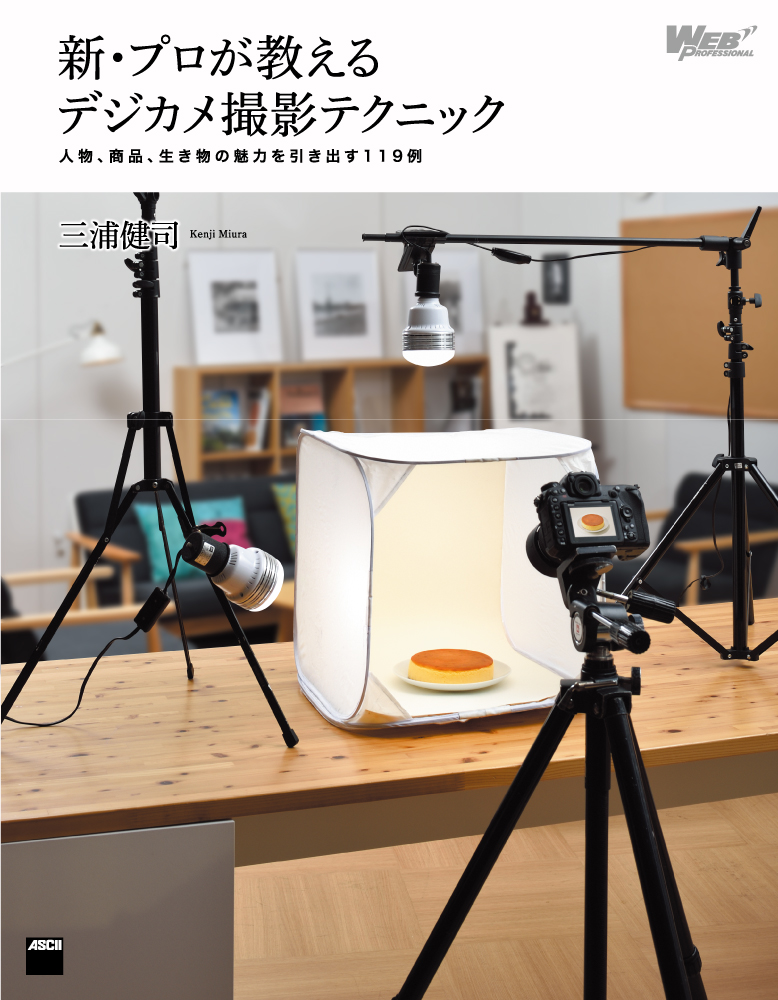さて、第1回では「顧客を理解しましょう」というテーマでお話しました。
今回は、どのようにメールを使って、質問するかの実例をあげたいと思います。
CASE1:商品開発についてニーズを聞く場合
ある素晴らしい商品を開発しようと思っているとします。企画者はすでにその内容にほれ込んでいて、「きっと売れるに違いない」と考えています。その勢いで商品を開発して、結局は売れなかったということは非常によくあるケースです。失敗は成功のもとといいますが、何度も失敗を重ねていては、お金も時間もなくなってしまいます。
そんな時には、その商品のアイデアが出た時点で、つまり商品の開発をする前に、ターゲット層に聞いてみるのです。
「こんな商品を開発しようと考えています。ほしいですか、いくらなら買いますか?」
もう、堂々と聞いてしまいましょう!
それで、「欲しいとは思わない」とか「よくわからない」とかいう回答ばかりであれば、まず売れません。そのようにして、実際に開発に時間やコストをかけることなく、開発に踏み切るのか、やめるのかを判断できます。
ターゲットが「それはいいね、ぜひ欲しい」と言えば、成功する確率は高くなります。ぜひ、やってみてください。
CASE2:競合よりも売れていないので、その理由を聞く場合
自社の商品が、どうしても競合に負けている質や機能で勝つぺきなのか、それとも価格で勝つべきなのか、その方向性が定まらない
こんなときも、やはり、顧客に聞きましょう。
「その商品で一番の購入のポイントになるところは、なんですか?」
「A社の商品と当社の商品を比べてどちらを買おうと思いますか、その理由はなんですか?」
やはり堂々と聞いてしまいましょう。
売り手にはわからなかった理由が出てきます。それを改善の方向にするべきか、検討できるようになるでしょう。
CASE1もCASE2も、結局は「顧客を理解する」ことなのです。
CASE3:「適正価格」を聞く場合
最後に「適正価格」を聞く場合です。
値づけには「コスト+利益幅」という売り手の考え方がありますが、これは顧客の視点を無視しています。
顧客は「安いにこしたことはない」と思う半面、「このような価値がある商品だったら、いくらなら出してもかまわない」という判断もするものです。
こうした顧客の考える適正価格をはるかに超えるような価格をつけても結局は売れませんし、逆に安すぎても顧客は品質に疑問を持つことでしょう。
商品コストがかかるからというのは、売り手の論理です。
顧客の視点からみての適正価格になるように、コスト構造を作ることも商売人の務めです。
ですから、「この商品はこのようなメリットがあるけれども、いくらまでなら購入したいと思いますか?」と聞きましょう。
このように、顧客に聞くことで、無駄の時間をたくさん省けるのです。
次回は、「商品に対するニーズ」について考えましょう。
著者プロフィール

| 名前 | 紙田 昇 | |
|---|---|---|
| 会社 | ピーアールジャパン株式会社 | |
| サイト | http://www.prjapan.co.jp/ | |