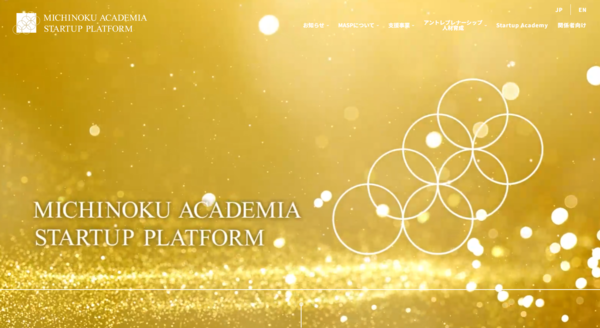日本のディープテックはどこへ向かうのか――大学発・人材・標準化──全5セッションが描いた“日本の課題と可能性”
初開催「ASCII STARTUP TechDay 2025」レポート
ASCII STARTUPは2025年11月17日、国内のディープテックエコシステムを次のステージへ押し上げることを目的としたイノベーションカンファレンス「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催した。会場には研究者、起業家、投資家が集まり、ディープテックの“今とこれから”を多角的に議論。基調となる東京大学FoundXディレクター・馬田隆明氏の講演を皮切りに、アカデミアピッチやパネルディスカッションなど全5セッションが繰り広げられた。
なお、馬田氏の視点や問題意識については、以前のインタビュー記事「小さな成功はもはや通用しない。東大FoundX馬田氏が警鐘を鳴らす、起業家が今“頭を切り替えるべき”理由」でも詳しく語られている。あわせて参考にしてほしい。
東京大学 FoundXディレクターの馬田隆明氏による基調講演のテーマは「ディープテックエコシステムの『解像度を上げる』」。
IT分野の成功体験が一巡し、新たな成長領域としてディープテックへの期待が高まっている。一方、その大きな期待が誤解や過度な楽観につながり、“バブル的な盛り上がり”に向かっているのではないか──。馬田氏はそんな問題意識を提示したうえで、深さ・広さ・構造・時間という四つの視点からディープテックを読み解く重要性を強調した。
「ディープテック・バブル」を避けるために──馬田氏が提示した問題意識
講演の前半は、まず「そもそもディープテックスタートアップとは何か」という根本的な問いから始まった。馬田氏は、深い研究開発を必要とする“ディープテック”と、短期間で急成長することを前提に設計された“スタートアップ”は本来別の概念であり、この2つのANDが満たされて初めて「ディープテックスタートアップ」と呼べるのではないかと整理する。
大学発ベンチャーが年々増え、数の面では伸びているように見える。しかし、売上1億円以上に達する企業は例年全体の約15%、10億円を超える企業はわずか1~2%にとどまり、その割合はほぼ変わっていない。数字を見る限り、日本の多くの大学発企業は、理想とされる“スタートアップ”のサイズに到達していないと言える。「総数は増えている。しかしこれまでと同様の大学発企業のやり方のままでは、大きな社会からの期待には応えられず、いずれ信認を失う」と馬田氏は危機感を示す。
研究の価値と事業の価値は“別物”──伸び悩む理由の核心
では、なぜディープテックの売り上げが伸びにくいのか。馬田氏はその背景に、「先端技術の商用化を行う起業」と「ハイグロース・スタートアップとしての起業」がしばしば混同されている点を挙げた。研究の世界で高く評価される技術が、必ずしもビジネスとして高い価値があるとは限らない。技術は顧客が利益を出していくための手段の一部でしかなく、先端技術がどの程度顧客の事業的な価値に結びつくのかを見極める必要があると指摘した。
さらに、大きな市場で勝てるかどうかも重要な視点だという。「この技術なら勝てる」という主張は正しいかもしれないが、仮に勝てても市場が小さければ事業としての伸びは限定される。馬田氏は「大学の技術の商業化だけを考えるのではなく、大きな市場にフィットするのかを重視するべきだ」と強調した。
人材構造の限界──担い手不足が生む“成長の天井”
講演の後半では、日本特有の“担い手不足”という構造的課題にも踏み込んだ。国内には理工農医系の研究室が約4万あると推定されるものの、テニュア(大学教員の終身雇用権)を取得した教授が起業する例は少ない。約1万5000人いるポスドク(博士号取得の任期付き研究員)は、研究室の数に対してすら少なく、ポスドクが起業すると研究室の研究が途切れるリスクがあるため中心的役割を担いにくい。
研究者の人数やキャリア構造を踏まえると、大学内部だけでディープテックスタートアップを生み続けるのは難しく、仮に博士人材が数割増加して、そうした人材向けの起業研修を増やしたとしても、毎年生まれるスタートアップの総数には限界があるという。「だからこそ、やり方を変えなければならない」と馬田氏は語る。
技術起点から“逆算型”へ──日本で求められる新しい方法論
日本では、どのような方法論があり得るのか。
馬田氏は、米国型のスタートアップ育成アプローチをそのまま日本に輸入するのではなく、日本流のアプローチを模索すべきだと提案した。米国は研究者も多く、数多くの起業家が自然発生的に生まれ、確率的な大成功を狙うアプローチを採用できる。しかし、日本の研究者は相対的に少ない。
そこで大学外部の起業家人材との協力が重要になるが、ディープテック領域で起業する起業家はいまだ少ない。そうした起業家が希少だからこそ、単なる先端技術の商業化での起業を促すのではなく、“成功したときの規模”や市場を強く意識してもらうような働きかけがより重要になる。
実際に近年では、経営者候補が技術シーズを探しに行くケースや、投資家が市場ニーズから逆算して必要な技術を取りに行く“市場起点”の手法の試みが始まっている。最初に想定される顧客にアイデアを持ち込み、購買契約を取った後に必要な技術を研究開発する「逆算型事業設計」もその一例だ。
締めくくりに馬田氏は、「日本からディープテックスタートアップの成功例を継続的に出していくためには、期待を上回る成果を出して、好循環を作り出す必要がある。そのためには期待が過剰すぎてもいけないし、課題のあるやり方に資源を注ぎ込んで拡大しても、あとでそのつけを払うことになる。正解へと近づくためには、概念の整理をきちんと行ったうえで現象を理解しようと努め、失敗から学び、新しい仮説を作って、仮説検証をし続けなければならない。それこそがアカデミアとスタートアップに共通する態度であり、方法論でもあるはずだ」と語った。
単なる技術トレンドとしてではなく、研究者・企業・投資家・政策のすべてが連動するエコシステムとしてどう成長させるか。その方向性を示すセッションとなった。