送り状の電子化が進む中国 周回遅れの日本と比較する
本記事はユーザックシステムが提供する「DX GO 日本企業にデジトラを!」に掲載された「送り状の電子化など発送業務の今後は?日本と中国の現状の違いから考える」を再編集したものです。
社会でDX推進が進むなか、さまざまな書類や業務の電子化が広まっていますが、発送業務においては日本では送り状をはじめ、いまだ紙が使われているケースが多く見られます。しかし、日本の現状とは対照的なのが中国です。中国は、すでに2017年には個人情報保護の観点から送り状の電子化に取り組み、今ではスマート物流が中国の巨大EC市場を支えています。
ここでは、日本と中国の発送業務の現状を比較するとともに、送り状を電子化することで、どのような効率化が実現できるのかを紹介します。
送り状の電子化が進まない日本における発送業務の現状と課題
送り状の電子化が進まない日本における発送業務には、下記のような現状と課題があります。
■アナログ処理による作業の非効率性
送り状はいまだに多くの企業でアナログ処理されており、作業が極めて非効率なものとなっています。手作業による作成やシステムへの手入力など、処理しなければいけない送り状の数だけ反復作業が頻発し、またその受け取りや持ち運びのための移動も発生しています。
こういったアナログ処理を電子化することで、多くの作業をPC上で完結することが可能になります。文字のデータ化や自動入力などの機能により、複数の送り状でも簡単かつ短時間で作成できるようになるでしょう。最終的には送り状の作成作業全体を自動化することで、作業効率のさらなる向上が見込めます。
■ヒューマンエラーの発生
送り状の手作業による処理は、個人の能力や体調などによって品質にバラつきが出ることがあります。ヒューマンエラーの発生により、業務が滞ったりクレームへつながったりして、会社として損害を受ける可能性もあるでしょう。
電子化して入力作業を自動化することで、品質が保たれ、ヒューマンエラーの防止にもつながります。
■労働環境が新しい働き方に対応できていない
送り状をアナログで処理した場合、問い合わせ対応もアナログで処理することになります。問い合わせがあった際に、内容確認のため大量の紙の送り状から目当ての送り状を探し出さなければなりません。また、控えは通常社内に保管されているので、問い合わせ対応のためには出社が必須となります。これでは、昨今求められるリモートワークなどの多様な働き方への対応も困難です。
送り状を電子化すると、目当ての送り状を探す際にも検索機能で容易に見つけることができます。また、社内にいなくてもさまざまな処理が可能で、多様な働き方にも対応しやすくなるでしょう。
送り状の電子化が進んでいる中国における発送業務の現状
中国では物流の効率化が進んでいます。日本とどのような違いがあるのか、その現状を紹介します。
■デジタル送り状の普及
中国では、過去に紙の送り状を原因とする個人情報の流出事件が起きました。配達員が送り状に記載されている個人情報を収集し、転売したのです。この事件により、紙の送り状では個人情報が配達員を含む他人の目にさらされやすいことの危険性が認識され、個人情報保護の観点から送り状のデジタル化が進みました。情報が保護されたバーコード、QRコード、特殊記号などを活用することで、容易には個人情報を確認できないようになっています。
■デジタルテクノロジーの活用
中国では、2000年代に入り急激に人件費が高騰しました。また、IoTやデジタル機器の開発により、ECが急速に発展し、物流が活発になっています。以上のようなことから、物流業務に効率化が求められるようになりました。AIやIoT、ロボット、無人搬送車(AGV)、ドローン、電子タグなど、電子化を進められるテクノロジーの活用が進み、物流業務の効率化が進められています。
■政府のあと押し
中国では政府自ら物流の効率化に積極的に取り組んでおり、道路、鉄道、水路など輸送インフラ網の長さや質を向上させ、物流を支援しています。また、ソフトウェア・情報サービス産業の発展を目的に企業の誘致や集積を進めており、それが前項で紹介したようなテクノロジーの発展を促しています。以上のように、政府として発送業務が効率化されるような施策を積極的に行っており、企業における発送業務の効率化をあと押ししています。
送り状の電子化を含めた発送業務の効率化
日本でも中国のように発送業務の効率化を進めていくには、どのような取り組みが必要でしょうか?
送り状の電子化を含め、主なものを紹介します。
■スマート物流の実現
スマート物流とは、デジタルテクノロジーにより物流プロセス全体を最適化することです。
スマート物流には物流システムなどデジタルツール活用による効率化だけでなく、データ分析による予測や自動化、またその持続性も含まれます。中国ではすでにスマート物流が浸透しており、IoTによるデータ収集、自動運転車やドローンを用いた無人配送などが実現されています。送り状の電子化もスマート物流の取り組みのひとつです。送り状の電子化により情報のやりとりがシステム上でできるようになり、後工程のピッキングや納品などへの情報伝達もスムーズになり、物流プロセス全体が最適化されます。
■物流システムやインフラの整備
スマート物流により物流プロセス全体を最適化するには、物流システムやインフラの整備が重要です。
物流における一連の工程を効率化するための下記のような物流システムを導入し、データ連携・活用も含めたスマート物流の実現につなげていく必要があります。
・倉庫管理システム(ピッキングシステムなど)
・在庫管理システム(在庫トラッキングシステムなど)
・実績収集システム(ハンディーターミナルなど)
・出荷業務システム(送り状発行システムなど)
など
また、倉庫やトラック、運搬機器などの物流インフラも同様に整えていかなければなりません。
ただし、以上のような取り組みについて一企業ができることには限界があります。物流の課題は一企業で解決できるものではなく、業界全体での取り組み、あるいは自治体や国の支援も必要です。
物流におけるデータを広く連携させ、物流全体を最適化させる取り組み「物流MaaS」が、昨今日本でも注目されています。物流業界の課題解決のために大きく期待されている物流MaaSについての詳細は、次の記事でご確認ください。
物流システムの再構築のヒントは、次の記事をご覧ください。
失敗しない物流システムの導入方法とは
発送業務のデジタル化による業務効率化が、物流部門のコスト最適化のポイントになります。詳しくはeBookでご確認ください
【eBook】物流部門のコスト最適化を進めるためにはなにが重要か?発送業務のデジタル化による業務効率化
送り状の電子化は発送業務全体・さらには物流全体の効率化への第一歩
物流の効率化が進んでいる中国と比較すると、日本ではアナログ処理している部分も多く残っており、まだまだ改善の余地がありそうです。中国における取り組みを参考にし、テクノロジーを活用して効率化を進めていきたいところですが、どこから手をつければいいかわからない場合もあるでしょう。
そのような場合には、まずは送り状の電子化から着手するのもひとつの選択肢です。送り状が電子化されれば、そこから得られるデータをその後の工程で活用しやすくなり、発送業務全体の効率化にもつながります。そして、物流システムやインフラが整備されていれば、データの活用の幅もさらに広がり、物流全体の効率化が実現できるでしょう。
送り状の電子化に役立つツールのひとつに、送り状発行システム「送り状名人」があります。帳票の種類や運送EDIの有無など、運送会社ごとに異なる形態にも、スムーズに対応できます。
詳しく知りたい方は、下記よりご覧ください。
また、送り状発行業務の改善事例集を無料でご提供しています。必要な方は下記よりダウンロードしてください。
送り状発行業務改善事例集&運送EDI e-Bookダウンロード
発送業務・物流全体の効率化については、次の記事も参考になります。ぜひご覧ください。
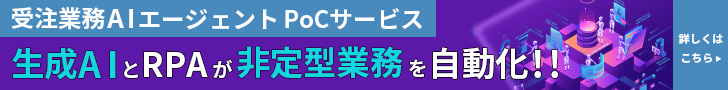
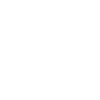 お気に入り
お気に入り
