物流・商流データが標準化されたオープンプラットフォームをベースに
荷主が物流を自由に選べる時代に ヤマトHDと富士通の“共同輸配送”が始動
2025年01月29日 07時00分更新
慢性的な人手不足やCO2排出量の削減などの社会課題を受け、輸配送の効率化が求められている物流業界。積載率を上げ、車両数を削減できる選択肢として注目されているのが「共同輸配送」だ。単一荷主の荷物を運ぶ個別配送と異なり、複数荷主の荷物を混載して輸配送する方式であるが、荷主と物流事業者をマッチングするプラットフォームが必要となる。
このような状況下で、ヤマトホールディングス傘下のSustainable Shared Transport(SST)は、共同輸配送サービスである「SST便」を、2025年2月1日より提供開始する。同サービスの基盤となるのが、SSTと富士通が手掛ける、物流・商流データが標準化された、誰でも参加できるオープンなプラットフォームだ。
ヤマトホールディングスの代表取締役社長である長尾裕氏は、「持続可能なサプライチェーンの実現には、共有的な物流サービスが提供できるオープンプラットフォームの構築が肝要になる。内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)におけるスマート物流サービスに共に関与した富士通の協力のもとで、社会実装のモデルとなるSSTが動き始めようとしている。これからの展開に期待して欲しい」と語る。
リアル×デジタルで標準化を進めるオープンプラットフォームで「共同輸配送」という選択肢を
SSTは、安定した輸送力の確保と環境に配慮した持続可能なサプライチェーン構築を実現するために、2024年5月に設立。リアルにおける「標準パレット輸送」とデジタルにおける「標準化された商流・物流情報の連携」によるオープンプラットフォームの構築を進めてきた。
SST 代表取締役社長の髙野茂幸氏は、「BtoBの輸送では、貸し切りトラックをチャーターするのがスタンダード。共同輸配送を新たな“選択肢”に入れてもらえるよう、リアルとデジタルの両方で使いやすいプラットフォームを用意する」と説明する。
リアルにおける標準パレット輸送は、ヤマトグループのリソースで先行提供していた輸配送サービスネットワークを引き継ぎ、オープンプラットフォームを活用した共同輸配送サービス「SST便」として、2月1日より提供する。
まずは、宮城県から福岡県間の1日16便の運行において、標準パレットスペース単位で利用できる「混載輸送」「中継輸送」「定時運行」からなる拠点間の幹線輸送を展開。拠点となるのは、宮城、福島、厚木、浜松(中継地)、京都、広島(中継地)、福岡の7か所だ。
混載輸送は、複数社の荷物を積み合わせるパレット輸送で、積載率を向上させる。中継輸送は、単中距離のリレー輸送であり、高稼働を確保しつつ、労働時間の短縮につなげる。定時運行は、幹線拠点からの定時運行であり、安定した稼働と輸配送能力を確保する。加えて、地域の物流事業者と連携して、拠点からの「域内配送」も提供する。
これらの輸配送における、オペレーションやハードを標準化して、複数事業者間で共有することでサプライチェーンの効率を高めていく仕組みになる。今後は、既存線便のダイヤ数の拡充に加えて、鉄道や船舶などマルチモーダルも活用しながら、エリアを拡充していく予定だ。
この共同輸配送サービスを利用するためのシステムでは、荷主企業が、出発地や到着地、荷物情報などを入力することで、“電車検索のアプリ”のように候補の便が表示され、予約・手配状況もリアルタイムで可視化される。
荷主企業は、共同輸配送のパートナーを自ら探すことなく、同一区間で最適な時間帯や輸送手段を選択でき、安定した輸送力を確保できる。物流事業者は、復路の空車走行の減少といった積載率や稼働率の向上や、ドライバーの負担軽減を図れるようになる。
サステナブルなサプライチェーンを実現する業種・企業の壁を超えるデータ基盤
この共同輸配送を支えるシステムおよびオープンプラットフォームは、SSTと共に富士通が構築している。同社は、社会課題を起点とした事業モデル「Fujitsu Uvance」を展開しており、異なる業種や企業間のデータ活用基盤を構築してきた。今回のシステムでは、同モデルにおいて物流業界の社会課題に対応する「Fujitsu Unified Logistics」のデータ基盤を活用した。
富士通の代表取締役社長 時田隆仁氏は、物流業界における課題について、「サプライチェーン上には、業種の異なるさまざまな企業が携わっているが、企業や業種間においてデータが十分に連携できていない。サプライチェーン全体の業務効率化や意思決定のスピードアップには、データをスムーズに、そしてスピーディーに共有する必要がある」と語る。
また、これまでの物流プラットフォームでは、商流の情報、いわゆる物を発注する情報が、物流の情報とつながっていなかった。つまり、「頼んだものが、どのトラックに入っているかが直前にならないと分からない」(SST髙野氏)という状況に陥っており、過剰な検品や受け入れ準備の遅れ、荷待ち時間の発生など、さまざまな非効率が発生していた。
これらの課題を解決するのが、構造や仕組みが標準化され、誰もが参加でき、かつ安全にデータの流通ができる、SSTと富士通が構築したプラットフォームだという。この基盤上で物流情報と商流情報を一体的に管理できるようになることで、サプライチェーン効率の向上が見込める。
このシステムとオープンプラットフォームの特徴は3つある。
ひとつは、「物流・商流データの標準化」だ。内閣府の物流サービスプロジェクトにおける「物流情報標準ガイドライン」に準拠することで、これまで業種や企業単位で最適化されていたデータを自動的に標準化して、データ連携を円滑にする。これにより、企業間での情報の受け渡しで要していた作業やコストを削減できる。
2つ目は、「ブロックチェーンによるデータの信頼性担保」だ。外部からの閲覧を防止して、第三者からの改ざんに対する検知・対応・復旧が可能になる。企業をまたぐデータ連携においても、データを保有する企業がアクセス権限を設定できるなど、セキュリティを担保できる。
3つ目は、「データとAIによる物流アセットの最大化」だ。収集した荷主の情報と物流事業者のデータとAIを活用することで、車両やドライバー、利用拠点の配置を最適化できる。
今後の展開について富士通の時田氏は、「このオープンプラットフォームを他業種のデータ連携の基盤と組み合わせて、クロスインダストリーなデータ連携の仕組みを構築し、より多くの社会課題に貢献していきたい」と語る。また、荷主企業としてもSST便を活用する予定であり、「サプライチェーン全体の最適化には、荷主側や物流事業者側も、発想の転換や行動変容が必要。荷主企業としても、行動変容を起こしていきたい」と指摘した。
SSTの髙野氏は、「SSTのパーパスは、共同輸配送で日本の物流をサステナブルにすること。“物流がビジネスを支えてきた世界”から、“企業がサステナブルな物流を選ぶ世界”に移るための選択肢を提供したい」と言及。「物流の担い手不足、物流におけるグリーハウスガスの削減、この大きな社会課題の解決を、荷主企業と物流企業が協調する共同輸配送の普及が、ひとつの解になる」と語った。






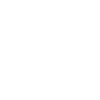 お気に入り
お気に入り































