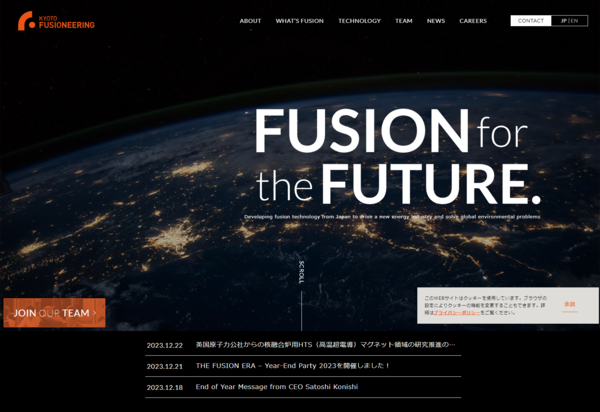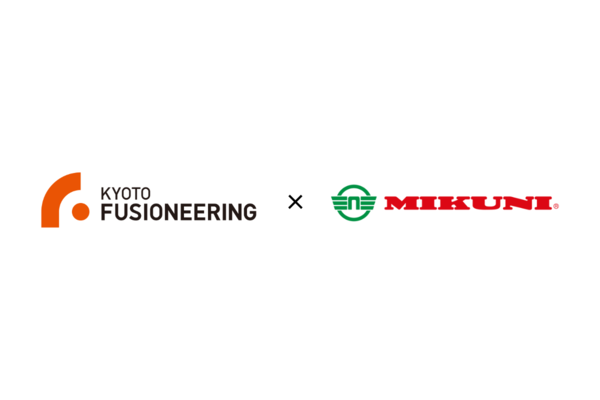グローバルな事業展開を踏まえ知財戦略を検討。世界が注目する「核融合」の早期実現に挑む
京都フュージョニアリング株式会社 代表取締役会長 長尾 昂氏インタビュー
この記事は、特許庁の知財とスタートアップに関するコミュニティサイト「IP BASE」に掲載されている記事の転載です。
京都フュージョニアリング株式会社は、核融合エネルギーの実現に取り組む京都大学発のスタートアップ。核融合炉を構成する機器の開発とプラント全体の設計に関する技術を有し、海外のスタートアップや研究機関と連携して事業を展開している。同社はグローバルでの本格的な事業展開に向け、2021年度のIPASに参加。代表取締役会長の長尾昂氏と知財を担当するコーポレートデザインディビジョン マネージャーの鷲巣敬太氏にグローバル戦略とIPASで得た成果について伺った。

京都フュージョニアリング株式会社 共同創業者 代表取締役会長
長尾 昂(ながお・たか)氏
京都大学大学院工学研究科機械理工学専攻修士課程を修了。 コンサルティングファームArthur D. Little Japanに入社し、新規事業などの戦略コンサルティングを担当。2010年にエネルギースタートアップの株式会社エナリスにて、マザーズ上場、資本業務提携、AIを活用したR&D等を主導。2019年に創業者として京都フュージョニアリングを設立。代表取締役社長として、ラボスケールの研究開発を起点に核融合事業を立上げ、戦略立案、資金調達、人材採用を推進。2023年10月より、代表取締役会長に就任。京都大学 協力研究員。
核融合エネルギーの実現を目指し、核融合プラント技術を研究開発する
二酸化炭素や放射性廃棄物を出さない持続可能な次世代エネルギーとして期待されている核融合(フュージョン)エネルギー。京都フュージョニアリング株式会社は、核融合プラントに関する装置の研究開発・設計に取り組む京都大学発スタートアップだ。同社は、核融合反応を起こすために必要なプラズマ加熱システム、燃料を循環させる水素同位体排気循環システム、核融合炉から熱を取り出すブランケットなどの機器の開発やプラントの全体設計に高い技術力を有し、海外の民間企業や研究機関に提供している。
同社が重視しているのは、技術開発とグローバル化だ。2021年10月には英国、2022年9月には米国に子会社を設立し、各国の研究機関とも連携して技術開発を進めている。2022年7月には、世界初となる核融合発電試験プラント「UNITY」のプロジェクトを発表。自社の研究開発拠点「京都リサーチセンター」内で「UNITY-1」の建設を進めており、2024年末には発電システムの実証が行われる予定だ。さらに、2023年9月にはカナダ原子力研究所と提携し、燃料サイクルシステムに関する共同プロジェクト「UNITY-2」の開発に取り組んでいる。
「UNITYは研究開発のための施設ですが、ショールームとしての位置付けもあります。各国の核融合スタートアップを招き、技術設計を提案するためのプラントとしても想定しています」(長尾氏)
世界でも取り組みが進んでいる。国際的な核融合実験炉プロジェクト「ITER(イーター)計画」では2035年の核融合反応開始に向けて建屋の建設などが進められている。また、米国のスタートアップが2028年までの核融合発電所稼働開始を目指すと発表するなど、夢のエネルギー実用化が現実味を帯びてきた。京都フュージョニアリングも実証実験から実運用へ向けた技術開発へとシフトしている。
「核融合反応が起こるための物理的な条件は、以前に比べて大きく検証されています 。次は、連続運転と、実際にトリチウム(三重水素)燃料を使った実証実験になります。連続運転に関しては、機械の長寿命化、高出力化などが課題です。また、重水素なら対応できるが、トリチウムには対応できない素材があり、その場合は機械を変更しなければいけない。実験レベルではなく、実運用に耐えうる性能、大規模化へ向けての技術開発を進めています」
グローバル化と技術開発を加速するため、経営体制を拡充
2019年の創業以来、代表取締役社長として同社を牽引してきた長尾氏だが、2023年10月からは代表取締役会長に就任。共同創業者であり京都大学名誉教授の小西哲之氏が代表取締役社長という代表取締役2名体制に移行している。新しい経営体制の目的について伺った。
「創業から5年目に入り、従業員が100人を超えました。これまではゼロから1をつくることに大きなリソースがかかっていましたが、2023年5月に約105億円の資金調達を実施して、グローバル化と技術開発に重きを置いていくフェーズに入ったと考えています。ここからは小西のリードで、しっかりと技術開発とグローバル化を進めていただくことが私の一番の狙いです。
海外でビジネスを展開すると、交渉のその場で決断が求められることがあります。代表取締役の2人体制は、会社としての基盤固めというよりも、成長に向けた屈伸運動としての体制強化と考えています」(長尾氏)
加えて、部長格の人材を続々と採用して組織を拡大している。各種役員を抜擢人事し、権限移譲も進めているそうだ。
「餅は餅屋。技術は小西が詳しいですし、英国で起こることは英国で意思決定しなくてはいけない場面があります。そのようなときに権限が集中していたら、意思決定スピードが遅れてしまう。特に海外では個人の裁量が重視されるので、会社をグローバル化していくことも新経営体制の背景です」
ここ2年間で、社員は十数名から100名以上へと急速に増えた。組織の拡大は、研究開発にどのような影響があったのだろうか。
「設立当時は小西に5人ぐらいがついて研究開発の全領域をカバーしていましたが、今は5つほどのチームに分かれ、各チームリーダーを中心にメンバーが専門性を持って研究に携わるようになり、高度な組織化がなされています」
チームによる役割分担により、それぞれが専門性を持った研究に長く携わることで、開発スピードが速まり、品質も上がっているという。
グローバルでの成功にはインナーサークルに溶け込めるかが課題
グローバル展開では、英国と米国にビジネス拠点を開設している。
「単なる営業拠点としてだけではなく、各国政府機関などとの渉外を含め、現地の核融合産業コミュニティに入り込むこともミッションの一つです。グローバルスタートアップはどこも苦労されていますが、特にアジアの企業が欧米で現地の『インナーサークル』に溶け込むには、厚い壁があると感じています。我々は入り込んでいるほうですが、日本と同じレベルにまで持っていきたい」と長尾氏。
海外のVCからの資金調達のためにも、現地のスタートアップコミュニティに溶け込み、認知を高めることが課題だ。
「欧米の機関投資家に『いい会社だね』と言ってもらえる状況に早くなりたい。それには、海外ビジネスに長けた人材を入れるのが早道。米国は比較的流動性が高いので、優秀な人材を獲得する方向で動いています」
費用対効果を踏まえたIPASでのアドバイスで知財戦略の視野が広がった
京都フュージョニアリングは、2021年度の特許庁が主催する「知財アクセラレーションプログラム(IPAS)」に参加している。
長尾氏はIPAS前の知財意識について、「海外特許を取らなければ、という意識は持っていました。小西は何件も特許を取っていますし、ほかにも特許を取っているエンジニアがいますので、会社として予算を配分して海外特許も押さえたかった。しかし、何十件もとなるとコストがかかるので、いいものがあれば取ろう、という短絡的な特許戦略になっていたと思います」と振り返る。
実現まで数十年先という息の長いビジネスのため、特許を取るタイミングが難しい。また、学会論文で公知となっている技術が多い領域でもある。どの特許を押さえていくのが効果的なのか判断に悩んでいたという。
「IPASでは、ビジネス視点での戦略の立て方をアドバイスしていただきました。特許を取るか取らないかという選択肢の中で、どうやって集中的に取っていくか。防衛のため、あるいは技術者のモチベーションを躍動する手段など、特許の使い方にはいろいろな視点があることも教えていただきました。特許事務所に相談すると『いい発明だからまず特許を取りましょう』となりがちですが、IPASでは費用対効果の観点を踏まえて語ってくれるのがありがたかった。一歩引いて、俯瞰的に見たコンサルティングをしていただけたことで視野が広がりました」
IPAS参加後は、海外の知財専門家とも連携して知財戦略を立てている。また、社内で海外の特許戦略についての議論が活発に行われているそうだ。
なお、IPAS後も専任の知財責任者は設置せず、コーポレートデザインディビジョン マネージャーの鷲巣敬太氏が知財を担当している。
「知財専門家はあえて入れていません。というのは、我々の場合は特許を取得するだけではなく、事業戦略を実行する上でどのような知財を取得し利用するかを考える必要があります 。鷲巣には、自社の事業にとって何を取るべきか、取らないべきか、あるいはパートナーに取ってもらった方がいいのか、などを多面的に検証してもらっています」
最近は、カナダ原子力研究所との提携など外部との 共同研究が増えてきたことから、契約書の内容に気を付けているそうだ。
「よく契約書には『貢献度に応じて分ける』などとあいまいな表現がありますが、問題になる前に、ビジネスを見渡せるプロがバランスを取ることが大事です。日本の大企業とスタートアップとの共同研究契約では、スタートアップの研究成果を大企業側が保有することになる 方針が多く、アライアンスが失敗する要因にもなっています。 スタートアップにも寄り添う形にしていただけると、よりよいアライアンスが増えるように思います」
技術力のアピールと社内文化の醸成に知財を活用
鷲巣氏に入社当時の同社の知財体制の印象について聞くと、「第一印象は、このステージのスタートアップとしては、よく考えられた知財管理体制だと感じました。多くの技術者が大企業出身で知財の知識を持っていたこともあり、一人ひとりのリテラシーがとても高く、私から出願プロセスなどについて説明する必要はありませんでした」とのこと。
技術者側から上がってくる特許案件について、ビジネス側の視点で調整するのが鷲巣氏の役割だ。
「例えば、企業との共同開発で共同出願を避けて単独出願するには、最初の段階で進め方をフォローしなければいけません。また、弊社には特許出願していない知見もあるので、どこまで相手に開示するのか、といった整理も必要です」(鷲巣氏)
特許権の存続期間は20年。核融合でのプラズマ加熱に使用される「ジャイロトロン」のように、すでに受注を受けて売り上げを立てている製品も同社にはあるが、それ以外の領域は長期的な戦略を立てる必要がある。特許を出すタイミング、権利化/秘匿するべきかについて技術者と議論を重ねているそうだ。
会社のプロモーションや社内文化の醸成として知財活用にも取り組んでいる。
「会社の技術力をアピールするため、学会で表彰された社員を自社ブログで紹介するなど、技術コンテンツを発信するプロジェクトも進めています。また、社内発明規定を策定し、技術で一定の成果を出すと評価されるカルチャーを醸成しています。ただ、今の職務発明規定は、欧米に比べると補償に差があるので、今後はグローバルに合わせて修正していくべきでしょう」と鷲巣氏。
日本と欧米とは雇用の考え方が違い、対価への意識も異なる。グローバル展開で海外からの研究者人材が増えていく中、チームとしての研究成果について各個人をどのように評価するか検討しているところだという。
最後に、今後の展望を長尾氏に伺った。
「これからはさらなる技術開発と海外展開が重要なテーマです。創業当初は、自社のことしか考える余裕がありませんでしたが、今は日本における核融合の位置付け、核融合産業の中で当社がどのようなポジションを取るべきか――と、広い目線で考えるようになりました。プレッシャーを感じることもありますが、こうして広い範囲で捉えられるのはとても幸せなこと。核融合の実現までにはまだ時間がかかりますが、これまで長く研究開発してきた先輩方、夢を持っている若い世代のためにも、核融合を早期実現したいです」