後編 ~レコードの功罪と音楽にまつわるあいまいな値段~
なぜ音楽は売れない――その本質と「お布施」による打開策
2016年01月05日 09時00分更新
レコード産業が確立した「ジャンル」という名の光と影
もちろん、レコーディング技術の向上によって音楽が獲得した表現の自由度/可能性の拡大を否定するわけではない。さきに述べた「フェードアウト」という技法自体がスタジオにおける録音技術の恩恵であり、歌唱の方法ひとつ取っても、ウィスパーボイスと呼ばれる囁くような唱法はマイクロフォンの技術なくしては誕生しなかった。マイクロフォンの発明以前は、オーケストラおよびバックバンドの演奏に対して人間の声量が負けてしまうため、歌手はメガホンで自らの歌声を拡声していたこともある。
レコードというメディアはより多数の人々に、より広範な地域に音楽を届けることに貢献した。しかしその光に対する影、つまるところ制約を、音楽自体と音楽を制作し演奏する表現者たちにもたらした。
レコードと同時に誕生したジャンルの存在である。
アメリカのコラムニストであるジョン・リーランドは、「ヒップ アメリカにおけるかっこよさの系譜学」という優れたポップカルチャー研究書の中で、ジャンルの発生が音楽に及ぼした負の側面を指摘している。
“レコードはマーケットを欲し、マーケットは固定的なカテゴリーを好んだ。歌い手を見ることができないのだから、ジャンルから理解するしかないのだ。黒人パフォーマーたちはスタジオに入る際、戸口で他の技能をふるい落としてブルース・シンガーとなった。白人パフォーマーもヒルビリー・シンガーとなった。とすると、ブルース・シンガーとはスタジオの発明品、それもしばしばレコード会社の白人重役の発明品であったのだ。ギター製造の技術が音楽の形態を変えたように、レコーディングの技術はパフォーマーのアイデンティティとレパートリーを変えたのである。それまでミュージシャンたちは自力で、あらゆる種類の音楽に自身を刻印していた。歌い手を商品へと転換するレコーディング・プロセスにおいて、初めてブルース・シンガーはブルースだけを歌うようになったのだ。”
| Image from Amazon.co.jp |
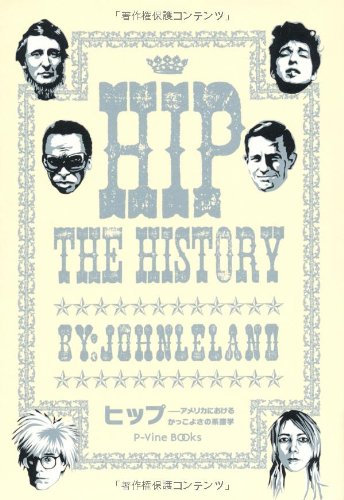 |
|---|
| 元「New York Times」の記者でありコラムニストのジョン・リーランドによる「ヒップ アメリカにおけるかっこよさの系譜学」(P-Vine BOOKs)。音楽をはじめ文学、映画、そしてネットカルチャーなど、あらゆる文化の領域を渉猟しながらアメリカにおける「かっこよさ=HIP」の源流をたどる意欲作 |
ジャンルは消費者がレコードを選びやすくする代わりに、音楽家の多様な表現を封じ込めた。そして、アーティスト側もいつの間にか自分が属する、というかレッテルを貼られたジャンルを進んで受け入れるようになり、リスナー側も「私、こういうジャンルの音楽が好きなんです」などと表明する事態が当たり前になってしまった。これは音楽家が持つ豊穣な可能性の矮小化であり、音楽が背負い込まされたある種の不自由である。
(次ページでは、『「演歌」というジャンルは60年代後半から70年代前半に作られた』)

この連載の記事
-
最終回
トピックス
「これほど身近な時代はない」ネットと法律はどう関わるのか -
第27回
トピックス
著作権法に対するハックでもあるクリエイティブ・コモンズ -
第26回
トピックス
なぜクルマほしいのか、水口哲也が話す欲求を量子化する世界 -
第25回
トピックス
「Rez」生んだ水口哲也語る、VRの真価と人の感性への影響 -
第24回
トピックス
シリコンバレーに個人情報を渡した結果、検索時代が終わった -
第23回
トピックス
「クラウドファンディング成立低くていい」運営語る地方創生 -
第22回
トピックス
VRが盛り上がり始めると現実に疑問を抱かざるをえない -
第21回
トピックス
バカッター探しも過度な自粛もインターネットの未来を閉ざす -
第20回
トピックス
人工知能が多くの職業を奪う中で重要になっていく考え方 -
第19回
トピックス
自慢消費は終わる、テクノロジーがもたらす「物欲なき世界」 -
第18回
トピックス
なぜSNS上で動物の動画が人気なのか - この連載の一覧へ
































































