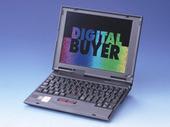日本アイ・ビー・エムの「ThinkPad i Series 1124(2609-93J)」は、IntelがCrusoeに対抗してリリースした超低電圧版Mobile PentiumIII-500MHzを搭載したノートPC。その試作機を入手できたので、レビューをお届けしよう。
バッテリ持続時間にフォーカス
超低電圧版Mobile PentiumIII-500MHz採用
 |
|---|
| 1月31日にIntelから発表された超低電圧版Mobile PentiumIII。1.1Vで駆動し、平均消費電力は0.5W以下。North BridgeとSouth Bridgeを統合したモバイル用チップセット「440MX」とあわせた平均消費電力も0.8W程度だという。 |
この新しいMobile PentiumIIIは、1.5kg以下のノートPCセグメントにフォーカスしてIntelが開発したもので、2000年にTransmetaから登場した低消費電力CPU「Crusoe」に対抗するもの。動作電圧1.1Vという低電圧で駆動するだけでなく、SpeedStepテクノロジに対応しており、バッテリ優先モード(動作クロック300MHz)では、なんと1Vを切る0.975Vでの駆動を実現している。
 |
|---|
| 現状のノートPCの消費電力に関して、CPUの占める割合は10%以下だという。1月31日の発表会場でのプレゼンテーション資料より。 |
さらに、従来比で倍の容量のリチウムイオンバッテリを標準装備することもあり、カタログ上のバッテリ駆動時間の公称値は5時間と、先代73Jの1.8時間から3時間以上ものドラスティックな進歩を遂げた。オプションとしては、さらに大容量(9セル)の「Full Dayバッテリ」も用意(販売開始は4月を予定)され、これを利用すると公称7.5時間のバッテリ駆動時間が得られるという。ちなみに、この超低電圧版Mobile PentiumIIIを同じモバイルPCであるi Series 1620などへ採用する予定はないという。理由としては、液晶パネルのサイズ(1620は12.1インチTFT)がネックとなり、CPUクロック低下に見合うだけのバッテリ持続時間延長が望めないためだという。
低消費電力といえば最近はCrusoeというイメージが定着しているが、日本アイ・ビー・エムでもやはり、そのCrusoeの採用を検討してテストを行っていた。結果的に採用を見送った最大の理由は性能面で、IBMのテストでは、Webブラウザやメール、DVD再生といった用途ではそこそこ良好なパフォーマンスを示したものの、表計算やデータベース、グラフィックス/CADといったアプリケーションでは良い結果が得られず、ThinkPadがターゲットとするユーザーのニーズを満たせないと判断したためだという。