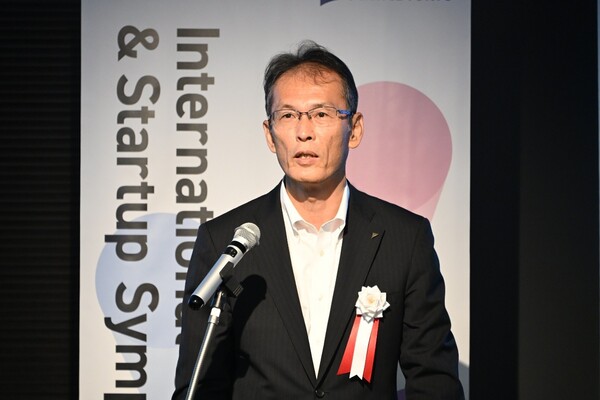東京科学大学が築く産学官共創 稼ぐ研究をともにつくるファーストペンギンへ
「International Open Innovation & Startup Symposium 2025~未来を先取りするイノベーションの最前線へ!~」レポート
2025年7月23日、東京科学大学の設立を記念し、世界規模の課題解決に向けた産学官連携活動と社会発展のためのイベント「International Open Innovation & Startup Symposium 2025~未来を先取りするイノベーションの最前線へ!~」が開催された。
変化の激しい時代における産学官連携のあり方やディープテック分野でのスタートアップエコシステム構築に関する、複数の識者が登壇した基調講演やグローバルエコシステムの事例の講演が展開された。その中で語られた中から、日本がグローバルに打って出るために必要なヒントをピックアップしてお届けする。
ダイキン工業が語る産学連携の現実と企業に求められる覚悟
基調講演にはダイキン工業株式会社 常務執行役員 テクノロジー・イノベーションセンター長である米田裕二氏も登壇。「企業から見たグローバルイノベーションエコシステムの重要性と期待」というテーマで、現在の課題と解決策について語った。
日本の大学には産業界にとって有用な技術テーマが少なく、大学教員も社会実装への関心が低いという課題があるという。この状況を打破するためには、企業側にも大学の研究を後押しする取り組みが必要になる。単に成果を求めるだけでなく、失敗を恐れずに野心的な研究に投資する覚悟が求められるのだ。
「企業は大学にもっとこんなテーマを思い切ってやってほしいと伝えてほしいです。たとえ三振しても構わないから、やるからにはホームランを狙ってほしいと、もっとリスクを取って、多額の資金を投入することが必要です」
大学と企業の間をつなぐ「橋渡し人材」の不足も問題だ。大学の産学連携の窓口が機能しておらず、企業側にも専門人材が少ないため、双方のポテンシャルを引き出すことができていない。この問題を解決するには、ビジネスの視点を持ち、最後までやり抜く精神力を持った人材の育成が急務であると語った。
日本のスタートアップやベンチャーキャピタル(VC)は、市場を国内に限定してしまいがちで、グローバルな視点が欠けているとも指摘。しかし、海外には日本企業が考える以上に大きな市場が広がっており、打って出るべきだという。
「海外の市場はインドやインドネシアのような新興国でも、欧州のような成熟国でも、日本のスタートアップやVCが考えている以上に、豊かな市場があります」
グローバルで成功するためには、技術の開発戦略だけでなく技術の外交戦略も重要になる。金銭的なリターンだけを目的とするのではなく、ビジョンや社風に共感しあえる信頼関係を築くべきだと提案している。そうした関係性から生まれるシナジーこそが、世界で戦うための日本の独自のエコシステムになり得るという。
そのためには、まずはダイキンと東京科学大学が先駆者となり、良い前例を作ることが重要だと語った。日本人は前例があれば追随するという国民性のため、ファーストペンギンが出ることの意義は大きい。最終的に目指すのは、大学と企業が研究開発の収益化に共に取り組むこと、そして、真のビジネスパートナーへと関係性を深めることだ。
「研究開発のマネタイズを企業任せにせず、産学が一緒に進めることで、技術パートナーから真のビジネスパートナーへ発展しうるのです。東京科学大学はそのポテンシャルを持った大学で、今後は日本のエコシステムをリードする大学として、大いに期待しています」と米田氏は語った。
政府主導で「稼ぐ研究」を徹底、スマート国家シンガポールの仕組み
ICMG Groupグローバル共創事業執行役の羽田大樹氏は「スマート国家シンガポールが描くイノベーションエコシステム」というテーマで講演。シンガポール政府の強力なリーダーシップのもと、大学やスタートアップ、大企業が連携して社会課題解決のための技術を迅速に社会実装し、グローバル展開の拠点となる先進的なイノベーションエコシステムについて解説した。
日本の大学や研究機関が持つ「サイエンス」の面白さは、シンガポールの大学教授やVCからも高く評価されていると指摘。しかし、「エンジニアリング」のところでギャップが発生していて、そのため実用化に至っていない、と言われることが多いという。
シンガポールでは、政府が強力なリーダーシップを発揮し、国全体でイノベーション創出に取り組んでいる。「RIE(Research, Innovation and Enterprise)」という国家戦略のもと、5年ごとに約3兆円の予算を投下し、食料自給率30%達成など、明確な目標を掲げている。
特徴的なのは、政府系研究機関ASTAR(科学技術研究庁)のKPI(重要業績評価指標)だ。論文数や特許数だけでなく、「企業との共同研究数」や「スピンオフ(事業化)数」が目標として設定されており、研究者が積極的にビジネス化を目指す仕組みが構築されているのだ。すでにASTARから90以上のスタートアップが生まれており、エコシステムの活性化に大きく貢献している。
シンガポールの大学は研究の事業化を専門的に支援する組織と機能を構築している。たとえば、シンガポール国立大学(NUS)では、専門組織「NUS Enterprise」が、知的財産の管理、起業家育成、インキュベーション(事業支援)、海外市場へのアクセスまでを一気通貫で担う。日本の高輪ゲートウェイにも拠点「Block71」を設置し、シンガポールのスタートアップが日本へ進出する際の水先案内人としての役割も果たしているのだ。
南洋工科大学(NTU)では、子会社である「NTUitive」がスタートアップ支援を手がけている。技術的な実現可能性を検証するPoC(Proof of Concept)に留まらず、その技術に市場が価値を感じ、お金を払うかを検証するPoV(Proof of Value)を徹底しているのが特徴だ。
「PoVでは、その技術に市場の顧客は本当に『お金を払うのか?』という検証をします。結構ここが弱いことがあるのです。スタートアップの失敗では市場がありませんでした、というのが1番の理由です。NTUではそこを徹底的に潰すようにしているのです」
また、NUSとNTUは共同で、熱帯地域におけるデータセンターの冷却技術を開発する国家プロジェクトを進めている。実際に学内のITシステムで稼働するデータセンターを「生きた実験室」として活用し、液体冷却などの最先端技術を企業と連携しながら実証している。これは、大学の研究成果を社会実装につなげる産学官連携の成功例のひとつと言える。
多様な人々を巻き込み「魔法」を起こす、UCデイビス校の仕掛け
カリフォルニア大学デイビス校 グランドチャレンジ室 シニアアドバイザーのMr. Benjamin Finkelorは「UCデイビス校:産学官連携を活用し、世界の壮大な課題に対するソリューションを革新する」というテーマで講演した。
UCデイビス校では、大学での研究を社会実装する上で、従来の産学連携の枠を超えた、より広範なステークホルダーとの協働を実践しているという。フィンケラー氏が共同リーダーを務める「エネルギー効率研究所」の事例では、研究室での技術開発に留まらず、その技術が実際に市場で受け入れられ、社会に価値をもたらすまでのプロセス全体を見据えている。
「商業化のプロセスには多くの異なる団体や人々が関わるため、エンゲージすべきステークホルダーはさらに多くいます。例えば、施工業者や設置業者、建築検査官など、さまざまな視点を持つ人々と協力することで、研究室で技術を進歩させるだけでなく、その技術が現場で採用され、顧客に価値を見出してもらえるようにすることができるのです。産業界と学術界が協力することが非常に重要なのです」
イノベーションを加速させるためには、人々が物理的に集い、偶発的な出会いや交流が生まれる「場」が重要となる。UCデイビス校では、2025年に大学の研究者や大企業、スタートアップ、そして学生や地域コミュニティの人々が一堂に会する最先端のイノベーション地区として設計した「アギースクエア(Aggie Square)」を新設。知的財産保護という課題に配慮しつつも、あえて異なる組織の人々がフロアや設備を共有する環境を創り出すことで、予想を超えた化学反応を狙っているのだ。
「人々が直接会うことは、イノベーションのプロセスにとって非常に重要です。同じフロアで、同じエレベーターを使い、設備を共有する環境で、どのように知的財産を保護するかを考えるのは難しい課題です。しかし、それこそがイノベーションの魔法であり、私たちはイノベーションを推進するためにそのリスクを引き受け、管理しようとしています」
優れた研究をビジネスにつなげるためには、研究者自身が商業化への意識を持つことが不可欠だという。UCデイビス校では、15年以上にわたり「起業家育成アカデミー」を運営し、研究者にイノベーションのプロセスを学ぶ機会を提供してきた。必ずしも全員を起業させることが目的ではなく、むしろ、自身の研究を社会実装へと近づけるために、どのように研究を方向づけ、調整すればよいかという思考様式を身につけさせることが目的だ。
「研究者をイノベーションのプロセスで訓練します。彼らは、実際には会社を立ち上げたくないということを気付くかもしれませんが、それはそれで構いません。会社を立ち上げるかもしれませんし、自分の研究をより商業化しやすくするためにどう調整すればよいかを学ぶかもしれません。そして、これこそが私たちが学術研究者に身につけてもらおうとしている考え方なのです」(フィンケラー氏)
様々な講演を聞く中で、日本の産官学が「連携」という言葉に隠れて、研究とビジネスの間にある断絶を放置してきたという状況が見えてきた。企業は大学に成果を求めつつもリスクある投資を躊躇し、大学は社会実装を企業任せにしてきた。この責任の所在が曖昧な構造が、日本がイノベーションの国際競争から遅れつつある原因なのかもしれない。
シンガポールやUCデイビスの成功は、大学自身が事業主体となり、研究の価値をビジネスの価値へと転換するプロセスにまでコミットする覚悟に基づいている。今後、求められるのは、単なる連携強化ではなく、「産官学共創」という意識を持つことだろう。新設された東京科学大学には、このファーストペンギンとしての役割が期待される。