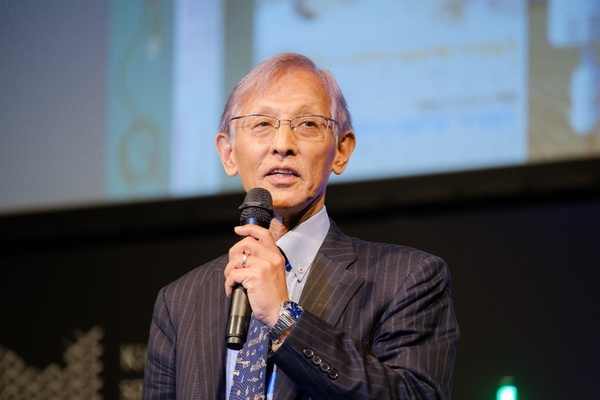共創と宇宙 北九州市がスタートアップと描く未来
北九州市発の大規模スタートアップイベント「WORK AND ROLE 2024」レポート
MIT-K(メイカーズオープンイノベーショントライアル)
続いてのプログラムでは、MIT-K(メイカーズオープンイノベーショントライアル)の経過発表が行なわれた。同プログラムは、北九州市の特徴である「ものづくり」と、スタートアップとのオープンイノベーションを実現するもの。スタートアップ支援だけでなく、プレイヤー企業への支援でもあるという。スタートアップ、起業準備者が共創企業のサポートのものとでプロダクト開発を進める。今回は4者が登壇し、発表した。
大分県立情報科学高等学校 小松 杏氏(共創企業:株式会社ドーワテクノス)
最初に登壇したのは、大分県立情報科学高等学校とその共創企業の株式会社ドーワテクノスだ。
大分県立情報科学高等学校の小松杏氏は、街中のゴミ箱に関しての課題を提示し、新しいソリューションを提案する。街中にはゴミ箱が少なく、あってもゴミがあふれてしまっているという現状を指摘。設置されない理由を回避するため屋内設置を選択し、トライアンドエラーの後、回収された資源をアートにする試みを発表した。
小松氏の発表を受けて株式会社ドーワテクノスの前田氏は、「プロジェクトが進んでいったのは小松さんの高い熱量だった」と評価。ゴミが資源となり、アートとなっていく可能性に期待が寄せられた。
九州工業大学 情報工学部 白土拓実氏(共創企業:株式会社REIZ)
続いての登壇は、九州工業大学 情報工学部 白土拓実氏と、共創企業の株式会社REIZ。
AIをより身近に感じられるとする、車の運転中の居眠り防止ソリューション「talk-be talked AI」が紹介された。
長時間労働で居眠りしやすい労働環境であるトラックドライバーに対して、興味のある話題をふるなど会話が続くコミュニケーションAIによって居眠りを防止するというもの。
共創企業の株式会社REIZは車用品のEC事業を展開する。大学生がトラックドライバーの過酷さを理解するのは大変だっただろうと振り返る。AIの使い方を知っている人は少ないので、理解のきっかけ、サポートとなるソリューションであることが共創の理由だという。
株式会社OUTSENSE 高橋鷹山氏(共創企業:株式会社タカギ)
3組目は、折り工学を用いて課題解決する株式会社OUTSENSEの高橋鷹山氏と、共創企業の株式会社タカギ。
折り紙で使われる「折り」で衝撃吸収、コンパクトな収納、平面から立体整形などを実現できるシーズ技術だが、共創企業とのワークショップで課題を洗い出し、シーズとニーズを掛け合わせるオープンイノベーションを目指したいと取り組みを紹介した。
株式会社タカギの佐々木氏は、新規事業開発部門と開発部門の成長機会となることを想定しており、目的は達成できたとし、オープンイノベーションを体験できたと取り組みを評価した。
株式会社J-mind 上野淳氏(共創企業:北九州産業学術推進機構/FAIS)
最後の発表は、災害時用コンテナハウス向け自律型電源システムを手がける株式会社J-mind 上野淳氏と、共創企業の北九州産業学術推進機構/FAISが登壇した。
世界各国で災害時の仮設住宅として用いられているコンテナハウス向けに、太陽光パネルや制御基盤などを提供したいとし、現在は災害時のデータ収集と検証の段階だという。
コンテナハウスは世界で8兆円規模の市場だというが、日本では8000台くらいにとどまっており、ブルーオーシャンであると市場を見込む。災害時用とはいえ、アウトドアなど災害時以外の活用、事業性も見込んでいる段階とのことだ。
北九州産業学術推進機構/FAISの原田氏は、今後の災害対応にニーズがあるとし、企業文化としてチャレンジ精神を持った企業であるということを評価。早期に実現することで、優位性を作ってほしいとエールを送った。
パネルセッション2/共創セクション「オープンイノベーションのリアル」
パネルセッション2/共創セクションでは、「オープンイノベーションのリアル」と題し、登壇企業のオープンイノベーションの現状と課題、今後について意見が交わされた。
明確な成功事例や失敗事例というものが紹介しづらい中で、日本と海外でスタートアップ企業が持っているもの、足りないもの、そのギャップをどのように埋めていけばいいのか、という点から議論はスタート。その中でキャピタルゲイン、共創による価値創造や、共創によって何が得られるのかを明確にすることが成功への道筋のひとつだとされた。
一方で、スタートアップの生存戦略の観点から、事業選択を急にされると困惑するとの意見が提示される場面も。企業においては、どのようなスタートアップなら投資対象になるか、という答えは持ち合わせていないという。とはいえ、ひとつの企業が自前でやっていくには限界があり、さまざまな方法で協業、共創は進んでいくだろうと将来像が示された。