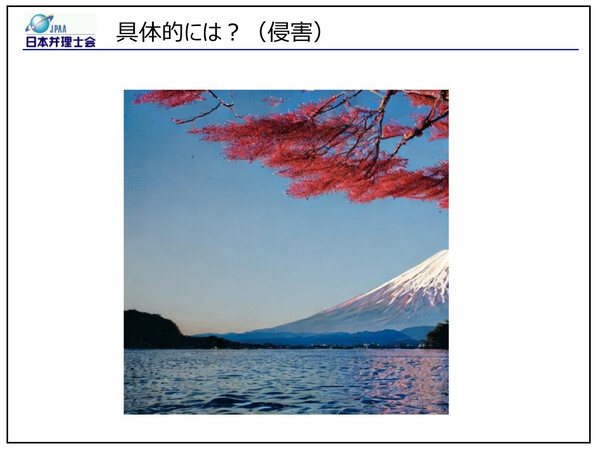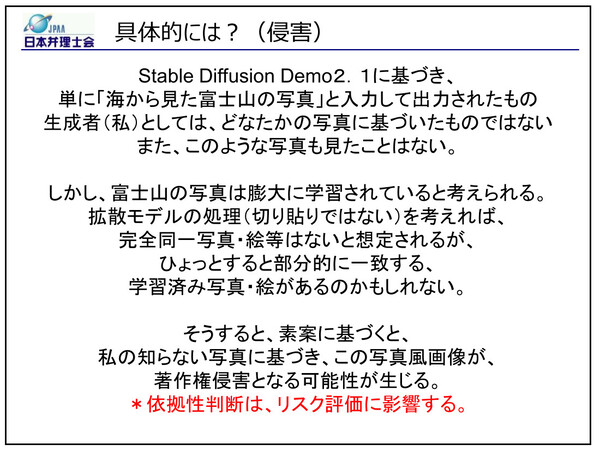生成AIの学習内容次第で、意図せず著作権を侵害してしまう?
生成AIが他者の著作物を学習した結果、それと類似した創作物が偶然に生成されてしまい、著作権侵害が問われる可能性がある。こうしたケースについては、今回の素案でも原則、これまでと同様の判断がなされているが、高橋氏は「一部では異なる判断になる可能性もある」と説明する。
「『生成者が知らなかったのに、結果的に類似物が生成された』場合に、これまでとは異なる判断になる可能性がある。素案では『対象の生成物を学習していれば、依拠を推定できる』と考えている」「この部分をどう判断するかによって、生成AI利用のリスクに影響が及ぶことになる」
弁理士会 著作権委員会では、大規模言語モデル(LLM)などの技術内容から考えて、生成AIによる生成物は単なる“切り貼り”ではないため、一律に「学習されていれば依拠あり」と認めるのはやりすぎであり、「“偶然の一致”と評価してもよいのではないか」という趣旨を盛り込んだ報告書を作成しているという。
より具体的に説明するために、高橋氏は、画像生成AIツールのStable Diffusionに「海から見た富士山の写真」とプロンプトを入力して生成した画像を示した。
「生成者であるわたし自身は、これは誰かの写真(著作物)に基づくものではないと思っているし、そもそもこのような写真を見たこともない。また、Stable Diffusionは膨大な数の富士山の写真、海の写真を学習しているが、完全にこれと同一の写真ではないはずだ。しかし、ひょっとすると部分的に、学習済み写真と一致しているのかもしれないと考えることもできる。文化庁の素案を基にすると、わたし自身が知らない写真に対して、わたしが著作権侵害をしてしまうことになる可能性がある」
なお文化庁の素案は、生成AIの提供者(開発者)に責任が生じる可能性にも言及している。
AI翻訳、AIコーディングなどでは個別の検討すべき事情がある
生成AIは文章やイラストの生成だけでなく、多言語の翻訳もこなす。高橋氏は、人間が翻訳した翻訳物については二次著作物となる一方、「AIによる翻訳物は原則、二次著作権が発生しないと考えられる。ただし、精緻な翻訳物には原著作権が及ぶ可能性がある」とする。
マンガなど、日本のコンテンツ産業が海外進出する際には“言語の壁”の問題が指摘されてきたが、生成AIを利用することで「原著作権を維持しながら、二次的著作物としての権利処理の難しさをクリアし、効率的に海外展開を狙えるようになる」と、ビジネス活用の可能性を紹介した。
他方、コンピュータープログラムのコーディングでは生成AIの活用が急拡大しており、現在では簡単なプログラムであればプロンプトによる指示だけで作れてしまう。ただし高橋氏は、著作権の観点からは「より検討が必要な領域」だと指摘した。
「著作権では、プログラム(コード)の機能を守るのではなく『表現』を守ることになっている(プログラムで構成されたシステムそのものは特許で保護される)。通常、プログラムは機能として効率的になるよう書くものであり、“個性的な表現”を目指して書くという意識は少ない。生成AIの技術が進歩していくと『プログラムの著作物性』に関する問題が発生しやすくなると考えられる」