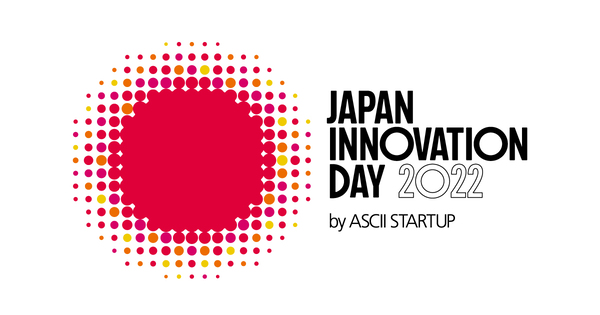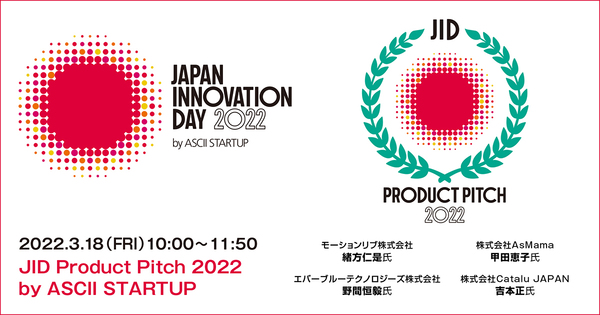新領域への知的好奇心がスタートアップ支援のきっかけ テキスト力の高い専門家がスタートアップ支援に向いている理由
「第2回 IP BASE AWARD」知財専門家部門グランプリ】STORIA法律事務所 弁護士・弁理士 柿沼 太一氏インタビュー
この記事は、特許庁の知財とスタートアップに関するコミュニティサイト「IP BASE」(外部リンクhttps://ipbase.go.jp/)に掲載されている記事の転載です。

STORIA法律事務所 弁護士・弁理士 柿沼 太一(かきぬま・たいち)氏
1997年京都大学法学部卒業。2000年弁護士登録。2021年神戸大学大学院博士号(法学)取得・弁理士登録。2015年にスタートアップのサポートを重点的に取り扱うSTORIA法律事務所を杉浦健二弁護士と共同設立。専門分野はスタートアップ法務およびデータ・AI法務。2018年には経済産業省の「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」、「ものづくりスタートアップのための契約書ガイドライン」検討会メンバーとしてガイドライン策定に参加。また2020年6月に公開された「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0」の策定にも携わる。
「第2回 IP BASE AWARD」知財専門家部門グランプリを受賞したSTORIA法律事務所の柿沼 太一弁護士は、2015年にSTORIA法律事務所を共同設立以来、多くのスタートアップの法律面・知財面をサポートしてきた。その中で見えた大企業との連携における契約交渉の課題感から、経済産業省の「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」や「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0」の策定に参加、オープンイノベーションを促進するための法的整備に取り組んでいる。これまでのスタートアップ支援の取り組み、スタートアップエコシステムにおける弁護士に求められる働き方について、話を伺った。
民事訴訟の経験がスタートアップ支援にも活きている
今でこそ企業法務分野で活躍している柿沼氏だが、弁護士になって十数年は一般民事を担当し、教育現場で起きた教職員や生徒の事故に関わる複雑な訴訟を担当していた。たとえば教職員の公務災害の有無が争われた事件では、働き方が争点となったが、学校現場にはタイムカードもないため、膨大な資料を集めて、成果物から当該教職員の勤務内容を逆算していかなくてはならなかった。また、熱中症によって生徒に重大な障害が残った学校事故に関する訴訟(一審で敗訴、高裁で逆転勝訴、最高裁で勝訴確定)では、責任を否定した学校側に対し、その過失を証明するための資料・情報収集に奔走しなくてはならなかった。地味で膨大な時間のかかる作業だが、こうした難しい訴訟に勝訴した経験が、今のスタートアップ支援にも役に立っているという。
スタートアップと接点をもったのは2013年。ある教育系コンテンツを提供する企業から契約書チェックの依頼を受けたことがきっかけだった。弁護士になって10年以上、目の前にある案件に全力で取り組みつつ、その一方で掘り下げるべき分野を探し続けてきた柿沼氏が見つけたのがスタートアップの支援だった。
「それまでスタートアップやベンチャーと関わったことがなかったのですが、たまたま、そのCEOが同じ京大出身でした。いろいろ話をしましたが、スタートアップのCEOや起業家は純粋な人が多く、頭の回転も話も早い。また、世界を変えよう、という熱い思いと行動力を持っている。こういう人達に初めて直に接し、弁護士としてスタートアップをサポートする側になろう、と考えるようになりました」(柿沼氏)
2015年に神戸でSTORIA法律事務所を杉浦健二弁護士と共同設立。せっかく新しく立ち上げるのだから、まだ誰もやってないことをやろう、という創業者間の意見が一致し、特に関西では当時は珍しかったスタートアップ支援を主業務に掲げた。
その際には、当時のスタートアップ業界や、スタートアップを支援している士業のことを徹底的に分析して、法律事務所としてどのようにスタートアップをサポートしていくかについて、50ページ近くのレポートを作った。
ちょうど神戸市がスタートアップ支援に力を入れ始めていた時期であり、神戸市と米国のシード投資ファンド500 Startupsと連携したアクセラレーションプログラム「500 KOBE ACCELERATOR」の導入を神戸市側でサポート。これを起点に紹介がつながり、数々のスタートアップとの取り組みを手掛けるようになった。事務所は神戸市だが、現在のクライアントの8割は東京の企業。やりとりはSlackやZoomで行なっているため、地理的な制約はほぼないそうだ。
法律事務所がスタートアップの支援にあまり前向きでない理由として、「手間がかかる」「その割にお金を取れず、かつリスクが高い」の2点に集約されると柿沼氏は当初考えていた。だが、報酬に関しては、スタートアップだからといって必ずしも法務予算が厳しいわけではなく、一般的な業務として十分に成り立っているそうだ。
「今は(スタートアップの資金)調達環境が良くなっているのもひとつの理由ですが、そもそも専門性のある弁護士に依頼することを考えるスタートアップは、それなりにビジネスの実力があるので、売上が立つようになるのにあまり時間がかかりません。うちの顧問契約の料金体系としては、起業後一定期間のスタートアップのみを対象とする特別の料金プランを設定していますが、ほとんどのスタートアップは、当該期間が終了すれば通常の顧問契約に移行します」と柿沼氏。
ただし、弁護士の仕事はどんな領域でも正確性が求められる。スタートアップ向けの業務だからといってそこがおろそかでよいはずがない。むしろ、スタートアップごとに、新しい技術や業界、ビジネスモデルを正しく理解するための勉強が必須であり、未知の領域では、まだ見えていないリスクも当然ありうる。半面、企業の定型業務とは違った知的好奇心を刺激される面白さ、やりがいがあるのがスタートアップ支援の醍醐味だという。
新しい技術領域での法務課題を調査し、ブログで情報発信
現在柿沼氏はAI・データ法務を専門としているが、AIに興味をもつようになったのは、著作権専門情報誌「月刊コピライト」で2016年10月に掲載された、慶應義塾大学の奥邨弘司教授のAIと知財に関する論考「THE NEXT GENERATION : 著作権の世界の特異点は近いか?」を読んだのがきっかけだ。
AIをはじめとする技術革新がもたらす変化が著作権を含む知的財産法制にとっても大きなインパクトとなる、という内容であり、衝撃を受けた柿沼氏はいても立ってもいられず、この分野への注力を決めたという。
そこで、まずは現場の課題を知るため、2017年に名古屋で開催された「人工知能学会全国大会」でAI企業の各ブースを尋ね、法的な課題を聞いて回ったところ、多くの企業でAIに関する法律・知財面での課題があることを知った。その一方で、奥邨教授をはじめとする知的財産を専門とする学者を訪ね、AIに関する知財の課題についてディスカッションを交わした。
弁護士が新しい領域に挑戦する場合、まず「どのような法律問題があるか」を書籍などで調査をするのが通常だが、AI領域においては、そもそも「どのような法律問題があるか」すらわからない状態だったため、AI企業にビジネスの最前線での課題を直接聞いてみた形だ。こうしたやりとりを続けていくうちに企業とのつながりも深まっていったという。
ただし、すぐにAI企業との仕事が始まったわけではない。平行して柿沼氏は、最前線でのAIビジネスにおける法的な論点について、記事の形で事務所ブログに公開しはじめた。当時も今もAIやビッグデータは技術に法律が追いついていない、いわば何が正解かわからない領域であり、知り合いの弁護士からはブログ執筆について「勇気があるね」と言われたそうだが、柿沼氏としては学んだことをまとめてみたいという知的好奇心からブログでの情報発信を行なったという。
だがそのような情報発信を続けていくうちに、問い合わせが増えてきた。さらには、ブログを読んだ経済産業省の担当者から声がかかり、「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」の検討会メンバーとして参加することにもつながっている。
AI・データ系企業の契約交渉、情報規制、知財戦略をサポート
柿沼氏の現在の業務は、AI・データ関連企業の法務知財サポートが半分以上を占める。ニーズが高いのは、1)契約締結交渉のサポート、2)各種法規制のクリア、3)技術開発・サービス開発における個人情報やデータの知財の取り扱い、以上3つの領域だ。
契約締結交渉については、経済産業省や特許庁の作成した契約ガイドラインやモデル契約書が公開されており、本気で読み解くスタートアップ側の理解度は高いが、契約相手となる大手企業側が理解しているとは限らない。
STORIA法律事務所では、交渉スタンスをクライアントと共有しつつ、交渉相手向けの想定コメントを作成し、交渉のスタートラインから細かくサポートしている。一見すると手間がかかりそうだが、スタートアップのほとんどは法務部がないため、経営陣やCEOと直接話を進められるため話が早く、一般的な企業に比べるとスピード感を持って契約交渉が進められるそうだ。
法規制の面では、AIはあらゆる事業分野に関連する技術なので、金融や医療といった規制産業で活用するには、それらの法規制をクリアしなくてはならない。特に医療・ヘルスケア系は規制が厳しいため、AI医療機器などは研究開発の段階から法務のサポートが求められ、臨床データの扱いなどを倫理指針や臨床研究法などに沿ってひとつひとつ確認していくことになる。AIは新しい領域のため、規制があいまいな部分もあるため、現状に即した法規制の整備などに向けて、専門家の活躍する余地があるという。
スタートアップはサービスの成長を優先して知財戦略の優先度が低くなりがちだが、データを扱うAI企業の場合、知財戦略は将来の事業展開に大きく影響するため、データや学習済みモデルにからむ知財の取り扱いは最重要課題となる。特にAIスタートアップは、ビジネスモデルを受託開発から自社サービスへと展開するのが一般的で、受託開発や共同研究で蓄積されたノウハウや知財が、都度完全に相手方に渡ってしまうと、将来のビジネス事業展開への負の影響も大きい。
AIソフトウェアに関する受託開発の場合、相手側の企業は従来のITシステム開発契約のひな型を用いて、すべての知財を委託元に帰属させるよう求めてくることが多い。そのため、受託開発契約の際には、コアの技術を渡さないように、譲れる部分と守るべき部分を意識しておくことが大事だと柿沼氏は強調する。実際の交渉では、スタートアップ側の技術力の高低が交渉力の大きな要素となる。スタートアップが力を付けることで相手企業側の意識も変わってくるだろう。
スタートアップを専門家が支援する際に求められること
柿沼氏は、スタートアップを弁護士が支援する際の対象は、大きく分けると2層のレイヤーがあると語る。
まずベースとなるレイヤーは、スタートアップであればジャンル問わず問題となるような問題、たとえば会社法上の会社の運営や株式に関する問題、資金調達の問題などだ。その上のレイヤーが、当該スタートアップが取り組んでいる事業領域や技術ごとに問題となる課題、法律分野(個人情報保護法、知的財産法)となる。ここは個々のスタートアップ特有のレイヤーである。
詳細に見ると、2つ目のレイヤーは「事業領域×法律」や「技術×法律」という組み合わせで問題となることが多いという。たとえば「著作権」という法律が問題となる事業領域や技術としては、①IT業界における第三者の著作物の利用行為や、システム開発契約における成果物の権利帰属の問題、②データ・AI系契約書におけるデータや成果物の権利帰属の問題、③エンタメ・コンテンツ業界におけるコンテンツ制作に関する多数当事者の契約調整などがある。これら多種多様なビジネスや技術領域に対応するためには、著作権の知識単体では役に立たず、実際にそれらの領域でどのようなことが問題となるのか、その問題における著作権法の位置づけ、実務的な複数の打ち手を知っている必要がある。
例えばAIに関する法的課題(生成に際しての権利処理・成果物の権利帰属)を理解するにはAIの技術的基礎を理解していなければならないし、そもそもそのような基礎を理解していないとクライアントと話もできない。
最後に、法律・知財の専門家としてスタートアップ支援をする際に必要なスキルや心構えについてアドバイスをもらった。
「スタートアップは組織内部において情報共有のためにSlackやチャットツールなどの非同期型のコミュニケーションを多用します。そのため、支援する側の僕らもその文化に合わせるようにしています。もちろん、直接確認した方がいい問題については会議を設定しますが、テキストで届いた質問には、できるだけわかりやすくテキストで回答を戻すようにしています。テキストのみで回答できることは意外と多いですし、その方がスタートアップ側も理解・整理しやすく、かつスタートアップ側のナレッジの蓄積にもつながるためです。
また、弁護士や弁理士は、法律問題を分析し、論理的に筋道を立てて解を出すというトレーニングを嫌というほど積んでいます。したがって、ロジカルな人が多いスタートアップの経営陣とも非常に相性がいい。ちなみに、最近スタートアップの中で働く弁護士が増えているのもすごくいい傾向だと思います。自分も20年若かったら、と思います。今後、中からでも外からでもスタートアップ支援をする弁護士がもっともっと増えて活躍していってほしい。それがスタートアップの成長を支え、ひいては世界や社会が良い方向に向かう1つの大きな力になっていくと思っています」