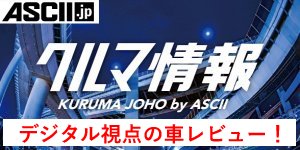まつもとあつしの「メディア維新を行く」 第60回
中国・配信・CG――アニメビジネスの最新事情を数土直志氏に訊く
他国のカネでアニメを作るとき、何が起きるのか?
2017年08月21日 17時00分更新
中国・外資参入が生む可能性と難しさ
アニメを巡る状況がほんの数年で激しく動いている。厳しいと指摘される労働環境や業界全体の収益性とは裏腹に、作品・キャラクターへの人気は世界へと広がり、資金調達・制作・流通を巡る環境も大きく変わった。この潮目に、星海社新書より『誰がこれからのアニメをつくるのか?』を著した数土直志氏に再び話を聞いた。
―― 数土さんにこの連載でお話を伺うのは2度目となります。その際のタイトル(後編)は、「日本アニメは世界各国で負け始めている」という刺激的なものでした。あれから6年が経ちましたが、いま日本のアニメが置かれている状況をどうみていますか?
数土 ずいぶん年月が経ちましたね。また、この本で中国について書いていたのも2016年の10月から12月頃で、そこからわずか半年ですがそこからも随分状況は動いています。あの頃は中国の勢いについて書きましたが、今は少し疑問符もつくような状況ではあります。ただ、引き続き中国が重要であることには変わりありません。彼らとどうつきあっていくか真剣に考えるべきですね。
どんなに中国の文化・経済政策が変化しようとも、そこには世界最大の日本のアニメファンがいます。市場としてはまだ日本のほうが大きいかもしれませんが、ファンの数だけみればそれは間違いありません。
| Image from Amazon.co.jp |
 |
|---|
| 誰がこれからのアニメをつくるのか? 中国資本とネット配信が起こす静かな革命 (星海社新書) |
―― 人口はざっくり10倍と言われたりもしますが。
数土 そこまでは行かないと思います。人気は上海・北京などの都市部に偏っています。逆に言うと地方はまだまだです。例えば「君の名は。」の中国での劇場収入を見ると95億円。日本は250億円です。これはチケットの額が日本の半分以下ですから、1000万人以上は見ていると推定できます。「NARUTO」の動画の再生回数も億単位になっています。ファンが多い、というのはそういった数字からですね。
―― 市場としての可能性はどうでしょうか?
数土 日本企業がもっと大きな利益を取る、というのはいまの状況ではなかなか難しいと思います。ファンは増え、市場は大きくなり、中国企業は潤っていくでしょう。しかし、そこに日本が乗っかれるか?
書籍・ビデオパッケージ・放送・ネット・上映、すべて外資はNGなんです。放送に至ってはJV(ジョイント・ベンチャー)でさえ不可だったりする。すべて、中国企業にコントロールされ、利益もそこに落ちる。大きな市場があるにも関わらず、日本企業がそれをメリットに変える方法がなかなか見いだせない。配信権や映像化権に多少の「抜け道」は発見できたものの、まだまだ……。
―― ファン人口と市場が直結していない。政府(中国共産党)による規制もある。そんななか、著作でも取り上げられていたのが、日本に絵梦株式会社を設立した中国企業HAOLINERSなど、資金調達先としての存在感でしたね。
数土 そうですね。今の中国のアニメを巡る状況がアメリカや日本のようなかたちに劇的に変わるとは思えません。そうなると、JVを組むしかない。その一環として、作品の制作に必要な資金を調達するという動きも出てきています。逆に言えばそれくらいしか、中国の資金力を利用して日本企業が儲ける「抜け道」はないんです。
今期の夏アニメ「セントールの悩み」は、中国企業資本のアニメスタジオ絵梦が制作。
―― 中国から見れば、日本で制作されたアニメが逆輸入される形になるわけですね。
数土 そうですね。日本のスタッフが制作することで、そこで収益を得ることができます。実際2016年もそういった作品がいくつも生まれました。しかし、必ずしもクオリティーは高いとは言えません。資金はそれなりに得ているはずなので、そこは日本側にも責任があるのかなと思います。
―― それは……中国で放送・配信するためにはストーリー展開上の制約があるということでしょうか? それとも、中国向けだからということで、クリエイターのモチベーションが上がっていない?
数土 モチベーションの問題はあるでしょうね。日中合作では、条件の1つとして挙げられることが多いのが「日本で放送すること」。それは中国側にしてみれば「日本のアニメ」というブランドを“纏う(まとう)”ため、ということはもちろんあるのですが、一方日本の現場からは、「日本でも見てもらいたい」と。
あとはスピード感の問題があるでしょうね。企画から制作までの期間が非常に短い作品が多いようです。中国は総じてスピードが速い国です。「今企画を決めたら、来年には放送しよう」くらいの勢いだったりします。
―― 通常2~3年は掛けるところ、それは拙速ですね(笑) 日本アニメに資金を提供する会社がIT系が多かったりすることも関係しているのでしょうか。
数土 ITのスピード感というのはあるでしょうね。純粋な作業だけでなく、企画を練るといった時間も含まれているところを半分にしよう、と言われた時点でクオリティーは下がりますよね。

この連載の記事
-
第102回
ビジネス
70歳以上の伝説級アニメーターが集結! かつての『ドラえもん』チーム中心に木上益治さんの遺作をアニメ化 -
第101回
ビジネス
アニメーター木上益治さんの遺作絵本が35年の時を経てアニメになるまで -
第100回
ビジネス
『THE FIRST SLAM DUNK』で契約トラブルは一切なし! アニメスタジオはリーガルテック導入で契約を武器にする -
第99回
ビジネス
『THE FIRST SLAM DUNK』を手掛けたダンデライオン代表が語る「契約データベース」をアニメスタジオで導入した理由 -
第98回
ビジネス
生成AIはいずれ創造性を獲得する。そのときクリエイターに価値はある? -
第97回
ビジネス
生成AIへの違和感と私たちはどう向き合うべき? AI倫理の基本書の訳者はこう考える -
第96回
ビジネス
AIとWeb3が日本の音楽業界を次世代に進化させる -
第95回
ビジネス
なぜ日本の音楽業界は(海外のように)ストリーミングでV字回復しないのか? -
第94回
ビジネス
縦読みマンガにはノベルゲーム的な楽しさがある――ジャンプTOON 浅田統括編集長に聞いた -
第93回
ビジネス
縦読みマンガにジャンプが見いだした勝機――ジャンプTOON 浅田統括編集長が語る -
第92回
ビジネス
深刻なアニメの原画マン不足「100人に声をかけて1人確保がやっと」 - この連載の一覧へ