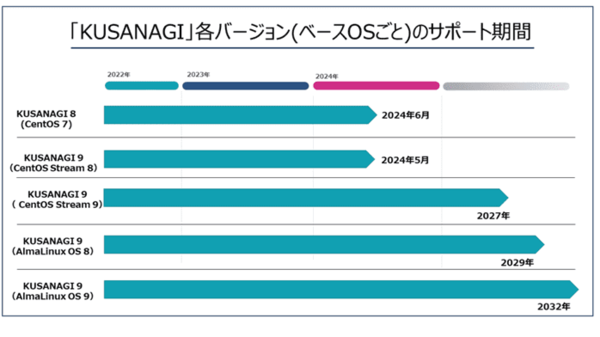資源が増える時代、富の再配分の公平さはそれほど問題にはならない。しかし現在、すでに資源生産が増えない時代に入っているとすれば、再配分する仕組みを調整しなければ、やがて共同体は崩壊し、暴力的な形で調整されてしまう。モザンビークでこの問題に挑んでいるのが日本植物燃料の合田真社長だ。
「世の中を根底から変える先進的なテクノロジーはあります。ただし、ローテクでも、捉え方や使い方によっては、世界を変えられる。アフリカは、最先端とはいないテクノロジーでも、新しい世界を作れる事例にあふれています。今日はその話を皆さんに紹介します」
4月10日、MITテクノロジーレビュー主催のイベント「MITTR Emerging Technology Conference #3」に登壇した日本植物燃料の合田真社長は「エネルギーと金融経済」をテーマに、モザンビーク(アフリカ)の無電化村で、地産地消型の再生可能エネルギー事業や食料生産、金融サービスなど、持続可能なビジネスを開発する方法について語った。
「たとえばケニアでは、2007年からM-PESA(エムペサ)という携帯電話を使った送金サービスが急激に広がりました。SMSで、ある人からある人に数字を送ると送金できるのですが、これ自体は、テクノロジーとして見れば、非常にローテクです。でも、金融に関する法律・制度が変わることで、爆発的に広がったのです」
社会科学では、社会の仕組みを「構造」や「システム」、思想、文化などの概念を「エートス」と理解する。講演で合田社長は、エネルギーや資源、テクノロジーを「現実」と呼び、法律や貨幣などのシステムを「ものがたり」と定義し、現実を変えるため、ものがたりをどう変えるか、について語った。
資源生産の拡大期と制約期
2010年、国際エネルギー機関(IEA)はWorld Energy Outlookで「世界の原油生産量は2006年にピークを迎えていた可能性が高い」と報告した。合田社長は、このレポートに「大きな衝撃を受けた」という。
「少なくとも第二次大戦以降、世界のエネルギー消費の総量は、右肩上がりで増え続けています。しかし、原油生産はどうやらピークを迎えた。原油がすぐに枯渇する話ではありませんが、原油生産が伸びなければ、経済も成長しません」
第二次大戦当時、日本は石油資源を制約された。世界は、限られた資源を奪い合う構造にあった。
「資源生産が拡大する時代、世界全体の人口は増え続けます。環境問題や局地的な紛争など、さまざまな問題はありますが、資本主義の競争原理により、結果として、富はおおむね公平に分配されます。では、資源制約期の世界はどうなるでしょうか?」
合田社長は、世界の金融の歴史を紐解きながら、資源制約期において、人は「金利を取ること」を、ある時代は宗教の教義にまで組込み、さまざまな形で禁じてきたことを説明した。
「閉じられた共同体で複利が積み上がれば、人口の1%が富の99%を独占するような状態に必ずなり、共同体が壊れてしまう。どうすれば、資源制約期に富を公平に分配できるのか。社会がハードランディングしないために、資源制約期に入る『現実』を踏まえて、アフリカであれば、お金の『ものがたり』を書き換えられるかもしれない。そんなことを考えています」
電子マネーなら、妖精が店のお金を持ち出さない
合田社長がビジネスを展開しているのは、南北に長いモザンビークの北東端、インド洋に面するカボ・デルガード州の農村部だ。国土の南端にある首都マプトからは2000km以上離れており「モザンビーク人からも、なぜそんな辺境にいるのかといわれる」ほどの場所だ。
日本植物燃料の主な事業は、社名の通り、植物由来の燃料の生産と販売だ。原料になるヤトロファの苗木を農民約6000人に配り、トウモロコシなどの畑の垣根として栽培してもらい、収穫、搾油、精製し、バイオディーゼル燃料を生産する。
日本植物燃料が現地にキオスク(雑貨店)を設立したのは、燃料の販売拠点目的のほか、発電して充電式ランタンを貸し出したり、製氷サービスを提供したりするためだ。現地で生産されるトウモロコシや米も購入し、精米、製粉などの加工後、流通させてもいる。
「キオスクの運営で問題が起きました。現地の人に店番を頼んでいるのですが、棚卸しすると、現金がどうしても足りない。『なぜだろう』とスタッフに聞くと『この辺りで電気を供給できるのはここだけだから、それを妬んだ人が呪術師に依頼して、妖精を操って店からお金を持ち出したのではないか』というのです。個人的には、面食らいつつ面白いと思ったのですが、事業主としては看過できません」
妖精を追い払うため、途上国向けの電子マネー・システムを提供しているNECと共同で、キオスクに電子マネーを導入したのが、日本植物燃料が金融サービスを提供するきっかけだ。店にはタブレット端末によるPOSシステムを設置し、現地の人に非接触型(NFC)のカードを配布して、キオスクでカードへの入金や買い物をしてもらうようにした。
「それ以来、妖精は出ていません(笑)。しかも電子マネーを導入したことで、村人のお金の流れがわかるようになった。弊社は農作物を買い取っているので、いくらの収入があったけど、ビールを買って使っちゃったとか、種もみを買って翌年に備えているのは誰かなど、お金をどう使ったか、収支を把握できるようになったのです」
現在は、国連食糧農業機関(FAO)と共同で、農民向け資金援助プロジェクトを進めている。従来は紙のバウチャーを農民に渡し、農業商社に持っていって物資に変えていたが、すべて電子マネーで交換できるようにした。
「キャッシュが入ってくるポイントと、共同体の中でどう循環するかを押さえられると、金融の地産地消に向けて、展開しやすくなります」
数の力で勝ちに行く
「僕が考えているのは、数の力で勝負したい、ということです」
モザンビークでは国民の7〜8割が農村に暮らしているが、農村部の電化率は1.7%に過ぎない。
「僕が関わっている農村部には、送電線が来ていません。そんな場所に、ICTで動いている金融機関の支店は開きようがありません。僕らはそこに対して、銀行と電子マネーを組み合わせて金融サービスを提供していきます」
銀行と銀行以外の一番の違いは、お金を預け入れられるかどうかだ。銀行のエージェントとして支店を作るには、資本金や業績の基準をクリアしなければならない。国によって細かい点は違うが、世界中どこでも、銀行を作るには厳格な法令が立ちはだかる。
「電子マネーのエージェントとして店を開く場合、銀行ほどの制約はありません。キオスクをエージェントとして、モザンビークの7〜8割の農村部の人に金融サービスを提供できるのです。同様の環境で暮らす人は、世界全体では20億人以上います。その人口はいまも増えており、20〜30年後には50億人になるともいわれています。そこに僕らが提供しているシステムが広がれば、世界のお金の『ものがたり』を書き換えられるかもしれない。そんなふうに考えています」
「先進国クラブ」といわれるOECD加盟国の人口は、2013年に約13億人。総資産額で見ればかなわなくても、合田社長の「ものがたり」を信じる銀行の利用者が、少なくとも日本のメガバンクの口座数より増える可能性は十分にあるだろう。