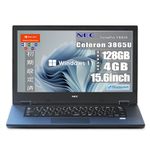Radeon RX 5700シリーズに対抗し
GeForce RTX Superシリーズを準備
これで終わるかと思いきや、AMDのRadeon RX 5700シリーズの投入に向けて、急遽発表されたのがGeForce RTX Superシリーズである。
もっともこちら、YouTubeに謎のディザー広告を出したのは5月23日のことだったのに、その後開催されたCOMPUTEXやE3で一切詳細が明らかにされなかったのは、「カウンター策を打つ」ことは決めており、ラインナップもある程度は固めつつも、AMDの製品ラインナップがわかるまで最終的な構成は決定してなかったのではないか?という気もする。
さてそのRTX Superシリーズであるが、まずはGeForce RTX 2060 SuperとGeForce RTX 2070 Superのみが7月2日に発表(発売は7月9日)となり、GeForce RTX 2080 Superは7月23日以降とされる。
もっとも構成で言えば、GeForce RTX 2060 SuperはGeForce RTX 2070と同じコアを、若干構成を下げ(シェーダーを36SM→34SMに削減)、その分ブーストクロックを若干引き上げ(1620MHz→1650MHz)、おおむね同等の性能になるように調整した(おそらくSM数が減った分、動作周波数が上がりやすくなっているのだろう)もので、それをバーゲンプライス(499ドル→399ドル)で発売するというもの。
GeForce RTX 2070 Superは、GeForce RTX 2080を、こちらも若干SM数を減らし(46→40)、その分ベースクロックを引き上げた(1515MHz→1605MHz)というもので、こちらもおおむね同等の性能になる様に調整したうえで、価格を699ドルから499ドルに引き下げたものである。そういう意味では、あまり技術的には新しい話はなく、純粋にマーケティング的な要素のみである。
ちなみに現状GeForce RTX 2080/2080 Tiのみで利用できるNVLinkであるが、実はGeForce RTX 2070 Superにもコネクターは用意されている。ただ、これが利用可能かどうかははっきりしない。
おそらくリファレンスのものはGeForce RTX 2080用の基板を利用してGeForce RTX 2070 Superを製造したためにコネクターも存在してしまっているのだろうが、OEM製品ではこのあたりが無効化されている可能性がある。
さて、最後がハイエンドのGeForce RTX 2080 Superである。こちらは同じくTU104を使うものの、48SM構成になっており、これはTU104の最大構成である。スペック的にはワークステーション向けのQuadro RTX 5000とほぼ同じ構成であるが、このままだとGeForce RTX 2080との性能差が十分に取れず、差別化が難しいと考えたためだろうか。15.5GbpsのGDDR6を搭載するという無茶な構成になった。
連載515回でも書いたが、Samsungを始めとするメモリーベンダーは現在GDDR6の14Gbps品を幅広く量産出荷しており、これに次いでGDDR6の16Gbpsを用意しようとしている。
ただこちらは歩留まりが低い(Speed Yieldがそこまで上がらないらしい)という話が伝えられており、一般に採用されるのはもう少し後になるかと思っていた。
実際16Gbps品はまだ量産にはおよばない程度の数しか取れていないのだが、15.5Gbpsまで下げればGeForce RTX 2080 Superに利用する程度の数量が確保できる、という判断が下されたようだ。
もちろん根本的にTU102のようにメモリーバスの幅を広げれば簡単なのだが、それはTU104のままでは不可能である。だからといって、TU102ベースで製品を提供するのはコスト面では無理だったようだ。
これは当然で、TU102は754mm2という巨大なダイであり、GeForce RTX 2080 Tiは999ドル、Titan RTXに至っては2499ドルもの価格がついている。これを従来のGeForce RTX 2080と同じ699ドルで出すのはかなり厳しかったのだろう、というのは容易に想像できる。
NVIDIA自身、GeForce RTX 2080 SuperはGeForce RTX 2080 Tiにはおよばない程度の性能としており、ちょうど従来のGeForce RTX 2080とGeForce RTX 2080 Tiの間に位置する、という形を考えたようだ。

この連載の記事
-
第861回
PC
INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -
第860回
PC
NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -
第859回
デジタル
組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -
第858回
デジタル
CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -
第857回
PC
FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -
第856回
PC
Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -
第855回
PC
配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -
第854回
PC
巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -
第853回
PC
7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -
第852回
PC
Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -
第851回
PC
Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ - この連載の一覧へ