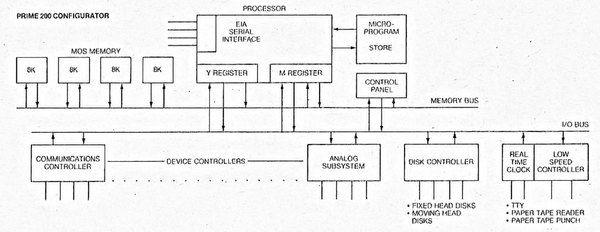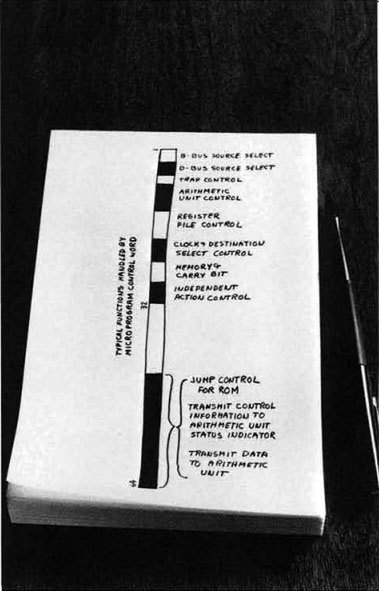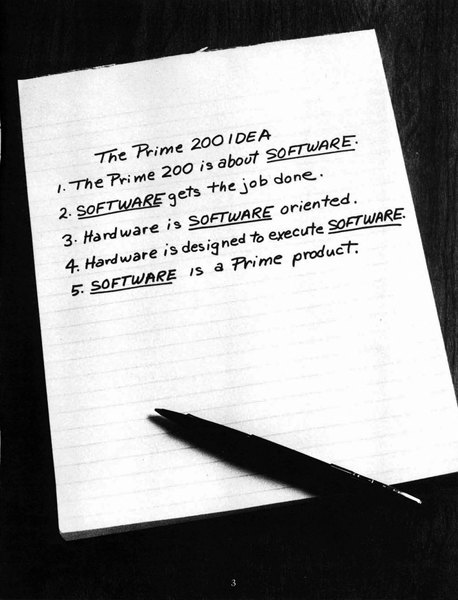今回紹介するPrime Computerはこれまでに2回、名前が出てきている。1回目はBob Rau博士のCydromeで、同社のCydra 5向けに資金提供していたのがPrime Computerだった。
2回目は連載425回で、John William Poduska Sr.博士がApollo Computerの前に創業した会社、という位置付けだ。
Multicsを開発したメンバーが
低価格なミニコンピューターを製造
話は1964年代に遡る。GEとBell研究所、MIT(マサチューセッツ工科大学)はまったく新しい、Multicsと呼ばれるOSの開発を始める。UNIXとの対比(Multics開発の過程で得られた反省を元に、機能のシンプルな実装を目指してUNIXは作られた)としてその名前は知られている。
ちなみに誤解されている節もあるが、Multicsそのものの開発はBell研究所こそプロジェクトから脱落したものの、MITとGEで引き続き行なわれ、最終的にHoneywellやGEのマシンに搭載されることになった。
William Poduska博士ら数名はまさにこのMulticsプロジェクトに関わって働いていた。プロジェクトが終了した1970年台の初期に彼らは相次いでMITを離れるが、そうしたメンバーが集まって作られたのがPrime Computerである。
創業は1972年で、創業メンバーはRobert Baron氏(CEO)、Sidney Halligan氏(営業担当副社長)、James Campbell氏(マーケティングディレクター)、Joseph Cashen氏(ハードウェアエンジニアリング担当副社長)、Robert Berkowitz氏(製造担当副社長)、William Poduska氏(ソフトウェアエンジニアリング担当副社長)、John Carter氏(人事担当ディレクター)の7人である。
1970年代前半というのは、従来のIBMやCDCといった大型なコンピューターが幅を利かせていた市場に、DECやData Generalといったメーカーが16bitの低価格マシンで斬り込みをかけ始めた時代である。
この市場にPrime Computerは、まず最初は16bitのPrime 200というマシンで参入した。ちなみにPrime 200、アドレスは32bit、データは16bitというやや変則的な構成で、これもあって32bitマシンとする向きもあるが、Prime Computerが出した資料そのものに“The PRIME 200 is a fully parallel, 100% rnicroprogrammed, 16-bit computer.”とあるので、16bitマシンとしたいと思う。
画像の出典は、Computer History Museumの“Prime 200 small computer”
性能そのものはそれほど高くなかった(0.1MIPS程度と言われている)が、フルプログラマブルの命令セット(すべての命令が64bitのマイクロコードで格納されている)、64レベルのプライオリティー付き割り込み管理、FPUの搭載など、当時としては先進的な機能も搭載されていた。
画像の出典は、Computer History Museumの“Prime 200 small computer”
ただ、Prime 200の場合はそのハードウェアよりもソフトウェアがメインだった。下の画像がPrime 200のモットーである。そのOSはPrimosと呼ばれていたが、当然ながらこれはMulticsの影響を強く受けるものであった。
画像の出典は、Computer History Museumの“Prime 200 small computer”
もちろんMulticsそのものではなく、開発陣(主にPoduska博士)は彼らなりにMulticsの利点と欠点を見極め、その結果としてPrimosを生み出している。部分的にはUNIXのような面も持っていたが、同じくMulticsの反省から生まれたUNIXとはいろいろ異なる部分もあった。

この連載の記事
-
第781回
PC
Lunar LakeのGPU動作周波数はおよそ1.65GHz インテル CPUロードマップ -
第780回
PC
Lunar Lakeに搭載される正体不明のメモリーサイドキャッシュ インテル CPUロードマップ -
第779回
PC
Lunar LakeではEコアの「Skymont」でもAI処理を実行するようになった インテル CPUロードマップ -
第778回
PC
Lunar LakeではPコアのハイパースレッディングを廃止 インテル CPUロードマップ -
第777回
PC
Lunar Lakeはウェハー1枚からMeteor Lakeの半分しか取れない インテル CPUロードマップ -
第776回
PC
COMPUTEXで判明したZen 5以降のプロセッサー戦略 AMD CPU/GPUロードマップ -
第775回
PC
安定した転送速度を確保できたSCSI 消え去ったI/F史 -
第774回
PC
日本の半導体メーカーが開発協力に名乗りを上げた次世代Esperanto ET-SoC AIプロセッサーの昨今 -
第773回
PC
Sound Blasterが普及に大きく貢献したGame Port 消え去ったI/F史 -
第772回
PC
スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -
第771回
PC
277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ