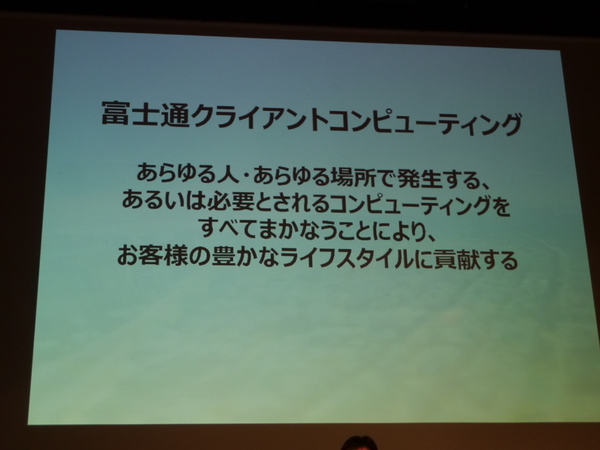今回のことば
「強化できるのであれば、いままでの延長線上でないこともやる。だが、自前の工場がないと富士通のPCの強みは発揮できない」(富士通クライアントコンピューティング・齋藤邦彰社長)
富士通グループのPC事業会社である富士通クライアントコンピューティングは、およそ777gの世界最軽量モデルや、およそ17時間の長時間駆動が可能なモデルをラインナップした13.3型モバイルノートPCをはじめとする、個人向けPC6シリーズ12機種、法人向けPC12シリーズ18機種を、一斉に発表した。
富士通クライアントコンピューティングの齋藤邦彰社長は、「総力をあげて投入した新製品。とくに、モバイルノートPCは、単に小型、軽量で持ち運びしやすいというだけでなく、富士通のデジタルビジネスプラットフォームであるMetaArcで提供されるMobile SUITEによって、業種ごとの様々なモバイルソリューションと連携し、より便利にスマートデバイスとして活用できるようになる。セキュリティーが弱かった領域にも入っていくことで、企業が安心して持ち運んで利用できる環境を提供できる」とする。
持ち運びやすさと壊れにくさによって実現するモビリティーの追求と、安心して利用できるセキュリティーを実現することにこだわったというわけだ。
製品発表会見で、富士通クライアントコンピューティングの齋藤邦彰社長は、「富士通には当社ならではの匠の技がある」と切り出した。
生保と教育向けにカスタムタブレットを開発
「富士通は、PCビジネスを35年間やってきている。この実績をもとにベストフィットの製品を提案していくことができる。また、要望に応じてオーダーメイドで製造、設計が可能であり、顧客が望むリードタイムにあわせて製品を提供することができる」とし、ここに「匠の技」の存在を示す。
具体的な事例としてあげたのが、生保、教育という2つの分野への導入事例だ。
生命保険会社に向けては、薄さおよそ15mm、重量およそ880gの12.1型タブレットを開発。資料をスクロールなしで表示できる4:3のスクエア液晶画面を採用。紙にペンで書くような書き心地を実現する最新デジタイザーを搭載したという。
「営業職員が、契約をその場で決めたいという用途に応じて開発したもの。生命保険会社にとっても効率的であり、顧客にとっても便利なものである。これを実現するために、ありとあらゆるカスタマイズを行なった。これは自前の設計、開発、工場があるからこそできること。市場からも高い評価を得ている」とする。
実際に日本の生命保険業界向け端末では、80%のシェアを獲得。圧倒的な強みをみせる。
また教育分野向けに導入したタブレットでは、滑りにくい「School Grip」や落下時などに衝撃を吸収する「School Face」、滑りにくいキーボードなどを採用。「直接エンジニアが教室に出向いて使い方を確認した結果、日本の教室の机が小さいため、落下が多くタブレットが故障し、それによって授業が止まってしまうということがわかった。タブレットのせいで授業を止めないための工夫を行なった」という。低重心設計とし、重心を本体手前側に置くことで、机からはみ出しても落ちにくい設計を採用するというこだわりもみせた。
さらに学校のあらゆるシーンで教員が利用できるようにも配慮。理科室や家庭科教室、プールでも使用できるように防水、防塵、塩素水対応を図り、体育館のような薄暗い場所でも撮影しやすいカメラを搭載するといった工夫を施している。
同様に北米の教育機関向けには、新たなに導入されたPCに、1台ずつ管理用のラベルを貼るということを行なっていたが、これを量産ラインで対応。さらに1台ずつの梱包ではなく、集合梱包を行うことでコストダウンを実現。そのほか、量産ラインにクリーンルームを作り、画面に傷が付かないようにする「スクリーンプロテクター」を貼付するサービスも提供した。「これらも、自前の工場があるからこそのカスタマイズだ」とする。
文教市場におけるWindowsタブレットの導入シェアでは、86%を獲得。ここでも同社独自のカスタマイズが市場に受け入れられていることを示した。
統合を模索しながらも、「工場がないと事業方針が維持できない」
富士通のPC事業は、レノボへの統合を前提とした戦略的提携を模索しているところだ。
それがどんな形で統合されるのかは、現時点では明らかになっていない。
富士通クライアントコンピューティングの齋藤邦彰社長は、「法人ユーザー、コンシューマユーザーに向けて、富士通がユニークなものを提供していくことは変わらない。それを強くするための提携を狙っている。強化することができるのであれば、いままでの延長線上ではないこともやる」とする。
だがその一方で「富士通のPC事業の強みは匠の技術によって実現されるカスタマイズであり、それを実現するのが自前の工場の存在。顧客にカスタマイズが受け入れられる限り、工場を自前で持つことがツールとしても不可欠である。工場がないと我々の強みがなくなる」とする。
そして「工場がないと、富士通のPC事業の方針が維持できない」とも語る。
富士通クライアントコンピューティングは、同社の基本方針を、「あらゆる人、あらゆる場所で発生する、あるいは必要とされるコンピューティングをすべてまかなうことにより、お客様の豊かなライフスタイルに貢献する」としている。
これを実現するには、工場の存在が不可欠だというわけだ。
富士通のPC事業は、国内の工場を維持した形でレノボに統合後も事業を継続できるのか。その点が気になる。

この連載の記事
-
第600回
ビジネス
個人主義/利益偏重の時代だから問う「正直者の人生」、日立創業者・小平浪平氏のことば -
第599回
ビジネス
リコーと東芝テックによる合弁会社“エトリア”始動、複合機市場の将来は? -
第598回
ビジネス
GPT-4超え性能を実現した国内スタートアップELYZA、投資額の多寡ではなくチャレンジする姿勢こそ大事 -
第597回
ビジネス
危機感のなさを嘆くパナソニック楠見グループCEO、典型的な大企業病なのか? -
第596回
ビジネス
孫正義が“超AI”に言及、NVIDIAやOpen AIは逃した魚、しかし「準備運動は整った」 -
第595回
ビジネス
DX銘柄2024発表、進行する日本のDX、しかし米国よりもここが足りない!! -
第594回
ビジネス
自動車工業会は、今年もJapan Mobility Showを開催、前身は東京モーターショー -
第593回
ビジネス
赤字が続くJDI、頼みの綱は次世代有機EL「eLEAP」、ついに量産へ -
第592回
ビジネス
まずは現場を知ること、人事部門出身の社長が続くダイキン -
第591回
ビジネス
シャープが堺のディスプレーパネル生産を停止、2期連続の赤字受け -
第590回
ビジネス
生成AIに3000億円投資の日立、成長機会なのか? - この連載の一覧へ