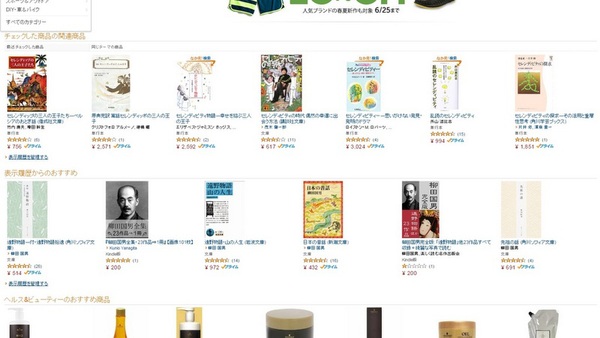情報同士がつながり、新たな価値を生み出していく
効率化や合理化は敵? インターネットは無駄な情報に価値がある
2015年06月23日 10時00分更新
私事で恐縮だが、いま、引っ越しの準備をしている。現在住んでいるところには10年も腰を落ち着けてしまったため、不要なものの処分が大変である。特に困るのは、仕事柄どうしても増える本。
そこで、「これはもうさすがに読まないだろ?」というものを売却すべく、意を決して本棚の前に立ち、選別作業に入ろうとするのだが、これがなかなかはかどらない。なぜか? 理由はいたって簡単で、そんなことをしている場合ではないのに、手に取った本をついつい読んでしまうからだ。
「本来の目的を忘れて別のことに気を取られてしまう」という不思議な現象……。この「寄り道癖」とでも呼べるようなものは、引っ越しのときばかりでなく、普段、われわれがインターネットを通じて情報と接しているときにもしばしば露呈する。
「非効率」かつ「非合理」な情報とのたわむれが意外な発見をする
仕事や学業でどうしても詳しく調べなければならない事柄があったとしよう。まずは、Googleで検索をかけてみる。いくつかの結果が表示される。その中から任意のテキストを読む。すると、文中によくわからないワードが出てくる。仕方がないのでその語句をクリックし、新たに表示された文書を読むと、今度はそこにかねてから気になっていた用語があり、この際だからちょっと見ておこうなどとさらにリンクをたどってしまう……。
こんなことを繰り返してるうちに、とうとう、「あれ、最初、何を調べようとしてたんだっけ?」ということになる。
人によってはこうした不可解な行動を一刀両断に「無駄」と断罪するかもしれない。ベンジャミン・フランクリン流に「時は金なり」の観点に立てば、確かに時間の浪費である。
しかし、アナログ/デジタルを問わず、人間と情報との関係を考えるとき、この「偶発的」な情報との邂逅、「非効率」かつ「非合理」な情報とのたわむれは、実はとても重要なことだ。思いがけない場面で思いがけない情報とばったり出会うとき、人間は意外な発見をしたりすることが多い。
(次ページでは、「なぜ無駄な情報が必要なのか」)

この連載の記事
-
第15回
トピックス
ネットの民意がリアルに反映されないケースはなぜ起こる? -
第14回
トピックス
電子書籍がブレイクしない意外な理由とは -
第13回
トピックス
国民半分の個人情報が流出、情報漏えい防止は不可能なのか -
第12回
トピックス
Apple WatchとGoogle Glassは何が明暗を分けたのか? -
第11回
トピックス
誰も教えてくれない、ウェアラブルを注目すべき本当の理由 -
第10回
トピックス
ドローンやウェアラブル、Netflixから見る情報のもどかしさ -
第9回
トピックス
PCと人間の概念を覆しかねないシンギュラリティーの正体 -
第8回
トピックス
PCが売れないのはジョブズが目指した理想の終了を意味する -
第7回
トピックス
ビジネスにもなってる再注目の「ポスト・インターネット」ってなに? -
第6回
スマホ
アップルも情報遮断の時代、情報をうまく受け取る4つのポイント -
第5回
スマホ
僕らが感じ始めたSNSへの違和感の理由と対処を一旦マトメ - この連載の一覧へ