アドビシステムズ(株)は23日、電子書籍閲覧ソフト『Adobe Acrobat eBook Reader 2.2 日本語版』(β版)の無償ダウンロード提供を開始した。
Adobe Acrobat eBook Reader 2.2 日本語版は、電子書籍の購入、閲覧、管理を行なうためのソフト。ウェブブラウザー機能を搭載しており、“書店ボタン”をクリックするとあらかじめ登録されているオンライン書店のウェブサイトにアクセスできる。一覧表示された電子書籍の中から欲しいものをクリックすると購入/ダウンロードできる。
 | 『Adobe Acrobat eBook Reader 2.2 日本語版』の画面。オンライン書店にアクセスし、一覧表示された電子書籍の中から希望するものをクリックすると購入/ダウンロードできる |
|---|
電子書籍を閲覧する際は、1ページずつの表示/見開き2ページ表示の切り替えが可能。本文のテキスト検索やしおり挿入、マーカー塗り、メモ記入なども行なえる。対応OSは、Windows 98/Me/NT4.0/2000、およびMac OS 9.0/9.1。今回無償提供されるのはβ版だが、数ヵ月後には製品版をリリースするという。
 |
|---|
| Acrobat eBook Reader 2.2 日本語版の電子書籍閲覧画面 『諸葛孔明』(陳舜臣/著) (c)中央公論新社 |
電子書籍を販売する出版社/書店側は、サーバー製品『Adobe Content Server』を通じてeBookの配信を行なう。Adobe Content Serverは、PDF形式の電子書籍を暗号化する機能や、暗号化された電子書籍を復元化するためのバウチャー(領収書)を発行する機能を搭載する。バウチャーは、ユーザーが電子書籍を購入してダウンロードしたパソコンでのみ有効となる。また、電子書籍ごとに印刷許諾/回数制限、貸し借り/譲渡の許諾などを設定可能。対応OSはWindows NT4.0/2000 Server/2000 Advanced Server。価格は年間ライセンス料金が5000ドル(約61万円)、ロイヤリティーがコンテンツの定価3%。
対応各社がeBookを販売
また同社は、オンライン書店運営会社など5社が、同社のAdobe PDF形式を採用した電子書籍(eBook)サービスを開始したと発表した。eBookへの対応を表明したのは、(株)イーブックイニシアティブジャパン、ソニーコミュニケーションネットワーク(株)、(株)インディビジオ、(株)パピレス、(株)中央公論新社の5社。
 |
|---|
| eBookに対応したサービスを行なう企業の代表者。左から、イーブックイニシアティブジャパン代表取締役社長の鈴木雄介氏、ソニーコミュニケーションネットワークbitbazaarプロジェクトプロジェクトリーダープロデューサーの村上真一氏、インディビジオ代表取締役社長の白川洋次郎氏、パピレス代表取締役社長の天谷幹夫氏、中央公論新社書籍編集局デジタル編集部部長の矢内栄一氏 |
イーブックイニシアティブジャパンは、同社が運営するオンライン書店“10daysbook”で、eBookの販売を開始する。10daysbookでは従来より独自フォーマットの電子書籍を販売していたが、本日より“Adobe館”というコーナーを設け、そこでeBookを販売するという。
ソニーコミュニケーションネットワークは、同社が運営するインターネット総合サービス“So-net”のサイト内に、ウェブ上の現代美術館“Internet Museum of Art”を本日オープンした。“Internet Museum of Art”は、毎月1人の現代美術作家の個展(企画展)をサイト上で開催するウェブ美術館で、企画展示を終えた作品群は、常設展示コーナーへ移動する仕組みとなっている。キュレーター(美術館館長)は編集者/写真家の都築響一氏。第1回企画展は都築氏の個展“賃貸宇宙”で、11月下旬に開催される。利用料金は700円で、3日間何回でも閲覧可能。“Internet Museum of Art”は、アーティスト作品の著作権保護のため、Adobe eBook Readerを採用している。
インディビジオは、同社が運営するコミックサイト“FRANKEN”を11月1日にリニューアルし、eBookコミックを販売する。また、パピレスは、同社が運営するオンライン書店“電子書店パピレス”で、中央公論新社の文庫新刊13冊をeBookとして販売する。さらに今後はエイガアル(株)と協力し、寺沢武一氏のコミックスをeBook形式で販売する予定という。
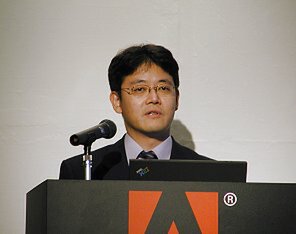 |
|---|
| アドビシステムズ代表取締役副社長の石井幹氏。「米国の電子書籍市場は日本円で約4500億円規模。日本市場は始まったばかりだが190%の成長率となっており、2005年には540億円程度の市場規模になるだろう」 |











































