コラボレーションアート“連画(linked image)”は、CG作品をネットワークで送りあい、相手の作品を引用したり直接手を加えることによって新しい作品を生み出し、組作品を成長させる創作システムである。連画のシステムを発案したのは、CGを中心とした創作活動に携わるアーティストの安斎利洋氏と、中村理恵子氏。'92年第1回目の連画セッション『気楽な日曜日』より数々の作品を発表し、その作品は“SIGGRAPH”など国際的な展示会で注目を集めてきた。
そして'98年、このコラボレーションに全盲の造形作家の光島貴之氏を迎え、連画チームは新たなプロジェクト“触覚連画”を開始した。
光島氏は京都で鍼灸院を営むかたわら、製図用のレトラライン(粘着テープ)や粘着シートを用いた凹凸感のある平面絵画“触覚絵画”を発表するアーティスト。今回ascii24では、安斎氏と中村氏、光島氏の3人に対談を行なった。
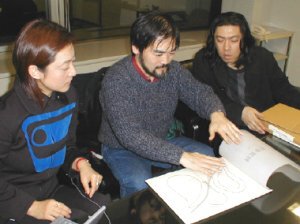 |
|---|
| 左から、中村理恵子氏、安斎利洋氏、光島貴之氏 |
--触覚連画の構想はいつごろ挙がったのでしょうか?
安斎「'97年のイベントで、光島さんの作品と出会ったのがきっかけです。作品を見た瞬間、彼とやりたいと感じました。そこで、僕らも光島さんが表現している触覚の世界を取り入れた表現ができないかと、触覚連画を思い立ちました」
中村「触覚連画を行なう前、連画のプロジェクトにおいて、畑違いのコラボレーション相手ということで中国の書家や文学者とのセッションをすでに経験していました。触覚連画は、とにかくやってみたいという気持ちが先行していました。通産省の“マルチメディアコンテンツ制作支援事業”に触覚連画プロジェクトの企画案を提出したところ予算が付きました」
 |
|---|
| 光島氏。3月15日より10日間、ギャラリイK(中央区銀座1-9-6)にて個展“触覚時間の体験 光島貴之展”を開催。入場料は無料 |
光島「もともと僕は粘土とか立体造形中心に作品を作っていました。'95年ごろに平面の創作活動を開始し、2人と出会ったころはその表現手法について暗中模索の最中でした。そういうときに声を掛けられて。他人の絵に触って、いろいろ手を加えることができるというので、それは面白いと思いました」
「触覚とデジタル画像をコラボレートさせるシステムをどうするかなど、様々なハードルが存在していましたので、当初は本当に実現する企画かどうかとても不安でした。しかし、2人が企画書を点訳してくれたり、ハードウェアを準備してくれたりとか、実現性のある方向を示してくれたので、これはイケるぞと感じました」
触覚連画のコミュニケーションと作業の流れ
ここで、触覚連画のコミュニケーションの流れと、その手法を説明する。触覚連画は、光島氏を核に、中村氏-光島氏、安斎氏-光島氏の2つの道筋を基本として作品を送りあうという方法をとっている。(1)光島氏->中村氏/安斎氏
光島氏の平面作品は、アナログの状態(紙作品のまま)でそのまま郵送で次の担当者(中村氏/安斎氏)に送られる。これを受け取った次の担当者は、スキャナーを使って光島作品をデジタイズした上で、パソコンでCGアプリケーションを用いて連画作品を制作する。
(2)中村氏/安斎氏->光島氏
こうして出来上がった安斎氏や中村氏のデジタル作品を、逆に光島氏に送る場合、デジタルデータではなく触覚で理解できる出力状態で送る必要がある。ここで採用されているのは、ラスタデータをベクターデータに変換し、カッティングマシンでシートを切りぬき張り付ける方法と、熱処理を利用した立体コピーなどで凹凸化するという方法だ。
こうして出力された作品は、剥離紙が付いたままの状態でベクターデータの形に切りぬかれた予備のカッティングシートと一緒に、郵送する。
(3)光島氏->中村氏/安斎氏
これを受け取った光島氏は、その予備のシートと画材を使って、次の連画作品を制作する。なお、これら使用している機材は特注ではなく、すべて市販のもの。
以下、(2)(3)を繰り返す。
 |
|---|
| 光島氏が画材として使っているレトララインは、もともと製図用。レトララインの持ち手部分に、点字で“青”や“赤”といったテープのカラーが記されている。光島氏は10才ごろに失明。目が見えたころの記憶を頼りにカラーを選ぶという |
現在、今まで制作した触覚連画の全作品は、連画のオフィシャルサイトで公開されている。触覚連画は連画同様、いわゆる“合作”と異なり、完成作品(もしくは現時点の最新作品)だけではなく、制作過程の1つ1つの作品も同様に発表している。そのため、1つの組み作品として、あたかもジャズのセッションのように、クリエーター間の対話や、作品の要素が交配する様子を楽しめる。
触覚連画
触覚連画チームはすでに1組の組作品を完成し、現在は“第2セッション”として新たな組作品を製作している。対談当日、安斎氏から光島氏に、新作が直接手渡された。安斎「これは、中村さんの作品『幸せを運ぶクモ』をモチーフにした僕の作品です。光島さんにも今日初めて触ってもらうんですよ。タイトルは『涙の音』」
安斎「目の下の部分を使って、閉じた目にしてみた。上まぶたが閉じてる状態、というつもり。“閉じた目”は、三日月形で表現することが多いんですよ」
光島「ここが下まぶたかな? じゃあこの下のほうにあるのが涙か……」
 |
|---|
| 安斎氏の新作『涙の音』に触れる光島氏。作品の黒い部分はカッティングシートで、凹凸で表現されている。現在、連画公式サイトでは『涙の音』に続く光島氏の新作『腕輪』と、中村氏の新作『アプリ家のマドンナ』が発表されている |
「あの半分の形というのは、靴下の本質の形じゃないですよ」
--連画に対し、“触覚連画ならでは”ということで何か発見がありましたか?安斎「一番は、光島さん自身の形の認識の面白さです。触覚の世界っていうのは、健常者には分からない、僕らとは、形の認識の仕方が全く違う世界です。僕らと違う線を描くわけですよ」
「例えば、空き缶があるとする。僕らは“フタが見えれば底は見えない”というように、輪郭による認識に囚われています。でも、光島さんの描く世界は、視覚による概念に邪魔されず、缶の構造を認識しているように思えます」
中村「第1セッションのとき、『オシャレして汽車にのってお出かけしよう! 』という作品で、私は靴下を描きました」
「この絵を立体加工して手渡したのですが、靴下を表現するときによく用いられる形で、ペタンコな状態の輪郭でした。でも、光島さんは靴下の部分を指で触っても、何が描いてあるのか絶対に伝わらなかった」
中村「光島さんは、靴下売り場の靴下、半分の状態の輪郭じゃなくて、靴下をはいている状態と、脱いだときのクシュクシュの形で認識していたそうです。このことは、私たちにとって大きな発見でした」
安斎「あの半分の形というのは、靴下の本質の形じゃないですよ」
光島「すぐはいてしまうか、脱いでしまうかで、折りたたんだ靴下を机の上において、まじまじと触るなんてことはないですよね」
次回、安斎氏と中村氏にとっての触覚連画の醍醐味とは何か、その魅力について連画チームが語る。



































