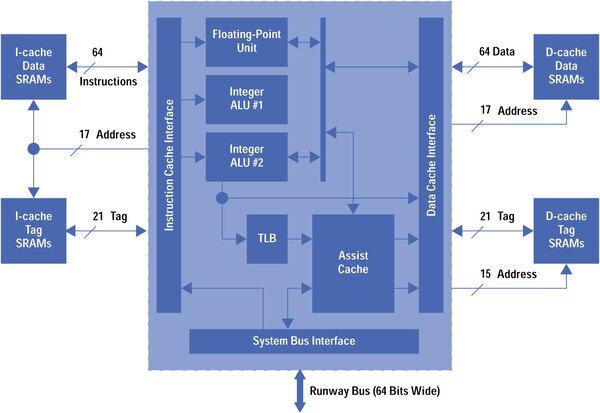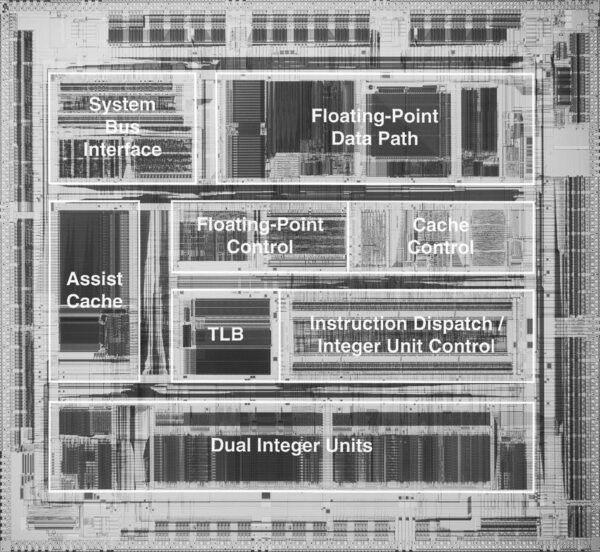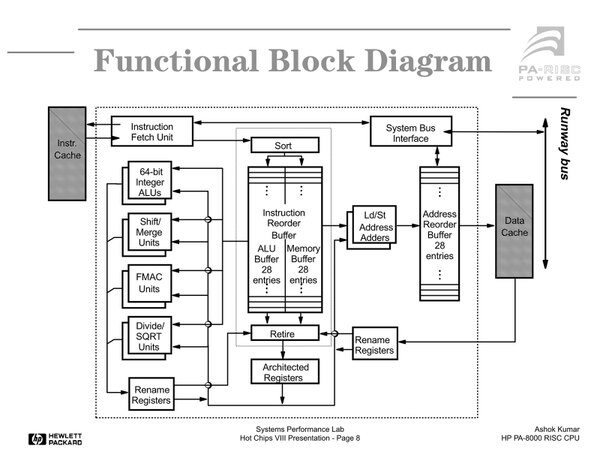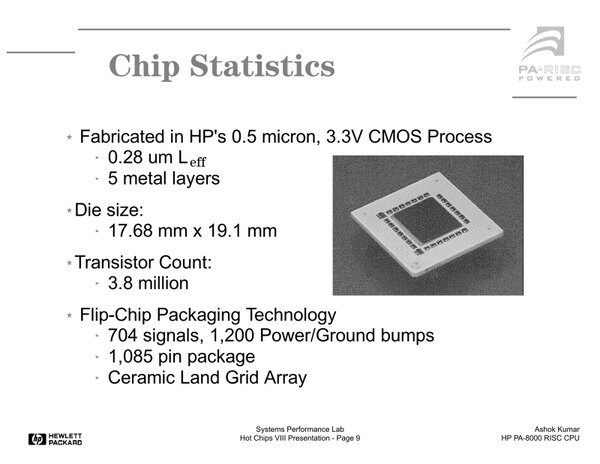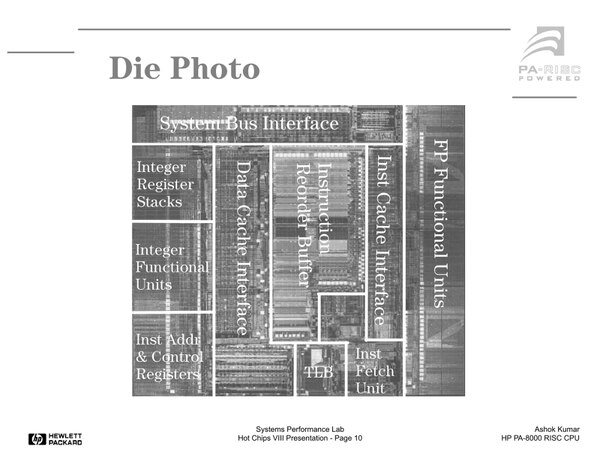動作周波数あたりの性能が高い
PA-RISCをプロセッサーに採用
このPA-RISCについては、以前Mercedの回で少し触れただけなので、細かく説明しよう。
PA-RISCのご先祖様は、HPが1982年に発表したHP 9000/500シリーズというワークステーションに利用されていたFOCUSと呼ばれるプロセッサーである。このFOCUSそのものは純粋にCISCで、Bit Slice方式のStackアーキテクチャーを利用したものである。
1.5μmプロセスのNMOSで製造され、トランジスタ数は45万、動作周波数は18MHzだったと伝えられている。このFOCUSの性能を上げるべくいろいろ開発していくなかで、RISCを利用して性能を上げよう、という試みが最終的にPA-RISCとなって結実した。ちなみにPAはPrecision Architectureの略である。
最初に定義されたPA-RISC 1.0は1986年に発表された。これに基づくCPUとしては、TS-1/NS-1/NS-2/PCXの4種類がある。TS-1はある意味本当の試作品のようなもので、8MHz動作、1次キャッシュは128KBという構成で、シングルパイプラインの構成である。
これをもう少し実用的にすべく作られたのが、動作周波数を30MHzまで上げたNS-1(1987年)と、動作周波数は27.5MHzどまりながら1次キャッシュを1MBに増量し、さらにマルチプロセッサー構成を可能にしたNS-2(1989年)が登場する。
最終的に1990年にリリースされたPCXは、NS-2に似た構成ながら50MHzまで動作周波数を引き上げる。
ただこのPA-RISC 1.0に基づくCPUはいろいろ制約が多かった。PA-RISCの命令フォーマットは昔のRISCらしく、主要な命令は1サイクルで実行可能で、マイクロコードは利用せず、命令長は32bit固定。メモリーアクセスはLoad/Store命令のみ、といった具合である。
レジスターは汎用が32個、シャドウレジスターが7個あり、論理アドレスは48bitとなっている。このあたりは使いやすそうな感じであるが、その一方でメモリー管理ユニットも仮想記憶のサポートもないというのは、本格的なOSを載せるのが極めて困難だった。
またプロセスの微細化が遅れたこともあり、1次キャッシュやFPUは全部外付けとされている。というわけで、ここまではある意味試作が続いたようなものである。
このあたりを対策したのが1991年に発表されたPA-RISC 1.1である。大きな違いはメモリー管理ユニットと仮想記憶のサポートだが、この世代からスーパースカラーも実装される。
1991年に発表されたPA-7000は最初にスーパースカラーに対応した製品で、これはまだパイプラインが1本(動作周波数は66MHz)だが、1992年に登場したPA-7100LC/PA-7150はついに2wayのスーパースカラーが搭載された。といっても、最初はALUとFPUがそれぞれ1本づつの構成であるが。そして、動作周波数も100/125MHzに引き上げられた。
ちなみにここまでのプロセッサーはいずれも、昔のPentium IIや初代Athlonのようにプロセッサーモジュール上にキャッシュ用SRAMが外付けされている構成である。
これに続き1994年に登場されたPA-7100LCは低コスト向けということで外付けキャッシュを廃し、その代わりに内部に1KBの1次キャッシュを搭載している(ただし、オプションで外付けキャッシュを利用可能で、これは2次キャッシュ扱いとなる)。
さらにMAX-1と呼ばれるSIMD拡張命令も追加される。このMAX-1は構成も狙いもx86で言うところのMMXと良く似ており、外部アクセラレーターなしでMPE-1のデコードを可能にするというものだった。
ただし、MAX-1は1 CPUのワークステーション向けの製品ということで、SMPのサポートは削られているため、SPP 1000は向かないものだった。もっとも開発時期を考えると、1994年登場のPA-7100LCではSPP 1000のリリースには間に合わないのだが。
さて、これに続いて1995年に登場したのがPA-7200である。こちらは下の画像のように、2本のALUと1本のFPUを持つスーパースカラー構成の製品である。
画像の出典は“Design of the HP PA 7200 CPU(Hewlett-Packard Journal February 1996)”
メインとなるキャッシュは相変わらずオフチップ(2次キャッシュ扱い)だが、2KBのアシストキャッシュ(1次キャッシュ扱い)が内蔵されている。
製造プロセスは0.55μmのCMOSプロセスで、およそ126万トランジスタ、動作周波数は最大140MHzだった。このPA-7200の性能を当時の他の製品と比較したのが下の表だ。
画像の出典は、旧MicroDesignのMicroProcessro Report Vol.8. No.3(March 7, 1994)”
| PA-7200の性能比較 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECint92 | SPECfp92 | |||||
| PA-7200 100MHz | 141.0 | 223.9 | ||||
| Alpha 21064 200MHz | 138.4 | 187.6 | ||||
| Pentium Pro 200MHz | 366.0 | 283.2 | ||||
ただAlphaはもうこの時期には21164のリリースを予定していたため、ここで大きく性能を引き上げられる予定であった。それでも140MHz動作にすれば、Alphaには拮抗できそうでも、Pentium Proにはまだおよばない感じで、性能不足は明白であった。
HPはこの後7200のローコスト版として、SMPのサポートを削り、MAX-1を搭載したり(PA-7200にはMAX-1は未搭載)、オンチップキャッシュを128KBまで引き上げたPA-7300LC(最大180MHz)を1996年にリリースした後で、PA-RISC 2.0を発表する。
PA-RISC 2.0では64bitアドレスがサポートされたほか、ついにアウト・オブ・オーダーの実装を可能にするIRB(Instruction Reorder Buffer)の仕様が追加された。
またMAX-1はワークステーション用という扱いで、SMPに対応したCPUには未搭載だったが、PA-RISC 2.0ではこれを拡張したMAX-2が標準で入るようになる。これに基づく最初の製品が、やはり1996年に登場したPA-8000である。
PA-8000は整数演算×4・浮動小数点演算×4・Load/Store×2という10個のパイプラインを持つ4way スーパースカラー/アウト・オブ・オーダーの重厚な構成になった。
画像の出典は、HotChips VIII(1996年)で同社のAshok Kumarが発表した“The HP PA-8000 RISC CPU”
プロセスは同社のCMOS-14C(0.5μm CMOS)を利用し、動作周波数は最大180MHzとされた。
画像の出典は、HotChips VIII(1996年)で同社のAshok Kumarが発表した“The HP PA-8000 RISC CPU”

この連載の記事
-
第864回
PC
なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -
第863回
PC
銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -
第862回
PC
「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -
第861回
PC
INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -
第860回
PC
NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -
第859回
デジタル
組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -
第858回
デジタル
CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -
第857回
PC
FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -
第856回
PC
Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -
第855回
PC
配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -
第854回
PC
巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ