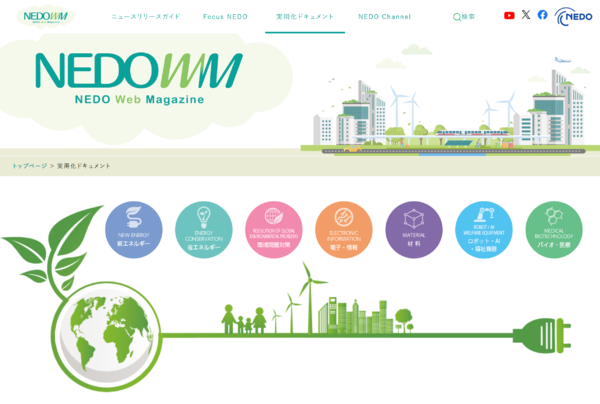「NEDO Web Magazine」にて2024年度の最新コンテンツを配信開始!
博士! 日本の技術力の高さとそれを支えるNEDOの役割が分かる「NEDO実用化ドキュメント2024」って何ですか?
2024年06月28日 15時00分更新

博士!「NEDO」について教えて!
助手: 博士、博士~! NEDOってなんですか!?
博士: なんじゃなんじゃ藪から棒に。
助手: インターネットを見ていたら、偶然面白そうなサイトを見つけたんです。それがどうやらNEDOという組織の運営しているサイトらしくて、そこに面白くて我々の研究にも役立ちそうな情報の記事がたくさん載っていたんで気になってしまって…。
博士: ああ、なるほどのぉ。それは助手くん、いいところに目を付けたぞ。ではまずNEDOについて説明しようかの。
NEDOとは、新エネルギー・産業技術総合開発機構(New Energy and Industrial Technology Development Organization)の略称なんじゃ。経済産業省が所管し、エネルギーと地球環境問題の解決、産業技術力の強化を目指している国立研究開発法人のことじゃな。
助手: へー。具体的にはどんな仕事をしているんですか?
博士: NEDOは主に3つの役割を担ってるんじゃ。まず1つ目に、技術戦略やプロジェクトの企画と立案じゃ。技術戦略というのは世界中から情報を集め、将来的に取り組まなければいけないことをまとめた戦略的な方針のことじゃ。その方針に則って研究開発を進めていくための国家プロジェクトを作り上げていくわけじゃな。
2つ目に、プロジェクトのマネジメントじゃ。民間企業に限らず、大学や研究機関などを巻き込んだ産学官一体の体制を作れるのもNEDOの強みなんじゃ。こうした体制づくりや評価と改善、必要な資金の配分などを通してプロジェクトの運営を担っておるんじゃ。
そして3つ目に、得られた成果の実用化と社会への実装を積極的にサポートすることで、様々な社会課題の解決を目指している、というわけじゃな。
助手: なるほどー。技術戦略を練るところから成果の社会実装まで、一貫した推進をしているということですね。産学官一体となって技術開発と実証に取り組むことで、エネルギー・環境問題の解決と産業競争力強化の両立を目指しているんですね。
博士: その通りじゃ。NEDOはイノベーション・アクセラレータとしての役割を担って、社会の抱える様々な課題の解決を目指しているんじゃな。
「NEDO実用化ドキュメント」って何?
助手: それじゃあ博士、私が見つけた、「NEDO Web Magazine」(外部リンク)というサイトに掲載されている「NEDO実用化ドキュメント」(外部リンク)というコンテンツについても教えてもらえますか?
博士: ああ、「NEDO実用化ドキュメント」についてじゃな。これはNEDOが支援した技術の中から、実用化に至ったものをまとめたドキュメントじゃな。NEDOが毎年更新して、それをウェブ上にも掲載しておるんじゃ。
助手: なるほど、NEDOが支援した技術の実用化事例が紹介されているんですね。具体的にどんな内容が記載されているんですか?
博士: まず、実用化に至った技術の概要が書かれておるの。その技術の特徴や長所、どのような課題を解決するのかが説明されとるんじゃな。次に、NEDOによる支援の経緯が記載されとる。研究開発の段階からどのようにサポートしたかが書かれているんじゃ。最後に、実際にその技術が製品化や事業化された例が紹介されてるんじゃ。
助手: なるほど、技術の詳細からNEDOの支援内容、そして実用化の成果までが一つの事例としてまとめられているんですね。このドキュメントを読めば、日本の優れた技術とNEDOの支援の関係が良くわかりそうですね。
博士: その通りじゃ。「NEDO実用化ドキュメント」を読めば、日本の先端技術が、NEDOの支援によってどのように実用化に結びついたかが一目瞭然じゃ。助手くんもこれを読めば、日本の産業技術力の高さと、NEDOの役割の大切さが実感できると思うぞ。
助手: わかりました。日本の技術力とNEDOの活動を知る上で、この「NEDO実用化ドキュメント」は重要な資料なんですね。ぜひ一度目を通してみたいと思いますが、たくさん事例が載っているので、どれから読み始めればいいか迷っちゃいますね。
博士: それなら、まずは今年新しく追加された実用化事例を読んでみるといいじゃろう。NEDO実用化ドキュメントは、1年に1度コンテンツが追加更新されるんじゃが、2024年度の更新では、3つの新しい実例が紹介されておるぞ。
日本の空をドローンが飛び交い、配送や点検を行う未来
助手: へー。今年公開されたのは3つなんですね。1つ目は
●ドローンが飛び交う世界を実現する「複数台ドローン運航管理システム」(外部リンク)
というやつですね。
博士: そうじゃな、このドキュメントはKDDIが開発した、複数のドローンを安全に同時運航できる革新的なシステムについて書かれておるんじゃ。
助手: へえ、複数のドローンを同時に運航できるシステムですか。詳しく教えてもらえますか?
博士: もちろんじゃ。このシステムは、たくさんのドローンを自動で飛ばしながら、1人の管理者がそれらを遠隔操作できるようになっておるんじゃ。これを使って、物流の荷物運搬やインフラ施設の点検など、複数のドローンを効率的に活用できるようにしようというわけじゃな。
助手: なるほどー。これは画期的なシステムですね! でも、安全性はどうなっているのでしょうか? たくさんのドローンが同時に飛び交うなんて危なくないですか?
博士: 安全性への配慮は特に重視されておるんじゃ。このシステムには、各ドローンの位置情報や飛行状況をモバイル通信網で常に把握できる仕組みがあるのじゃ。万が一、他のドローンや航空機に接近しそうになれば警報が出て、管理者が回避操作できるようになっておる。飛行規制区域の情報も入力されておって、事前に危険エリアを回避できるんじゃ。
助手: へー、すごいですね。このドローン運航管理システムは、ほかにはどんな可能性があるんでしょうね。
博士: おおいに可能性は秘められておるぞ。物流や点検だけでなく、救助活動や災害対応など、さまざまな場面で大活躍が期待できるんじゃ。例えば、有人地帯の上空を自由に飛べるようになれば、荷物の長距離運搬や遠隔地での無人監視など、新しい利用法が生まれてくるじゃろう。KDDIは、このシステムを発展させて、世界に誇れる日本発の技術にしていきたいと考えておるそうじゃ。
助手: なるほど、夢のある未来技術なんですね。このドキュメントを読めば、そのドローン運航管理システムの仕組みや可能性を知ることができそうですね。私もぜひ読んでみたいと思います!
博士: それは結構じゃ。ドローンの最先端技術に触れて、未来への夢を膨らませることができるじゃろう。ちなみに、NEDO実用化ドキュメントの内容を紹介している動画も公開中じゃ。動画で学ぶのもおすすめじゃぞ。
今日もいつものロボットが配達にやってきた、が当たり前に!?
助手: 博士、次は2つ目の
●人とロボットが共存する日常を目指す「自動配送ロボット ハコボ」(外部リンク)
についても内容を教えてもらえますか?
博士: いいじゃろう。このドキュメントは、人とロボットの共存社会を実現するための新しいロボット技術の話じゃよ。
助手: 人とロボットが共存する社会って、すごく未来的な感じがしますね。具体的にはどんなロボットの話なんですか?
博士: パナソニックが開発した「ハコボ」という自動配送ロボットの話じゃ。障害物を検知するセンサーやAI技術を搭載しておってな、人が行き交う街中を、ロボット単体で自律的に走行して荷物を配送できるんじゃよ。
助手: 本当ですか!? ロボットが一人で自分の判断で配送をするなんて、スゴい技術ですね。でもやっぱりここでも安全面が心配になりますね。
博士: よく分かっておるな。ハコボは完全自動ではなく、遠隔の管制センターで人間がモニタリングしていてな。もし危険な状況になれば人間がロボットを操作して対応するんじゃ。
助手: なるほど、人とロボットが協調しながら安全運用を実現しているんですね。でも一人で1台のロボットを監視したのでは、人が直接働いても効率アップするのは難しいですよね?
博士: よく気がついたの。そこでパナソニックでは、一人のオペレーターが複数台のハコボを同時に運用・管理するシステムを目指しておるのじゃ。現在は最大4台の同時運用が可能で、将来的には一人で10台以上のハコボを一括運用できるシステムを目指しているんじゃ。
助手: えっ!? 10台以上もですか!? それなら人手不足の解消にもつながりそうですね。
博士: そのとおりじゃ。このドキュメントを読めば、ハコボの技術的な裏付けや課題、そして社会実装に向けたパナソニックの挑戦、もちろん、その中でNEDOが果たしてきた役割も分かるじゃろう。人とロボットの共生社会実現に向けた、パナソニックの壮大なビジョンの一旦が見えるはずじゃ。
助手: なんだか本当にワクワクしてきましたね! ロボット技術の未来かー。興味深いドキュメントですね。これもぜひ読んでみたいですね!
博士: こちらのプロジェクトも、動画で紹介されておるので、そちらも要チェックじゃぞ。
将来、予防注射で泣く子供はいなくなるかも?
助手: 最後も面白そうなドキュメントですね。
●美容と医療に革新をもたらす痛くない注射針「中空型マイクロニードル」(外部リンク)
かぁ。美容と医療、とっても興味があります!
博士: ほっほっほ。ところで助手くんは、注射は好きかな?
助手: えー! 注射が好きな人なんていないですよ。痛いですし。
博士: ほっほっほ。このドキュメントはな、ズバリ、痛くない注射針の開発について書かれているんじゃ。「中空型マイクロニードル」というんじゃがな。
助手: 痛くない注射ですか!? それはすごい! その、中空型マイクロニードルというはどんなものなんですか?
博士: 中空型マイクロニードルは、マイクロというくらいじゃから、極小さい、そして極めて細い針なんじゃ。その小さくて細い針の真ん中に穴を開けて、中空にしてある針のことじゃな。真ん中が中空になっておるから、普通の注射針と同じように穴を通して薬液を体内に投与できるのが特徴なんじゃが、針が極端に細くて短いので、痛みを感じることがほとんどないんじゃよ。
助手: それは驚きの技術のようですね。よっぽど注射が嫌いな人が作ったんでしょうか…。
博士: ほっほっほ。実はこの針を開発したシンクランドという会社に糖尿病を患っていた方がいたんじゃ。その方が毎日インスリン注射を打つのを見て、社長である宮地さんが「なんとかこの痛みや恐怖から解放してあげたい」という思いから、生分解性ポリマーを使って極小の針を作り、その小さな針に光渦レーザーで穴を空け、痛くない注射針を作ることを思いついたんだそうじゃ。
助手: なるほど、それは素晴らしい着想ですね。でも、開発の過程は大変だったんじゃないですか?
博士: ああ、そのようじゃな。当初は資金がそれほど潤沙にないスタートアップ企業だったが、NEDOのプロジェクトに採択されたことで、開発の支援を受けることができたんじゃ。でも目標であった100マイクロメートルの針を作るのにはかなり試行錯誤が必要だったそうじゃがな。
助手: 開発には多くの努力が必要だったんですね。それで、中空型マイクロニードルの開発には成功したんですか?
博士: ああ、成功した。しかし、医療用途で使うには針をもっと長くする必要があってな。現在はさらに長い針の開発を行っている段階なんじゃ。それでも、とりあえず、現段階で実用化できている技術を使って、美容向けの製品に応用して発売したんじゃよ。
助手: それで医療用の痛くない注射針は実用化できそうなんですか?
博士: もう少しだけ時間がかかりそうということじゃな。医療用途の製品を作るには承認を得るのも難しくてな、2026年ごろまでに臨床試験に入れればいいかなという段階だそうじゃ。
助手: なるほど、一歩一歩着実に前に進んでいるようですね。痛くない注射針が実現すれば、病院通いの子供たちにも朗報になりそうです。もちろん、私にも(笑)。
博士: そうじゃな。いつかは医療を受ける子供たちが泣かずに済む世の中が来てほしいもんじゃ。このドキュメントからも、きっとそんな未来に向けて開発に携わっている技術者たちの熱意が伝わってくるじゃろう。ぜひ一度読んでみるといいと思うぞ。
これまでの実用化事例もまとめられた冊子も用意されておるぞ
博士: 実はの、助手くん。この「NEDO実用化ドキュメント」は、毎年冊子も用意されておるんじゃ。この冊子には、今回紹介した新しく追加された実用化事例の紹介だけでなく、過去の実用化事例がカテゴリーごとにまとめられたインデックスも付いておるので、NEDOがこれまでどういった事業をサポートしてきたかが一目瞭然に分かるというシロモノなんじゃ。PDF形式で配布されておるので、手元に1冊ダウンロードしておくとよいと思うぞ。
助手: へー、これはいいですね。このインデックスを参考にして、またWebマガジン上の気になるドキュメントを探すのもありですね、博士!
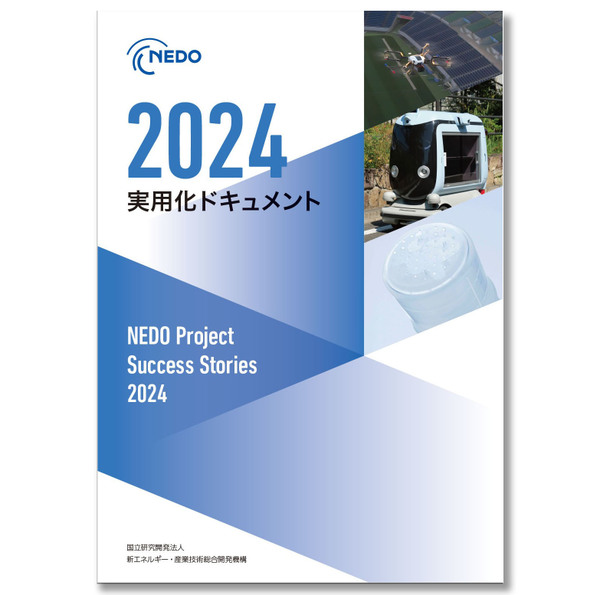
冊子もPDFで配布中!ダウンロードは以下のリンクから
取材協力:NEDO