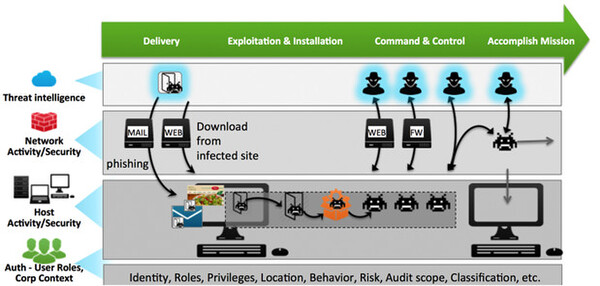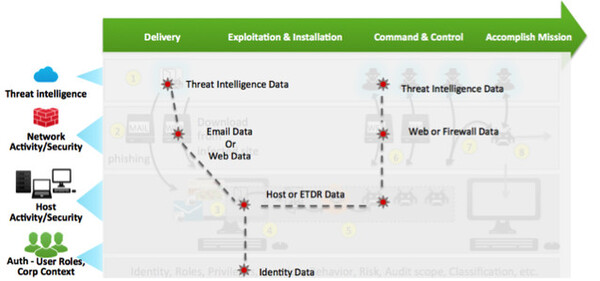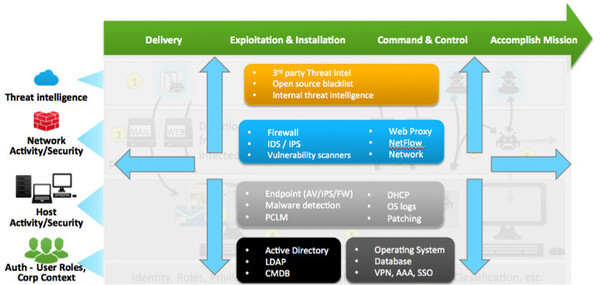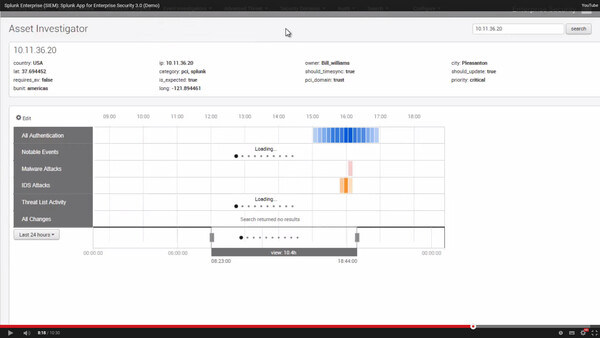同社最高マーケティング責任者、APACチーフセキュリティテクノロジストに聞く
標的型攻撃/APT対策で急伸、Splunkが語る“次世代SIEM”とは
2015年07月08日 14時00分更新
――その“次世代のSIEM”とはどんなものでしょうか。従来のSIEMとどこが違うのですか。
パン氏:従来型のSIEMは、セキュリティログ「だけ」を取り込んでいた。つまり、多数のセキュリティ製品から発せられる大量のアラートから、重要度の高いものを抽出し、見落とさないようにすることが主な目的になっていた。
しかし、長期潜伏型の高度な攻撃であるAPTの場合、セキュリティログには何の痕跡も残さないことが多い。APTに対抗するためには、それ以外の一般的なログ、たとえばEメールやWebアクセス、DNS、顧客が自社開発したアプリケーションなどのログも合わせて取り込み、データを分析していく必要がある。具体的には、脅威インテリジェンス/ネットワーク/アプリケーション/エンドポイントという、4階層のデータが必要になる。
一般的なAPTは、1:組織への侵入、2:組織内での感染拡大、3:外部からの攻撃指示、4:攻撃(機密情報窃取など)の実行といった流れで実行される(左図)。セキュリティログだけでなく、EメールやWebアクセス、エンドポイントなどのログも合わせて分析しないと、攻撃の全体像は見えてこない(右図)
また、一見正常に見えるログでも、ビッグデータとマシンラーニング(機械学習)の活用によって「異常」が見えてくることがある。これにサードパーティからの脅威インテリジェンス情報も組み合わせることで、潜伏する脅威も発見できるわけだ。
マシンラーニングを活用、多様なログから「異変」を見つける
――マシンラーニングの技術は、Splunkの中で具体的にどう活用されているのですか。
パン氏:マシンラーニングを活用することで、あらゆるデータにおいて「アノマリー(不正値)」の検出が容易になる。
たとえばSIEMが、社内PCからWebへのアクセスログをチェックしているとしよう。通常時のアクセス先URLの長さは1000文字未満だが、あるとき急に9000文字に伸びる。SIEMはこの異常を検知して、アラートを出す。実は、マルウェアに感染したPCから、ふつうのWebアクセスに見せかけて重要なデータが送信されていたというわけだ。
ここで、マシンラーニング技術を備えていない旧来のSIEMならば、あらかじめ設定された「しきい値」を基準に異常を判断することになる。しかし、それはとても難しい。なぜなら、個々の顧客環境における「通常時の値」をベンダーは知らないからだ。顧客の管理者自身でしきい値を設定するとしても、膨大な種類のデータ一つひとつに対して「正常な値」を決めていくのは難しく、大きな手間がかかる。
一方、Splunkでは、平常時に取り込まれた大量のデータをマシンラーニングで解析し、最大/最小値や平均値、標準偏差などを自動的に“学習”する。これにより、顧客が独自開発したアプリケーションのログなど、どんなデータであっても「正常な値」を解析し、何らかの異変の発生を容易に検出できるわけだ。
――Splunkのセキュリティソリューションを導入している海外の企業や組織の事例を教えてください。
パン氏:Splunk App for Enterprise Securityの顧客は、グローバルでおよそ4000社/組織いる。その多くが、セキュリティベンダーの従来型製品からSplunkへと乗り換えた顧客だ。
たとえば株式市場のNASDAQ、金融機関のBank of AmericaなどがSplunkのセキュリティソリューションを採用している。また、ハニーネットやボットネットの研究のために、SymantecやSophosといったセキュリティベンダーもSplunkを活用している。サムスンも、Splunkを使ってグローバルセキュリティのモニタリングを行っている。
ソマー氏:導入の目的はAPT対策だけではない。オンラインショップなどのサイトで、違法行為や不正行為を検出するためにSplunkを採用されているケースもある。たとえばオンラインバンキングのサイトで、1つのIPアドレスから何百何千もの口座へのアクセスがあれば、それをアカウント乗っ取りとして自動的に検出できる。
ほぼすべての主要セキュリティベンダー製品と連携できるSplunkは、セキュリティシステムの“頭脳”として動作する。さまざまなセキュリティ製品からログデータを取得し、そうした製品に高度なインテリジェンスを与えるというわけだ。