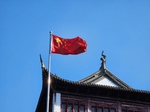日本と英国の両政府が、「日英デジタル・パートナーシップ」の立ち上げを決めた。
2022年12月7日に両政府が会合を開き、合意文書に署名した。
日英両国がデジタル分野で協力の深化を目指す枠組みは、3年ほど前から動きがあったが、今回は「大臣級」のパートナーシップであることがポイントのようだ。
このパートナーシップに基づき、定期的に「政務級」の会合を開くという。
デジタル分野で両国が協力を深めることで、何を目指すのだろうか。
協力は「政治」のレベルに格上げ
今回のパートナーシップでは、日本側は総務省、経済産業省、デジタル庁の各大臣、英国側はデジタル・文化・メディア・スポーツ省の大臣が合意文書に署名している。
まず、「政務級の会合」という言葉だが、日本側としては今後、この3省庁の大臣、副大臣、政務官がパートナーシップの会合に出席することを指す。
大臣、副大臣、政務官は「政務三役」とも呼ばれ、一部例外はあるが、国会議員の中から任命される。この立場にある人たちが参加するから「政務級」と呼ばれるのだろう。
2022年5月には、両国がパートナシップの前身に当たる「日英デジタル・グループ」を立ち上げている。
「グループ」の段階では、3省庁の局長が出席する会合を開いていた。
今回、グループからパートナーシップに名称を変え、実務を担う省庁の「事務」レベルから、重要な意思決定を担う「政治」のレベルに引き上げることで、より踏み込んだ議論を進めていく狙いが読み取れる。
「価値の共有」を重視
今回の合意文書は計10ページで、かなり幅広い分野の協力に言及しているが、パートナーシップが目指すものとしては以下の記述が重要だろう。
「日英関係省庁は、言論の自由、民主主義及び法の支配を含む基本的価値を共有する。日英関係省庁は、技術の進歩の最前線に立ち続けることを相互に支援し、そのような価値に合致する世界的な規範及び基準の確保に貢献することができる」
「デジタル分野におけるオープンで民主的な価値を保護し擁護する必要性を強調してきた」
ロシアや中国などで国家によるインターネットの囲い込みや言論統制が強まるいま、言論の自由、民主主義など共通の価値をベースに両国がデジタル分野での協力を進めていくことには、重い意味がある。
データの越境移転に「実用的な解決策」を仲介
パートナーシップの「中核的な目的」としては、たとえば以下のような項目が挙げられている。
- 日英関係省庁の市民、ビジネス及び経済により良い結果をもたらすために、政策に関する知識、専門知識及び資源を共有すること。
- データの越境移転のような世界的なデジタルの主要課題に対する実用的な解決策を共同で仲介すること。
- 例えば英国及び日本のビジネスを促進するための規制の連携及び相互運用性を奨励するなど、日英の経済間の技術貿易及び投資のためのより強固な基盤を創出すること。
2番目の項目に出てくる「データ越境移転」については、たとえば野村證券のウェブサイトは、以下のように定義している。
「越境移転とは、個人データを外国の第三者が利用できる状態に置くことをいいます」
2021年には、LINEのユーザーの個人情報が業務委託先の中国の企業からアクセスできる状態だったことが明らかになり、問題化した。
データが国境を越えて行き交い、IT企業の業務の委託先が世界中に広がる中、日英両国がこうした問題に対して、協力して解決を図っていくという。
3番目の項目に関しては、デジタル分野における日英間の貿易・投資事例はすぐには思いつかないが、調べてみると大きな事例があった。
2016年にソフトバンクが、半導体設計大手ARMを買収している。ARMは英国に本社を置く企業だ。
日英の巻き返しにつながるか

この連載の記事
- 第376回 「情報は力です」米政府が“検閲回避ポータル”構想、EU規制との対立激化へ
- 第375回 「サポート切れルーターはすべて廃棄を」米CISAが異例の命令、その深刻な理由とは
- 第374回 ホワイトカラー、AIでいよいよ不要に? テック株暴落の裏にAnthropic
- 第373回 iPhone値上げは不可避か メモリ価格が大幅上昇、アップルCEOも言及
- 第372回 スペイン首相も標的に──最恐スパイウェア「ペガサス」事件、捜査打ち切りで残る深い謎
- 第371回 アメリカと台湾が半導体めぐり新たな通商合意 台湾なしでは立っていられないアメリカ
- 第370回 レアアース、中国と険悪なら海底から取ってくればいいじゃない
- 第369回 大手銀行vs.新興Wise SWIFTが仕掛ける“少額送金の逆襲”
- 第368回 ITの中心地サンフランシスコで大停電、ロボタクシーが路上で立ち往生
- 第367回 日本でも怖いTikTokの“アルゴリズム” 米政府はなぜ米国事業切り離しにこだわったのか
- この連載の一覧へ