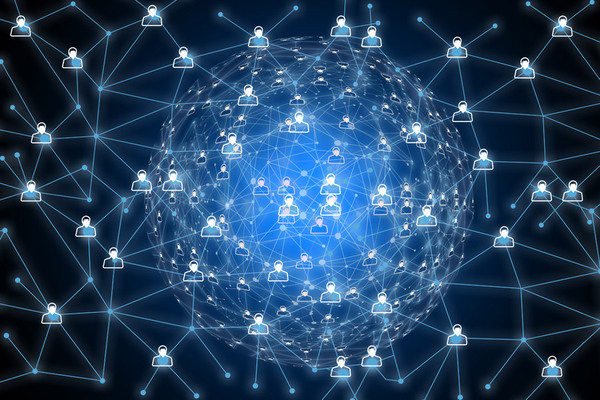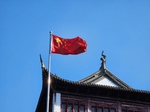電気通信事業法の改正をめぐり、激しい議論が起きそうだ。
同法は、携帯電話や固定電話など通信に関わる事業について詳しい規定を設けた法律だ。
総務省が、サイバーセキュリティ対策やデータの取り扱いについて、規制強化を検討しているが、その方向性に対して新経済連盟が2021年12月17日、「懸念」を表明した。
通信は、個人や企業間の情報のやり取り、買い物、行政手続など、あらゆる分野に浸透し、高度にデジタル化された社会において欠くことのできない重要インフラだ。
そこで、規制強化を進めたい総務省と、はっきりと「懸念」を示す経済団体双方の考えを理解しておきたい。
LINEの個人情報問題がきっかけ
2021年3月、LINEの中国の関連企業のスタッフが、ユーザーの個人情報にアクセスできる状態だったことが発覚。4月、個人情報保護委員会や総務省がLINEに行政指導した。
電気通信事業法に基づき総務省がLINEに対して指導をしたのは、4月26日。翌27日に同省は、電気通信事業者のデータの取り扱いについて検討する「電気通信事業ガバナンス検討会」の開催を発表している。
このため、LINEの個人情報の取り扱いが問題化したことが、規制強化をめぐる議論が本格化した直接のきっかけと考えていいだろう。
総務省が示した3つの対策
『ブリタニカ国際大百科事典』で電気通信事業法の項目をみると、同法は現在のNTTグループとKDDIが独占してきた通信事業を自由化する目的で、1984年に制定された。
もちろん、かつて電話を使った会話は重要だったが、法律が制定された当時から考えると、電気通信の役割の重さや、関係する事業者の数は飛躍的に増えている。
総務省が12月14日に検討会に提出した「電気通信事業ガバナンスの在り方と実施すべき措置」によれば、電気通信事業を取り巻く環境を激変を踏まえ、次のような対策が必要だと整理している。
- 情報の漏えい・不適切な取り扱いへの対策
- 通信サービスの停止への対策
- ユーザーへの情報提供
「情報の漏えい・不適切な取り扱いへの対策」の関連で、最大のポイントは、規制の対象となる事業者の範囲の拡大だろう。
総務省の資料はこの点について、たとえば次のように書いている。
「インターネットの発展に伴い、電気通信回線設備を設置せず、他人の通信を媒介しない電気通信事業を営む者の中でも利用者への影響度が大きい大規模なサービスを提供する場合も出てきているため、特に一定の要件を満たす場合に限り、規律の対象とすることを検討してはどうか」
「一定の要件を満たす場合に限り」としてはいるものの、かなり規制の対象が広範囲に拡大される印象を受ける記述だ。

この連載の記事
- 第374回 ホワイトカラー、AIでいよいよ不要に? テック株暴落の裏にAnthropic
- 第373回 iPhone値上げは不可避か メモリ価格が大幅上昇、アップルCEOも言及
- 第372回 スペイン首相も標的に──最恐スパイウェア「ペガサス」事件、捜査打ち切りで残る深い謎
- 第371回 アメリカと台湾が半導体めぐり新たな通商合意 台湾なしでは立っていられないアメリカ
- 第370回 レアアース、中国と険悪なら海底から取ってくればいいじゃない
- 第369回 大手銀行vs.新興Wise SWIFTが仕掛ける“少額送金の逆襲”
- 第368回 ITの中心地サンフランシスコで大停電、ロボタクシーが路上で立ち往生
- 第367回 日本でも怖いTikTokの“アルゴリズム” 米政府はなぜ米国事業切り離しにこだわったのか
- 第366回 メモリ供給は“危機的” PCもゲーム機も高値続きか
- 第365回 33兆円シリア復興マネー、VISAとマスターが争奪戦
- この連載の一覧へ