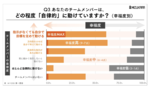国内のAIインフラに対する海外ベンダーの投資が過熱している。MicrosoftやAWS、Google、Oracleといったメガクラウドベンダーは、AI需要の拡大に対応すべく、国内データセンターの拡張を推進。海外のデータセンター事業者も国内投資を続けている状況だ。
このような状況の中、KDDIとさくらインターネット、ハイレゾの国内3社は、2025年4月11日、「GPU需要への対応に向けた共同検討」に関する基本合意書を締結したと発表した。国内組織が安定かつ柔軟にGPUを利用可能な体制構築を、3社で模索していく。
KDDIのビジネス事業本部 プロダクト本部 AIビジネス推進部 部長である中島康人氏は、「GPU需要と顧客ニーズに柔軟に対応できる体制を構築していく。生成AI開発を支援することで、日本の産業力強化に貢献していきたい」と説明する。
KDDI・さくらインターネット・ハイレゾが連携する「3つのメリット」
GPU市場は年々拡大。調査レポートなどからは、その需要は今後も増え続けるとみられている。さらには、大学・研究機関では「大規模な基盤モデルを高速に開発したい」、スタートアップでは「コストを押さえたい」といった形で、組織の属性や用途によって、柔軟なGPU提供が求められている状況だ。
このような背景を受け、KDDIとさくらインターネット、ハイレゾの3社は、各社保有のGPUを相互利用していくための検討を始める。もともと3社は、経済産業省による「特定重要物資クラウドプログラムの供給確保計画」の認定を受けており、国の支援を受けつつ、国内のスタートアップやAI開発企業などに対して計算資源を提供してきた。
現在、KDDIは、AI時代のビジネスプラットフォーム「WAKONX(ワコンクロス)」を、さくらインターネットは、生成AI向けクラウドサービス「高火力」を、ハイレゾはGPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を展開中だ。3社は、GPUの相互利用に加えて、各社のプラットフォームを相互接続することで、AI開発におけるGPU利用の選択肢を広げていく。
KDDIの中島氏は、今回の協業でユーザーが得られるメリットを3つ挙げる。ひとつ目は、「調達窓口が広がる」ことだ。例えば、KDDIの窓口を通じて、さくらインターネットのGPUリソースを利用することも可能になる。
2つ目は、「GPUのライナップが拡充される」こと。新たなチップが毎年登場するため、GPUの提供側も、単独で取り揃えるのが難しい状況になっている。3社が手を組むことで、用途に応じた最適なGPUを最適なコストで提供することができる。3つ目は、「GPUの安定提供」だ。3社が融通し合うなどして、需要の振れ幅にも対応可能な安定した体制を整備していく。
3社多様なGPUクラウドサービスを相互接続
ここからは、相互連携が見込まれる各社のGPUクラウドサービスやAIインフラにおける取り組みを紹介する。
まず、KDDIは、業界別にAIを活用したビジネスプラットフォームを提供する「WAKONX(ワコンクロス)」を通じて、マルチLLMやGPUサービスを展開している。2025年度内には、「NVIDIA GB200 NVL72」などの最新GPUを導入する「大阪堺データセンター」の稼働を開始して、幅広いユースケースに応えるAIサービスやGPUリソースを提供予定だ。
また、日本語に特化したLLMを提供するELYZAと資本業務提携を結んでおり、同社の研究開発力と、KDDIの計算基盤やネットワーク資源などのアセットを組み合わせて、生成AIの社会実装を推進してきた。「KDDI ∞ Labo」や「KDDI Open Innovation Fund」といったプログラムでは、スタートアップ企業に計算基盤を提供。実際に、自動運転や自動操縦向けのAIモデルを開発する企業などを支援してきたという。
さくらインターネットでは、GPUクラウドサービスとして「高火力」シリーズを展開している。ワークロードの規模や利用期間に合わせたラインアップを揃え、現在は、ベアメタル型でGPUサーバーを丸ごと提供する「高火力 PHY(ファイ)」、コンテナ型でDockerイメージの実行ができる「高火力 DOK(ドック)」を提供。2025年春には、時間単位での利用が可能なVM型の「高火力 VRT(バート)」も追加予定だ。
さくらインターネットの執行役員である霜田純氏は、高火力シリーズについて、「AIブームを一過性にしないことに加えて、貿易赤字が拡大しないよう、国産クラウド事業者として国内市場の成長を主眼に置いている」と説明。今後は、サービスの更なる増強に向け、最新GPUやデータセンター拡張など、1000億円の投資を計画しているところだ。
さらに、GPUクラウドインフラだけではなく、AIアプリケーションと基盤モデル、高火力をつなぐ生成AIプラットフォームサービスも開発中だ。半導体の領域では、Preferred NetworksとRapidusの3社で協業、グリーン社会に貢献する国産AIインフラの提供に向けた取り組みを進めている。
ハイレゾは、石川県の志賀町や香川県の高松市や綾川町、佐賀県の玄海町など地方拠点でのGPU専用データセンターを運営する。ハイレゾの取締役である小堀敦史氏は、自社について、「国で掲げる計算力の整備をしつつ、地方経済の問題を同時に解決していくベンチャー企業」と説明する。
GPUクラウドサービスとしては、コストパフォーマンスを売りとする「GPUSOROBN」を提供。画像生成・機械学習に最適な「高速コンピューティング」やNVIDIA H200搭載の「AIスパコンクラウド」、BtoC向けの画像生成用途の「PICSOROBAN」など、幅広いメニューを取り揃えている。
コストパフォーマンスは、「世界と比べても最安値級の価格を追求している」(小堀氏)といい、同社の試算では、GPUSOROBNでNVDIA H200搭載のインスタンスは、ハイパースケーラーのNVDIA H100よりも、GPUメモリが1.7倍な上に“70%安い”価格になるという。
世界を見据えてGPUインフラ活用の裾野を広げる
本連携のグローバルベンダーとの差別化について、さくらインターネットの霜田氏は、「直接的に競合することもあるが、色々なGPUインフラの使い方を提示して、その裾野を広げる意味でのアライアンスでもある。日本企業がGPUインフラを使うことが増え、ユースケースが広がっていくことを期待している」と語る。ハイレゾの小堀氏は、「三者三様のサービスを上手く組み合わせることで、世界にないサービスを生み出せる可能性がある。また、日本企業に使いやすいサービスは、やはり日本のサービスであることが理想だと考える。デジタル赤字の問題もあるため、日本企業の成長に貢献できるような取り組みにしたい」と付け加えた。
また、小堀氏は、「(計算資源を整備した)その次は、日本企業のAIに対する意識を改革して、レベルアップをしていく必要がある。1社では時間がかかるため、3社で協力し合い、可能であれば国の支援も受けながら、日本全体のAIインフラの提供と、その利用促進を同時進行で進めないと世界には勝てない」と強調した。