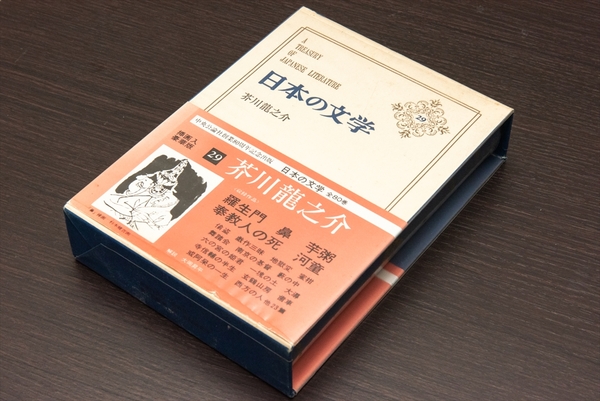芥川龍之介の短編小説『蜘蛛の糸』は、生前に悪事を働いて地獄に落ちた男・犍陀多(カンダタ)に差し伸べられる救いと、その機会をふいにしてしまう彼の愚行を描いた短編小説だ。
ある日、極楽の蓮池から下に見える地獄を眺めていたお釈迦さま(ブッダ)は、罪人である犍陀多が生前にたったひとつだけ善行をはたらいたことを思い出し、1本の蜘蛛の糸を地獄まで垂らして彼を引き上げようと試みる。糸にすがりつき、何万里とある天上までの道をのぼる犍陀多はそのまま極楽へ入るかと思われたが、下から同じように蜘蛛の糸を手繰ってくる大量の罪人たちを見つけ、彼らを怒鳴りつけてしまう。
そこで犍陀多は大きな声を出して、「こら、罪人ども。この蜘蛛の糸は己のものだぞ。お前たちは一体誰に尋いて、のぼって来た。下りろ。下りろ。」とわめきました。
そのとたんでございます。今までなんともなかった蜘蛛の糸が、急に犍陀多のぶら下がっているところから、ぷつりと音を立てて断れました。ですから、犍陀多もたまりません。あっという間もなく風を切って、独楽のようにくるくるまわりながら、見る見るうちに暗の底へ、まっさかさまに落ちてしまいました。
(芥川龍之介、1964、『日本の文学 29 芥川龍之介』、中央公論社)
犍陀多が再び地獄へと落ちていくさまを目の当たりにしたお釈迦さまは、彼をもう一度助けようとはせず、悲しそうな顔をしてぶらぶらと歩き始め、物語は幕を閉じる。文中では、犍陀多がその無慈悲な心により相応の罰を受けたことが示唆されており、“自分のことばかりを考えてはいけない”というシンプルな教訓が受け取りやすい構成もあって、本作は現在でも優れた児童向け文学作品として巷間に親しまれている。
あえて細かいことを言えば、芥川の『蜘蛛の糸』における仏教的世界観には不可思議な点が多く、あまり宗教的な厳密さがあるとは言えないようだ。しかし、一方で本作は、初期仏教や大乗仏教において最も根源的に克服が困難とされる「三毒」、すなわち「貪・瞋・癡(とん・じん・ち)」の「貪(とん)」の煩悩を鋭く描くことに成功している。
「貪」は、簡単に言えば貪欲さのことだ。人よりも幸福になりたい、人よりも金持ちになりたいといった欲深さは、いずれ他人を蹴落とし害することに繋がる上、欲ばかりを突き詰めていけばきりがなく、いつまでも満たされないままに苦み続けることになる。貪欲さが特に深刻とされているのは、最終的には「自損損他(じそんそんた。自分も他人も不幸にすること)」に直結するものであるからだろう。
仏教において、こうした欲の本性は「我利我利(がりがり)」と教えられる。読んで字のごとく、自らの利益のみを追求し、他人をかえりみないという意味だ。そして我利我利の心は、自分に余裕がなくなった時、追い詰められた時にこそ如実に表面に現われてくるという。『蜘蛛の糸』における犍陀多の行動は、まさに我利我利そのものというわけだ。
このような人間を指して「我利我利亡者(がりがりもうじゃ)」と罵ったりもするわけだが、しかし、我利我利の本性はすべての人間にとって他人事ではなく、自分自身でも引き受けなければならない問題と言える。なぜなら仏教において、人はみな108つの煩悩からなる「煩悩具足の凡夫」であるからだ。煩悩を持たない人間は存在しないし、煩悩を消すこともまた不可能なのである。
そのような教えに従えば、我々人間にできることはただ自分の煩悩を認め、戒めながら生活するのみ、ということになる。先ほどの自損損他ではなく、自分が得たものを他人にも還元し、決して自らの利益のみを追い求めない「自利利他(じりりた)」を常に心がけることこそ、真に幸福へ近づく道というのが大乗仏教の説くところだ。筆者は敬虔な仏教徒ではまったくないが、こうした考え方には大いに感じ入るところがある。それと同時に思うのは、その実践の難しさだ。特に、最近はその難しさを強く感じている。
ここ数ヵ月は先の見えない社会的な混乱が続き、人間の根源的な欲深さを身近に意識する機会が増えているように思う。1000年以上も昔に生きた仏教者が、また芥川が喝破したように、やはり切羽詰まった時には人間の本性、我利我利の心が露骨に現われてくるものらしい。こうした欲深い人を傍目に見て批判するのはたやすいが、自らもまた我利我利の心を持つことを顧みて、自分を律していかねばならないと切に思う。
仏教徒であろうとなかろうと、改めてこのような教えに耳を傾けてみることは、決して無意味なことではないはずだ。
前置きが長くなってしまったが、ブッダマシーンの話に移ろう。