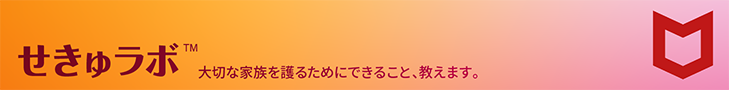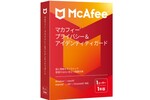フィッシング詐欺=偽サイトに誘導して個人情報を盗み取る
第1回 日本のスマホ利用者を狙う悪意の中身を知ろう
2018年10月29日 09時00分更新
最近、スマホ利用者を狙った「フィッシング詐欺」が増えています。フィッシング詐欺とは有名サイトなどを装った電子メールを送り、個人情報を盗む行為のこと。ネットの利用者を騙して被害者を「釣り上げる」ことからその名が付きました。
最近話題の「フィッシング詐欺」ってなんだろう?
今年に入ってフィッシング詐欺の被害が増えています。先日も、宅配便の再配達を装ったSMSメッセージ(ショートメッセージ)を使って公式そっくりの偽サイトに誘導し、スマートフォンを乗っ取るアプリをインストールさせるという事件が大きな話題となりました。このほかにも、巧みにインターネット利用者を騙して個人情報などを盗み取ろうとする事件は後を絶ちません。そして最近は、特にスマホ利用者を狙う手口が目立っています。
そこで今回から数回にわたって「フィッシング詐欺の見分け方と対策」について易しく解説します。まずは、そもそも「フィッシング詐欺とは何か?」から始めましょう。
偽サイトに誘導して個人情報を盗み取り、最終的に金銭を得る
セキュリティ専門会社「マカフィー」の説明によれば、フィッシング詐欺とは「インターネットの世界で行われる詐欺の一種で、正規のサービスなどのふりをしたメールやショートメッセージで偽のWebサイト(フィッシングサイト)に誘導させ、クレジットカード情報やログイン情報(IDとパスワードなど)を盗み出す行為」を指します。
悪意ある人たちの目的は金銭です。フィッシング詐欺の場合は、騙して手に入れたネット利用者の個人情報を悪用することで金銭を得ようとします。たとえばインターネットバンキングのアカウント情報を入手して被害者の口座から不正に送金できますし、SNSなどのアカウント情報を入手したならば、アカウントを乗っ取って被害者に成りすまし、別の詐欺に使う、といった具合です。また、個人情報自体を売却して金銭を得ることもできるのです。
以上、フィッシング詐欺とは何かについて解説しました。転ばぬ先の杖として、最低限の知識は持っておきたいものです。次回はフィッシング詐欺の代表的な手口についてお伝えします。
なお、フィッシング詐欺は海外で生まれ、広がったものです。ネット利用者を騙して被害者を「釣り上げる」ことから名付けられました。とはいえ、釣りを指す「fishing」ではなく「phishing」と英語圏では表記されます。

この連載の記事
-
第89回
sponsored
Wi-Fiは「鍵マーク」付を選んで使いましょう! 安全に通信できます -
第88回
sponsored
スマホに延々と『ウイルス発見!』の通知が届き続ける!? -
第87回
sponsored
きっぷを買おうと思ったら個人情報を盗まれた!? -
第86回
デジタル
「水道料金を割引」「滞納で給水停止」……水道局を名乗る偽者に要注意 -
第85回
デジタル
スマホの「システムアップデート」してますか? アプリのアップデートではありません! -
第84回
デジタル
1年で偽Webサイトによる詐欺が90万件以上! フィッシング詐欺の現状を知っておこう -
第83回
デジタル
身代金要求ウイルス「ランサムウェア」があなたの会社を脅す -
第82回
デジタル
拾ったUSBメモリーに注意。お宝かとおもいきや、じつはウイルス入り!? -
第81回
デジタル
連休明けにサイバー攻撃を受けやすい理由 -
第80回
デジタル
偽の宅配便「不在連絡」が!? そのSMSは偽物です! -
第79回
デジタル
あの人気イベントの専用アプリを発見!? じつはニセモノかもしれません - この連載の一覧へ