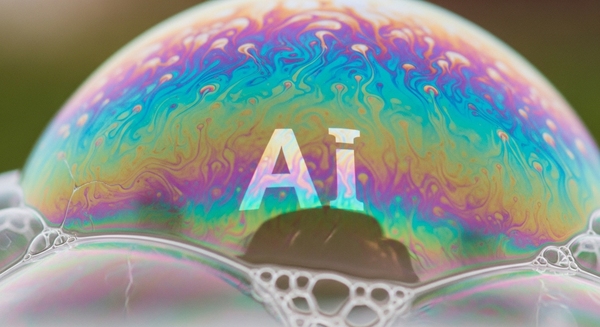2025年11月7日、半導体大手のNVIDIAの株価が一日に4.2%下落。時価総額は数兆円規模が一瞬にして消え、株式市場全体に衝撃が走った。多くの投資家や経営者が「AIバブルは弾けるのか」と不安を募らせている。実際、この1年を振り返ってみると、AIをめぐる熱狂と緊張感は目を見張るものがある。
AIへの期待でバブルがふくらみ続けた1年間
2024年11月、NVIDIAの株価は過去最高値の148ドルを記録し、「Blackwell」チップへの期待でAI需要が爆発した。OpenAI「GPT-5」への期待感もAI投資を急増させた。S&P500の株価上昇の75%をAI関連銘柄が牽引するほどだった。
しかし2025年1月、中国の新興AI企業DeepSeekが低コストで高性能なAIモデルを発表すると、NVIDIAの株価は一時17%も急落し、時価総額が5900億ドル(約91兆円)も吹き飛んだ。最先端のGPUを大量に使わなくてもトップ級のAIが作れるという事実は、市場に「AIは本当に高価なままか」という疑問を残した。
4月には米中貿易摩擦の影響で55億ドルの損失を計上し、NVIDIAの株価はさらに落ち込んだ。5月、著名ヘッジファンドのエリオット・マネジメントが「AIは過大評価されている」と警告を発し、同時期にNVIDIAやIntelの株も下落した。
7月、NVIDIAの時価総額はついに4兆ドルに到達。トランプ政権が特定の州に900億ドルのAI投資を表明し、テスラやウェイモの自動運転ビジネスが「物理世界のAI」への期待を高めた。しかし8月、MITの調査で、企業が投じた300億~400億ドルのAI投資のうち95%が利益を生んでいないと判明し、幻滅感が高まった。
AI銘柄の“過大評価”にたびたび警鐘
9月にはNVIDIAがOpenAIに最大1000億ドル(約15兆円)を投資すると発表したが、OpenAIがOracleにデータセンターの構築を依頼し、OracleがNVIDIAのGPUを購入し、NVIDIAがOracleからGPU販売代金を受け取る「循環取引」だと批判された。10月には、NVIDIAが史上初の5兆ドル企業となる一方、イングランド銀行が「AI株の過大評価が世界経済に悪影響を及ぼす」と警鐘を鳴らした。
そして11月、NVIDIAの株価が再び急落した。中国の安価なAI技術が再評価されたほか、企業がAI予算を削減し始めたとの観測などが重なった。OpenAIのCFOが資金調達を可能にする保証を政府が補強する可能性に言及したことも動揺を広げた。「世紀の空売り」で知られるマイケル・バーリ氏率いるヘッジファンドがNVIDIAとPalantirに弱気ポジションを開示したことも懸念を煽った。
NVIDIAジェンスン・フアンCEOの発言も重い。フィナンシャル・タイムズは11月、「AI競争で中国が勝つ」という発言を報じた。ロイターも同様に伝え、中国の巨大な開発者基盤や、政策・コスト面の優位に触れたとする。NVIDIAは「中国が勝つと言ったのではない。中国は米国の“ナノ秒差”だ。米国が先行し世界の開発者を獲得すべきだ」と釈明しているが、報道は投資家たちを動揺させた。
振り返れば、AIをめぐる興奮と不安が交互に訪れ、市場を乱高下させてきたことがわかる。最初は技術革新と巨額投資が市場を押し上げたが、次第に「本当にAIで儲かるのか?」「中国に追いつかれるのでは?」といった疑念が広がり、11月の株価急落で不安がピークに達した。市場の不安や緊張を数値化した“恐怖指数”は、11月10日時点で「極端な恐怖(Extreme Fear)」と最高値を差している。
AIバブル崩壊でも、“AI市場”は誕生か
本当にバブルは崩壊するのか。「修正は避けられない」と指摘する専門家はいる。NVIDIAの株価収益倍率が40倍を超え、OpenAIが年間135億ドルの赤字を抱える状況は、2000年のドットコム・バブルを思わせる。企業のAI投資はほとんどが成果を出しておらず、電力不足、規制強化、地政学リスクも重しとなる。
もしバブルが弾ければ、影響は大きい。AIスタートアップの資金が枯渇し、大規模なレイオフが起きるだろう。株式市場がリセッションに陥るリスクもある。2028年までにAIデータセンターに1.5兆ドルの負債が予測され、NASDAQ時価総額から最大40兆ドル規模が失われる可能性があるとの仮説もある。
ただし、完全な崩壊にはならないとの見方もある。AIは既に医療や科学の研究に使われ、成果を出しはじめている。NVIDIAの新チップ出荷や生産性向上への期待も残る。バブル崩壊が起きたとしても、それは「過熱の調整」で、数年後には成熟したAI市場が誕生するかもしれない。長期的には資本が価値を生む分野、たとえば医療診断や工場の自動化に流れ、イノベーションが加速するはずだ。
AIの未来は不確実だが、経営者や投資家は今、不透明な“泡”ではなく、現実を見るときが来ているのかもしれない。