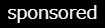「富士通開発陣が明かす“匠の技”――「ARROWS Tab Wi-Fi」を探る(前編)」に引き続き、「ARROWS Tab Wi-Fi」開発者インタビューの後編をお届けする。前編では、「日本人技術者としての『匠』の精神」をもって開発に取り組んだとのコメントが印象的だったが、ARROWS Tab Wi-Fiにはスペック表だけでは語れないポイントがまだまだ隠されているという。ARROWS Tab Wi-Fi開発の裏側と、富士通が描く今後のタブレット戦略について話を聞いた。
――タブレット端末の画面サイズは7〜10型程度が主流で、それより小さい、あるいは大きい製品も一部出てきています。ARROWS Tab Wi-Fiにおいて、“10.1型”というサイズを選択した理由を教えていただけますか?
吉澤: 今回のARROWS Tab Wi-Fiは主に家庭で使っていただきたい、なおかつ迫力のある映像を楽しんでいただきたいという製品コンセプトでしたので、(外出先への携帯に適した小さい画面ではなく)10.1型を選択しました。
同時に、ディスプレーサイズをこれ以上大きくした場合、消費電力が上がり、バッテリーもより大型のものが必要となるため、家の中で手軽に移動できるということも考えて、10型クラスが最適だろうという結論に達しました。
本郷: 映像を再生するときに、音声もできるだけ良い音質で楽しめるように、スピーカーもこの筐体に入れられる最大のものを採用しています。
とはいえ、このサイズのスピーカーの音には限界があるので、ARROWS Tab Wi-Fi筐体の空間をエンクロージャー(スピーカーを取り付ける筐体部分を指す用語)とすることで、できるだけ効率良く音を出せる構造を当初から目指し、何種類もの設計を試しています。
吉澤: 例えば、携帯電話に使われているスピーカーそのものは非常に小さなサイズで、単体で鳴らすとすごく貧弱な音しか出てきません。しかし、それを携帯電話の筐体の中に入れることによって、大きく迫力ある音が出せるようにしています。搭載しているスピーカーサイズ以上の音を出すという技術は、富士通が携帯電話の開発で蓄積してきたものです。