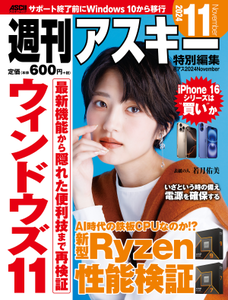住基ネットを拡充して「負の所得税」を
おかげで住基ネットの機能は自治体の事務合理化に限定されたため無用の長物となり、納税者番号がないため定額給付金のような還付にも850億円もの費用がかかる。安倍政権でも社会保障番号が出てきたが、政権が変わると潰れてしまった。今度も住基データとは別に社会保障番号を導入する方向で、それとは別に納税者番号が検討されている。
このように官庁の縦割りでバラバラに国民の個人情報を管理することは、セキュリティの点でもコストの点でも問題がある。年間200億円もかけて管理・警備されている住基データを抜本的に改正し、各官庁の共有データとして社会保障にも納税にも利用するほうが効率的だ。
特に重要なのは、税と社会保障を一体化することだ。欧米では社会保障番号が納税者番号にも使われ、納税や年金の給付情報を一体的に管理し、子供の多い世帯に税額控除を手厚くしたり、課税最低限以下の低所得者に現金を支給する負の所得税(給付金付き税額控除)にも使われている。日本でこういう制度が実施できないのは、背番号がないため事務コストがかかりすぎるからだ。
こういうとき、最大の障害になるのは「プライバシー保護」を主張する人々だ。個人情報保護法のときも、野党がこういう反対運動に迎合して与党案より規制を強化した法案を出し、おかげで厳格な個人情報保護法ができて、「官製不況」が起こってしまった。さすがに今となっては、背番号反対を強硬に主張する人はいなくなったが、役所には住基ネット騒動のトラウマが強いので、個人情報を一元管理することには慎重だ。
しかし、背番号とプライバシーを結びつけるのはナンセンスである。たとえば私の名前をグーグルで検索すると148万件あり、虚実とりまぜてあらゆる個人情報がウェブにさらされている。インターネット時代に、行政情報だけを分散しても意味がない。住基ネットを有効利用し、税負担の公平化を図ることこそ、国民に対する責任だ。
筆者紹介──池田信夫
1953年京都府生まれ。東京大学経済学部を卒業後、NHK入社。1993年退職後。国際大学GLOCOM教授、経済産業研究所上席研究員などを経て、現在は上武大学大学院経営管理研究科教授。学術博士(慶應義塾大学)。著書に 「ハイエク 知識社会の自由主義 」(PHP新書)、「情報技術と組織のアーキテクチャ 」(NTT出版)、「電波利権 」(新潮新書)、「ウェブは資本主義を超える 」(日経BP社)など。自身のブログは「池田信夫blog」。

この連載の記事
-
最終回
トピックス
日本のITはなぜ終わったのか -
第144回
トピックス
電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -
第143回
トピックス
グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -
第142回
トピックス
アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -
第141回
トピックス
ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -
第140回
トピックス
ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -
第139回
トピックス
電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -
第138回
トピックス
原発事故で迷走する政府の情報管理 -
第137回
トピックス
大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -
第136回
トピックス
拝啓 NHK会長様 -
第135回
トピックス
新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ