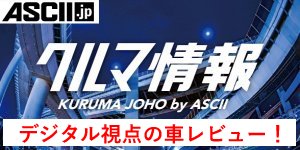●先ずは体力測定から
それでは、用意したAthlon-1.2GHzの限界性能を調べておこう。そうでないとマザーボード本来の性能やマッチングの良いメモリーを探る作業で正しい判断ができない。調査にはCPUの倍率やFSB設定クロックをBIOSから操作できるK7T266 Proを使用した。
チップセットを含めてメモリーが十分安定動作できるFSB設定クロックをセットしておき、CPUの倍率を順次高くして行けば必ずどこかでエラーが出る。そしてそのエラーが出ないところまでFSB設定クロックを下げて正しく動作するクロックを導き出す。こうして得た数値が暫定的な限界クロックと推定できるわけである。なおCPUのコア電圧は標準値で良しとした。また「暫定」とした意味は、CPU温度やコア電圧によってその限界値は変化する可能性が残されているからだ。
●予備テスト~その1~
では、実際に動作させてみよう。当然のことながら最初はデフォルトの設定(FSB設定クロック133MHz、倍率9倍、SDRAM CAS Latency:2.5)で動作確認だ。以降システムが正常に動作するしないは、Superπと次のテストで実施する3DMark 2000及び3DMark 2001を使って大まかな判断基準とした(実用機レベルの判定基準とは話しが別)。
K7T266 ProにAthlonとCPUクーラーを装着、メモリーは無難な選択でMicronチップを実装したCrucial Technology製PC2100 128MBをスロットに押し込んだ。そしてWindows98SEをインストールする。「初モノはチョットねぇ…」と少々疑り深い筆者だが、これまで経験した厄介なトラブルもなく、いたってスムーズなセットアップが進んだ。ドライバーやテスト用のプログラムも整えてSuperπを立ち上げる。計算量は104万桁を指定して計算開始…システムは次々にループをクリアし118秒で計算を完了。どうやら用意したAthlonの初期不良は免れた。
●予備テスト~その2~
次にBIOSセットアップ画面まで戻してFSB設定クロックを120MHzに変更(倍率はそのまま)する。そしてWindowsが起動できたら3DMark 2000と3DMark 2001をベンチモードで走らせてみる。次のCPU限界テストを行う上でFSB設定クロックを133MHzから下げるため、上昇するAGPバスクロックにビデオカードが正しく動作するか予めテストを実施しておくのだ(BIOSセットアップにてCPU FSB CLKを133から100に変更しオーバークロックすると1/3PCIクロックとなり結果的にFSB設定クロック120MHzでAGPクロックは先の66.6MHzから80MHzと高くなる)。なお、このクロックで無難に動作するならFSB設定クロックをシフトアップした場合に160MHzまでは理論上大丈夫と言う計算になる。逆に起動困難に陥る場合は、AGPビデオカードかメインメモリーのオーバークロック耐性が疑わしい。
さて、解像度を1024×768、16ビットカラーにセットしたベンチマークテストだがNVIDIA製GeForce2 MXチップ搭載のAGPビデオカードを用いた筆者の環境(PCIスロットには何も装着していない軽装備)では無事に完走できた。なお、先のSuperπも含めて取得できた数値は後の比較対象になる。しかし現段階では、無事に計算できたか?あるいはモニター上に映し出された描画が崩れていないか?と言った観点がより重要である。
●いよいよCPUの限界性能を調査
 |
|---|
| CPUの動作限界クロックを超えてしまったためにとうとうエラーが・・・これ以上のクロックでは正常動作が見込めない。 |
これで下調べは十分だろう。再びBIOSセットアップにて今度は倍率を11倍にセットする(FSB設定クロックは120MHzのまま)。この設定(CPU内部クロック1.32GHz)で動作すれば確実にワンクラス上の性能を得られる。「この程度の耐性は持っていて欲しいなぁ…」と思いつつ筆者の期待に応えてWindowsの起動は無難にこなせた。すぐさまSuperπを先のテストと同じ計算量でスタートさせた。結果は、見事に計算を完了。「よしよし“AVIA”もなかなか好調じゃない? 」。筆者は、調子にのって11.5倍を試してみる。CPUの内部クロックは計算値1.38GHzとなるわけだ。BIOSセットアップをSAVE EXITして再起動は順調に進んだ。WindowsのスタンバイもOKだ。「この調子なら1.4GHzオーバーか?」。ところが世の中そんなに甘くはない。先と同じようにSuperπを立ち上げて計算を開始した瞬間、いきなりエラーが告げられて計算がストップした。実は、テスト当日の室温は、昨日の天気予報でも告げられた通り初夏を思わす好天気に恵まれ温度計が27℃を示している。また、マザーボードのモニターでCPUの温度を観察すると44℃となっている。冬場ならもう少し耐えられた可能性も残るがこれからの季節は気温上昇に向かう訳で「今後を想定した妥当なテスト環境」と考え方を切り替えた。
結局、FSB設定クロックを1MHz下げた119MHzの11.5倍でSuperπの計算が完了できたことから、このAthlonの暫定限界クロックは1368MHzと見きわめられた。念のためにFSB設定クロック138MHz、倍率10倍でも試してみたがSuperπの結果は同じで即刻エラーが表示された。この性能がアタリかハズレかは別にして現在リリースされている最高クロック製品(Athlon-1.33GHz)を超える性能は出せるわけだ。
前述の通り、L1クローズのAthlonならマザーボード次第で倍率操作が可能である。したがってチップセットあるいはメモリーが許す限りの高いFSB設定クロックと倍率の兼ね合いを計算し、CPUの限界以内で巧く動作できれば効率の良いオーバークロックシステムとなる。要は「用意できる設備の範囲で使えるところまで存分に使ってやろう」と考えれば良いのである。