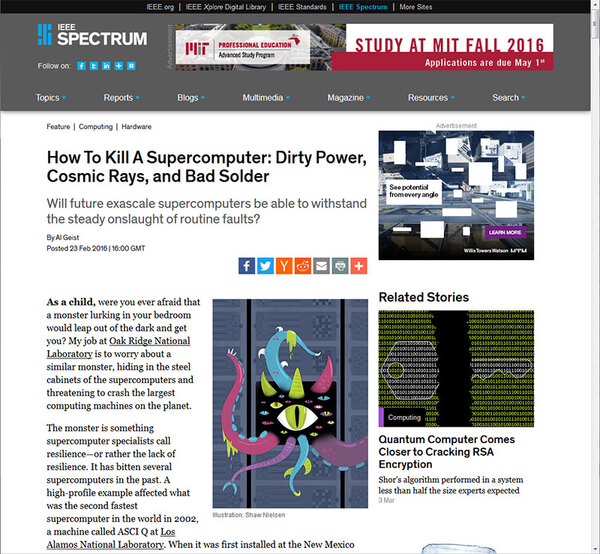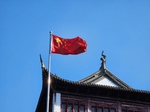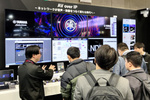今回のスーパーコンピューターの系譜は、CRAY X-MPを手がけたSteve Chen博士のその後をフォローアップしよう。その前に関係ない話題を1つ。
スーパーコンピューターが
エラーを起こす原因は宇宙線!
2月23日、IEEE SPECTRUMに“How To Kill A Supercomputer: Dirty Power, Cosmic Rays, and Bad Solder”という記事があがった。
IEEE SPECTRUMはIEEE(米国電気電子学会)の学会誌で、通常は学会員は無料で読めるのだが、一般人は有償になっている。ところがこの記事は珍しく無償で誰でも読めるようになっており、かつおもしろいので紹介しよう。ちなみに筆者はオークリッジ国立研究所でスーパーコンピューターの面倒を見ている人である。
記事の中身を要約すると以下のとおり。
- ローレンス・リバモア国立研究所のASCI Qは当初連続稼働時間が1時間未満だった
- バージニア工科大のBig Mac(アップルのMac G5を1100台集めたスパコン)はまともに稼動しなかった
- オークリッジ国立研究所のJagureは当初、基板上の電源モジュール不良が原因でネットワーク全体がしばしばダウンして使い物にならなかった
- ローレンス・リバモア国立研究所のBlue Gene/Lは、基板上の配線が理由で1次キャッシュの動作不良に陥った
いずれも直接的な原因は宇宙線である。ASCI QはアドレスバスがECC保護されておらず、ここに宇宙線が当たるとエラーを起こしてクラッシュした。
Big MacはそもそもメモリーがECC保護されていなかったので、システムが立ち上がる前にかならずどれか1台がメモリーエラーを起こし、まともに動作しなかった。
Jagureの場合、基板上の電源モジュールが宇宙線保護の対策を取っておらず、これが理由で突然あるノードが落ちる場合があった。悪いことに、Jagureのネットワークはあるノードがいきなりダウンすることを想定しておらず、これが発生するとネットワークの再構築のために再起動の必要があった。
BlueGene/Lは基板上の配線に宇宙線があたると、それが最終的に1次キャッシュの中身を破壊する(PowerPC 440コアは1次キャッシュのECC保護がされていなかった)結果になった。
解決策はいろいろである。ASCI Qの場合、キャビネット側面に金属パネルを追加したことで、クラッシュするまでの時間を1時間未満から6時間まで延ばすことに成功した。
Jagureの解決策は明記されていないが、おそらくネットワークのルーティングの方式を変更したものと思われる。BlueGene/Lは最終的に1次キャッシュを無効化して解決したが、性能は猛烈に悪化したらしい。
そしてBigMacはシステムを解体し、1100台のMac G5をそれぞればらばらに売却してしまった。バージニア工科大は代わりにECC保護機能の付いたXserve G5 serverを集約したSystem Xを構築している。
細かい話は記事を読んでいただければと思うが、猛烈な量のCPUやメモリーが集約されるスーパーコンピューターでは、宇宙線の影響が本気で無視できないことを示すエピソードである。

この連載の記事
-
第858回
デジタル
CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -
第857回
PC
FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -
第856回
PC
Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -
第855回
PC
配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -
第854回
PC
巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -
第853回
PC
7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -
第852回
PC
Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -
第851回
PC
Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ -
第850回
デジタル
Zen 6+Zen 6c、そしてZen 7へ! EPYCは256コアへ向かう AMD CPUロードマップ -
第849回
PC
d-MatrixのAIプロセッサーCorsairはNVIDIA GB200に匹敵する性能を600Wの消費電力で実現 -
第848回
PC
消えたTofinoの残響 Intel IPU E2200がつなぐイーサネットの未来 - この連載の一覧へ