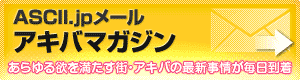ベンチ結果を他の機種と
簡単に比較できる
テストの内容はWindows版と同様だ。つまりGraphicsテストを2回、Physicsテストを1回実行し、それらのfpsを元にスコアが計算される。Andoroid版ではCPUやGPUの温度やfpsをグラフ化する機能がない代わりに、他のデバイスとの比較がWindows版よりも楽に実行できる。現在使っているデバイスよりも高スコアが出るデバイスに乗り換えたい、という場合にはぜひ活用したい。
「Ice Storm」でわかること
では各テストがどんな処理をしているのかを簡単にチェックしていこう。「Ice Storm」がターゲットにしているデバイスに搭載されているGPUは最新ビデオカードのGPUとは異なり、頂点とピクセル(テクスチャーなど)を扱うシェーダーが固定されているものもある(いわゆるバーテックスシェーダーとピクセルシェーダー)。そのため「Ice Storm」のGraphicsテストでは、これらの機能別シェーダーに集中してストレスをかけることで、搭載GPUの“弱点”を知ることができるようになっている。
最初に実行される「Graphics test 1」では、頂点シェーダーの性能テストがメインだ。多数の戦闘機や戦艦をグリグリ回すことで、GPUは頂点情報の処理に翻弄されることになる。その分ピクセルシェーダーを使うような処理(パーティクルや照明効果など)は使われないか、最小限になるよう画面が設計されている。
2番目の「Graphics test 2」はピクセルシェーダーを苛めるためのテストだ。ここでは多量のテクスチャーが使われ、「Graphics test 1」よりも空気感のあるグラフィックになっている。さらにピクセル単位での照明効果の計算や、ブルーム(眩しさ)、モーションブラーなどがポストプロセス処理で追加されている。頂点情報は「Graphics test 1」が平均53万個なのに対し、こちらでは平均7万5000個と少ない。
最後の「Physics test」はWindows版と同様に、CPUの1コアごとに1スレッドを割り当て、ブヨブヨとしたゼリー状の物体の動きと、その中に入っている剛体の動きをシミュレートする。

この連載の記事
-
第2回
PCパーツ
3DMarkの「Fire Strike」ではなにをテストしている? -
第1回
PCパーツ
新しくなったベンチマークソフト「3DMark」の用途と使い方 -
第-1回
PCパーツ
グラフィックベンチ「3DMark」徹底解剖 - この連載の一覧へ