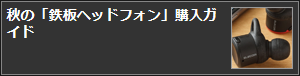ヤマハ試聴室で体験した、ネットワークオーディオ
NP-S2000が切り拓く、高音質再生の地平 (4/5)
2010年12月02日 11時00分更新
低域に差が出る、CDとリッピング音源
さて、CD-S2000とNP-S2000の大きな違いとして、最初に安井氏が示したのが、低域の質だ。まずはウッドベースのソロを含んだ楽曲『Amazing Grace』を使って、CD-S2000で再生したCDの音と、NP-S2000で再生したWAVファイルの音を順番に注意深く聴いた。
同じCDからリッピングしたものだが、後から聞いたWAVファイルのほうが、低域が柔らかく広がっていく。逆にCDの低音はエッジがよりハッキリとした印象でメリハリ感が強い。
高域の抜けや反響した音が小さく消えていくさまなど、空間表現に関しては文句なくネットワークオーディオに軍配が上がる。S/N感が上がったせいか、残響など微細な音がより明瞭になる。ただ一般的なオーディオ機器の評価では、低域はタイトに引き締まったほうがいいと言われれることが多い。それとは若干外れる印象で、意外性があった。
締まった低域という観点ではCDのほうがメリハリが利いている印象もあるが──。
ここで安井氏がコメント。低域の質に違いが出るのは「響きの違い」によるものだという。ネットワークオーディオでは、より微小な信号までしっかりと切り捨てず残すため、低域の量感が増し、豊かに広がっていく傾向が強いのだという。
実はCD-S2000とNP-S2000の比較で感じた雰囲気、何となく覚えがあるものだった。過去にLINNのMAJIK DS-Iの音を聴いた際にも(さらに言えばiPodの音を高音質なヘッドホンで聴いたときでさえ)、低域について近い印象を持ったのだ。
共通して言えるのは、低域に硬さがない一方で、音程感は明確でボワ付きや見通しの悪さは感じないこと。これまでは機器固有のキャラクターによって得られるものだと思い込んでいたが、リッピングした音源全体に通じる特徴と言えるのかもしれない。
確かに短時間聴いただけでは、CDのほうが輪郭がハッキリとしており、メリハリが利いているように感じなくもない。しかし聴きこめば、より自然で豊かな情報を再現するのがネットワークオーディオのほうだと気付く。この印象は次に再生されたフルオーケストラ。小澤征爾指揮の「新世界より」でさらに強められた。
オーケストラのソースは、音場と音像の調和をチェックする上で最適だ。
音場はAmazing Graceの横方向から縦方向、さらには奥行き方向にも一段広がる。管楽器や打楽器(ティンパニー)は上下方向の位置関係が分かるほど見通しが良く、ライブ録音ならではの拍手や観客の咳の音なども立体的な空間の的確な位置にマッピングされる。とても自然で、あるべきものがあるべき位置にあるという印象だ。
ここまで聴けばNP-S2000に優位性があるのは明らかである。上に挙げた素性の良さを持つネットワークオーディオだが、その本質は30分ほどの視聴でも十分に実感することができた。
雑味なく爽快なNP-S2000の音
となると心配になるのが、CD-S2000の立ち位置だ。
一連のデモの中で印象に残った安井氏のセリフに「今後CDのような光メディアが生き残るのは、SACDしかない」というものがあった。これは、ネットワークオーディオの圧倒的な再生能力は、その素性と言う意味でCDとは異なる次元であるという意味だろう。
確かにSACDと高音質配信の住み分けは気になるところだ。SACDは単に情報量が多いだけではなく、DSDというPCMとは異なる方式で記録されているため、ハイサンプリングのロスレスデータが入手できたとしても完全に同じものが得られるわけではないが……。
SACDとの比較と言うことで安井氏が取り出したのが角田健一のビッグバンド録音だ。ワーナー初のSACDとしてこの夏に発売された『BIG BAND SOUND ~甦るビッグバンドステージ~ 』から7曲目のマック・ザ・ナイフを聴く。NP-S2000のソースは同じディスクのCD層をリッピングしたもの。
SACDの音はよりマスターへの加工感が少ないと言うか、ニュートラルな印象で、情報量の差という優位も確かにあるようだ。しかしその一方で筆者は、ここでもリッピングデータの再生に魅力を感じた。
印象に残ったのは、まず最初に雑味なく魅力的なブラスの音色。そしてビブラホンの硬く澄んだ音色だ。特にビブラホンでは、金属特有の無音から瞬間的に音が立ち上がり、すっと消える硬い質感が非常にリアルであった。この音を聴くと、慣れ親しみ、十分な音と感じていたCDに余分な成分やガサツキ感が混じっていたのだと改めて感じる。

この連載の記事
-
Audio & Visual
第7回 DYNAUDIO Confidence C1 Signatureを聴く -
Audio & Visual
第6回 LUXMAN試聴室で、ハイレゾと真空管、両極端のサウンドを体験 -
Audio & Visual
第5回 AirPlayで広がる、AVアンプの可能性 -
Audio & Visual
第4回 NP-S2000が切り拓く、高音質再生の地平 -
Audio & Visual
第3回 Hi-FiソースとしてのiPodを改めて体験する -
Audio & Visual
第2回 Hi-Fiとゼネラルの懸け橋──MAJIK DS-Iを聴く -
Audio & Visual
第1回 伝統のJBLを、総額ウン千万円のシステムで聴く -
AV
第回 こだわり機器を聞く、最上の試聴室めぐり - この連載の一覧へ