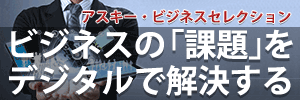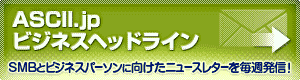操作性──親指だけですべて操作できるのが理想的
肝心なときに操作がもたついて、録音チャンスを逃した……ということは、なんとしても避けたい。音質や録音形式と並び、ICレコーダー選びのポイントとなるのが「操作性」だ。
操作ボタンが本体正面に集約されていると、親指だけで操作できるうえ、誤ってボタンを押してしまう可能性も少ない。一方、ボタンが側面に配置されているタイプは、慣れるまではその都度ボタンの位置を確認しなければいけないため、もどかしさを感じる
今回ピックアップしたモデルは、携帯性に優れたスリム筐体のモデルばかり。ジャケットやパンツのポケットにすんなり入るサイズで、気軽に持ち歩けるコンパクトボディだが、それだけに操作ボタンの配置は難しい。
また、ICレコーダーの操作は基本的に片手で操作することが前提。本体を持ちながら操作するとなると、本体正面に主要なボタンを配置して、ほとんどの操作を親指だけで済ませられるスタイルが理想だ。それが難しい場合は、本体側面をどのように利用するかで、操作性が大きく変わってくる。また、本体のサイズもチェックしておきたい。
ピックアップしたモデルでは、大振りな製品から極めてコンパクトな製品まであるが、あまりに大きすぎたり、小さすぎたりすると、やはり操作をしにくい。手のひらにしっくりくるサイズのモデルを選ぼう。突発的に訪れた録音チャンスを逃さないためにも、快適に操作できるモデルを見極めたい。
インターフェース──USB端子の形状にも注意
ICレコーダーを利用するうえで、もはや欠かせない要素となっているのは、PCとのリンク機能。USBでPCに接続し、録音した音声データの保存・管理はもちろん、視聴や編集など活用するためだ。
ほとんどのケースは、USBケーブルでPCに接続し、録音データなどをやりとりするが、中には本体にUSB端子を内蔵しており、直接PCに差し込めるモデルもある。ケーブルを持ち歩く必要ながなく、外出先でも素早くPCに接続できるほか、PCのUSBポートに差したまま、利用することも可能。録音データをスムーズに活用できるのが魅力だ。
また、付属のソフトにも注目をしたい。録音データの管理のみならず、データの分割や結合、録音形式の変換などを備えているほか、マルチトラックサウンドの編集やサウンドエフェクトができるなど市販ツール顔負けの高機能ぶりだ。中には音声認識ソフトと併用することにより、音声をテキストデータに起こせるものもあり、使いこなせば非常に重宝する。インターフェースを確認するとともに、付属のアプリケーションも確認しておくとよいだろう。
フリーソフトで音声データのテキスト化を効率アップ!
会議を録音したデータなどは、録音して終わりというわけではない。議事録として、録音データを聴きながら、テキストデータに起こすことが少なくないだろう。MP3でもリニアPCMでも、Windows Media Playerで問題なく聴けるが、聴きながらテキストデータを作成するには効率が悪い。
そこで利用したいのが、音声データをテキスト化するためのソフト『Okoshiyasu2』だ。再生速度の可変や音程の変更などができるほか、再生や一時停止をホットキーで素早く操作できる。また、一時停止をして再開すると、一定の秒数ぶん巻き戻した位置から再生されるなど、テキスト化する際、非常に重宝する。
音声データをテキスト化する場合には、ぜひ用意しておきたいソフトだ。
- ソフト名:Okoshiyasu2
- ダウンロード:http://www12.plala.or.jp/mojo/
- 作者:Mojo氏
- ソフト種別:フリーウェア

この連載の記事
-
第4回
ビジネス
いま買っていい、ICレコーダー5機種 -
第2回
ビジネス
いま旬の電子辞書4モデル、購入のポイント -
第1回
ビジネス
電子辞書とICレコーダーでビジネスをスマートに乗り切る! -
ビジネス
仕事を乗り切る、BizTools - この連載の一覧へ