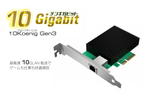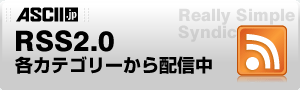新しい入力デバイスが登場
これに続くのがマウスの普及である。DOS環境であっても、Digital ResearchのGEMとかQuarterDeckのDESKviewなど、マウスを利用できる(というかマウスを前提にした)環境が出てき始めた。
またアプリケーションの中には、独自にマウスをサポートしたものもあった。これに関しては間違いなくApple ComputerのMacintosh(*1)が先駆者であり、もちろんその先祖はXEROXのAltoであるのだが、当時Altoの存在を知っていたユーザーなどほんの一握りであり、大多数のユーザーはMacintoshでGUIというものと、そこで使われるマウスという新しいツールを知ったとしてしまっても過言ではないと思う。
PCにおけるマウスの需要に対応すべく、MicrosoftはMicrosoft Mouseを1983年に発売する。当初発売されたのはRS-232-Cポートに接続するタイプで、シリアルマウスと呼ばれた。
これに引き続きMicrosoftは1986年頃に、Microsoft InPortなるI/Fカードとセットになったマウスも発売する。
シリアルマウスとの対比でこちらはバスマウスと呼ばれたが、バスマウスといっても実際にはマウスからポジションをシリアル通信で送っているので、本質的にはシリアルマウスと差がない。
違いは? というと、シリアルマウスの方は1本のシリアルで、マウスのX座標とY座標、それとボタンを押す/押さないの情報を順次送っていたのに対し、バスマウスはX座標用とY座標用、それとボタン1~3それぞれが別の配線になっており、全部の配線で並行して情報をシリアルで送っていたことだ。そのため、5chのシリアル通信を一気に処理できる専用チップがInPortのI/Fカードの上に載っている。
原理的には、シリアルマウスよりバスマウスの方が、より高頻度に位置情報やボタン情報を送れる分、反応が早いはずではあるのだが、まだゲームなどにマウスを活用する時代ではなかったので、現実問題として使い勝手にまったく差はなかった。
一部のビデオカードの中にはこのバスマウス用のI/Fを搭載したもの(例えば1989年に発表されたATIのVGA WONDER 1024 XL)も存在する。ただこうしたマウスの需要は、意外にPC互換機では立ち上がらなかった。
Windowsを使うには必須と言われても、Windows 1.0や2.0あたりは使い物にならないというのが正直なところで、どちらかといえばOS/2 2.0の方がまだマシ(ただしインストールが地獄)という感じだった。実際筆者もAT互換機で本格的にマウスを使うようになったのは1990年以降だと記憶している。
(*1) これもApple ComputerのLisaが先駆者というか、Alto→Lisa→Macintoshなのだが、Lisaも一部のマニアのみが知る機種であり、Altoとどっちが一般的なユーザー(≠Macintoshユーザー)にとって知名度が高かったか、よくわからない。

この連載の記事
-
第775回
PC
安定した転送速度を確保できたSCSI 消え去ったI/F史 -
第774回
PC
日本の半導体メーカーが開発協力に名乗りを上げた次世代Esperanto ET-SoC AIプロセッサーの昨今 -
第773回
PC
Sound Blasterが普及に大きく貢献したGame Port 消え去ったI/F史 -
第772回
PC
スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -
第771回
PC
277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 -
第769回
PC
HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -
第768回
PC
AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -
第767回
PC
Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -
第766回
デジタル
Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -
第765回
PC
GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ - この連載の一覧へ