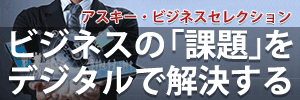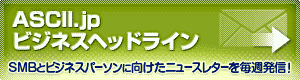日本電信電話(NTT)の研究チームは、半導体光触媒と金属触媒を電極に採用した人工光合成機器を開発した。350時間連続して二酸化炭素を一酸化炭素やギ酸に変換でき、連続動作時間は世界最長だという。人工光合成機器の連続動作時間は数時間〜数十時間にとどまっていたが、電極の劣化抑制などの工夫によって記録を達成した。
日本電信電話(NTT)の研究チームは、半導体光触媒と金属触媒を電極に採用した人工光合成機器を開発した。350時間連続して二酸化炭素を一酸化炭素やギ酸に変換でき、連続動作時間は世界最長だという。人工光合成機器の連続動作時間は数時間〜数十時間にとどまっていたが、電極の劣化抑制などの工夫によって記録を達成した。 半導体光触媒を酸化電極に、金属触媒を還元電極に採用した人工光合成機器では、水溶液に溶かした二酸化炭素(CO2)を一酸化炭素(CO)やギ酸(HCOOH)に還元する手法が一般的だが、水溶液に溶かせる二酸化炭素の量には限りがある。また、金属触媒が水溶液に触れる面で劣化が進む課題もあった。 研究チームは半導体光触媒として使用する窒化ガリウム系電極の表面をより滑らかにし、光を十分に透過する厚さ2ナノメートル(nm)の均一な酸化ニッケル薄膜を保護層として形成。窒化ガリウムと水溶液の接触を防ぎ、電極の劣化を大幅に抑制することに成功した。 さらに、水溶液中の二酸化炭素を還元する手法から、気相の二酸化炭素をそのまま還元する手法に切り替えた。金属電極には二酸化炭素をよく拡散する繊維状金属を採用し、この電極を電解質膜と一体化させ、水溶液からプロトンが電解質を通して繊維状金属の電極に移動できるようにした。この結果、従来に比べて二酸化炭素の変換効率が10倍以上に向上した。 研究成果は、11月14日〜17日にNTT武蔵野研究開発センタで開催される「NTT R&D FORUM 2023 ― IOWN ACCELERATION」に展示される予定。(笹田)