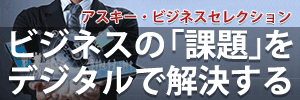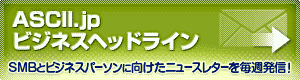大阪大学の研究チームは、紙、天然ワックス、スズ、炭など環境に配慮した材料のみで構成された土壌含水率センサーの開発に成功した。石油由来の非分解性プラスチックや有害金属が多用される既存のセンサーと異なり土に還るため、ばらまくように設置ができ、「センシングもできる肥料」としての応用も可能だという。
大阪大学の研究チームは、紙、天然ワックス、スズ、炭など環境に配慮した材料のみで構成された土壌含水率センサーの開発に成功した。石油由来の非分解性プラスチックや有害金属が多用される既存のセンサーと異なり土に還るため、ばらまくように設置ができ、「センシングもできる肥料」としての応用も可能だという。 センサーは、木材由来の微細繊維で作られた紙基板、スズ配線、カーボンヒーター、天然ワックス・コーティングで構成する。受信コイルを備えており、無線給電で電力が供給されることでセンサーに搭載されたヒーターが加熱される。 センサーを設置した土壌の含水率によって受信電力が変化する設計となっており、土壌含水率が変化するとヒーターの温度が変化する。その熱をサーマルカメラで撮影することで、センサーの設置位置と土壌含水率を遠隔から同時に取得できる仕組みである。 生分解性プラスチックなどを用いた環境に優しい電子材料に関する研究はこれまで数多く実施されてきたが、性能や安定性に課題があり、分解性とセンサーとしての必須機能(センシング・データ発信・設置位置情報発信)を両立することは困難だった。研究論文は、アドバンスト・サステナブル・システムズ(Advanced Sustainable Systems)に、2023年10月17日付けで掲載された。(中條)