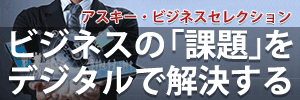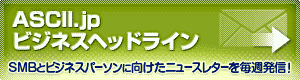国立天文台などの国際研究チームは、比較的若い原始星である「おうし座DG星」周囲の原始惑星系円盤に対し、チリの「アルマ望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計)」で高解像度観測や多波長観測を実施。円盤の構造や惑星の材料となる塵の大きさ、量について詳細に調べた結果、惑星形成前夜の様子であることが判明。さらに、円盤の外側で惑星形成の過程が進んでいることがわかった。
国立天文台などの国際研究チームは、比較的若い原始星である「おうし座DG星」周囲の原始惑星系円盤に対し、チリの「アルマ望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計)」で高解像度観測や多波長観測を実施。円盤の構造や惑星の材料となる塵の大きさ、量について詳細に調べた結果、惑星形成前夜の様子であることが判明。さらに、円盤の外側で惑星形成の過程が進んでいることがわかった。 惑星は原始星の周りを取り巻く原始惑星系円盤内で星間塵(ダスト)や星間ガスが集まって形成されると考えられている。だが、いつ、どこで、どのように惑星の形成が始まるのか、その最初の一歩はわかっていない。 研究チームは今回、原始星の中でも比較的若い天体、おうし座DG星に着目し、その原始星を取り巻く円盤内のダストが放つ波長1.3ミリメートル(mm)の電波強度の分布を0.04秒角という非常に高い空間分解能で観測した。その結果、この円盤は、のっぺりとしていて、比較的年を経た原始星の周囲の円盤で見られるリングのような構造がないことがわかった。これは、おうし座DG星の円盤にはまだ惑星が存在せず、惑星形成前夜の様子を捉えたと考えられるという。 さらに、波長を変えて円盤を観測し(0.87mm、1.3mm、3.1mm)、電波強度や偏光強度を調べたところ、ダストの大きさは円盤の内側よりも外側(およそ40天文単位以遠:太陽系の海王星に相当する距離よりも少し遠く)の方が比較的大きくなっており、惑星形成の過程が進んでいることがわかった。このことは、これまでの惑星形成論では内側から惑星形成が始まると考えられていたが、むしろ外側から惑星形成が始まる可能性を示唆しているという。 研究論文は、アストロフィジカル・ジャーナル(Astrophysical Journal)に2023年8月28日付けで掲載された。(中條)