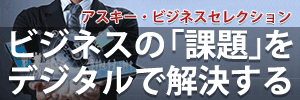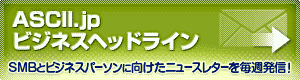東北大学の研究チームは、新型コロナウイルス感染症の流行とそれに伴う救急病院の多忙化においても、急性心筋梗塞の救急医療は維持されたとの調査結果を発表した。新型コロナウイルス感染症の流行による救急医療体制を逼迫が懸念されているが、日本の急性心筋梗塞救急医療体制に対象を絞って、実際の影響度合いを始めて調査した。
東北大学の研究チームは、新型コロナウイルス感染症の流行とそれに伴う救急病院の多忙化においても、急性心筋梗塞の救急医療は維持されたとの調査結果を発表した。新型コロナウイルス感染症の流行による救急医療体制を逼迫が懸念されているが、日本の急性心筋梗塞救急医療体制に対象を絞って、実際の影響度合いを始めて調査した。 研究チームは、新型コロナウイルス感染症による1回目の緊急事態宣言下(2020年4月7日〜5月25日)に、「宮城県心筋梗塞登録研究」のデータを使用して、感染拡大に救急医療への影響を調べた。宮城県心筋梗塞登録研究とは、宮城県の主要な循環器医療施設45施設が参加する研究で、県下で発生する急性心筋梗塞のほぼ全症例を長期間にわたって登録し、研究を続けている。 2020年に宮城県心筋梗塞登録研究に登録された1186名の患者と、2017年から2019年の3年間に登録された患者4877名を比較すると、1回目の緊急事態宣言下にあった期間では、来院から閉塞血管の血流回復までに要した時間(Door-to-device time)は、中央値が74分から83分に延長していた。 ただし、この傾向は病院搬送時に心不全の兆候が確認できなかった患者のみにあったもので、心不全の兆候を伴ったより重症な患者では中央値が80分から78分に短縮していた。このことから、研究チームは対象期間中はどの医療機関も適切なトリアージができていたとしている。また、急性心筋梗塞の発症から病院来院までにかかった時間が延長した事実もなく、救急車使用率や冠動脈カテーテル治療の施行率も低下しておらず、院内死亡率も過去3年と変わらなかったとしている。 研究結果は9月16日、「ICJハート・アンド・ヴァスキュラチュア(IJC Heart and Vasculature)」誌にオンライン掲載された。(笹田)