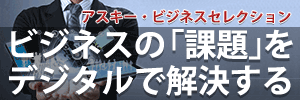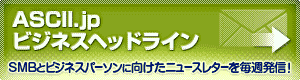DXのウィークポイント、データ連携基盤の重要さ
日本はなぜDXが進まないのか? いろいろな見解があるが、河西氏はDXを進めるためのデジタル社会基盤が存在していないことが大きなウィークポイントだと指摘する。これに対してソフトバンクは、さまざまなソリューションからデータを利活用できるプラットフォームを構築する。いわゆる「都市OS」と呼ばれるデータ連携プラットフォームでは、公共データ、民間データ、センサーデータなどさまざまなデータを、フラットに、オープンに、かつセキュアに連携できるのが特徴だ。
データ連携基盤はリアル空間とバーチャル空間でそれぞれデータを行き交わせる「デジタルツイン」においても必要なインフラと言える。デジタルツイン上でシミュレーションと未来予測を重ねることで、社会課題の解決に対して有効な現実解を導き出せるわけだ。「これから人が少なくなるので、PoCのような人手と手間のかかる煩雑なプロセスは難しい。シミュレーションファーストで、未来を予測しながら、意思決定して行くには、こうしたデータ連携基盤が必要になる」と河西氏は語る。
こうしたデータ連携でなにが実現できるのか? 災害対策の例を見てみよう。今まで河川に関する情報は自治体、救助が必要な人や地域の情報は消防・警察、病床数は医療機関といった具合に、それぞれデータを持っていても、連携するすべがなかった。しかし、これらを共通に利用できるプラットフォームがあれば、自治体は避難所に誘導するだけではなく、質の高いサービスを避難対象者に提供できる。
たとえば、医療サービスと連携すれば、避難者に最適な服薬が実現される。また、免許を返納しているならば、移動のためにモビリティサービスを付与することも可能になるだろう。災害時においても、自治体は迅速な状況の把握が可能になり、住民は次の行動を的確に判断できる。実際、会津若松では自治体と連携し、災害発生時に、位置情報データに基づいてきめ細かな避難誘導などができる仕組みの構築を進めている。
また、自治体との連携のみならず、自らもデータ連携基盤の活用を進めている。1月に移転が完了したソフトバンクの新竹芝オフィスは、1400を超えるセンサーでデータを収集し、データ連携基盤で活用できるようにしている。サイネージやアプリで働く人に最適な環境を提供するとともに、非接触での入館や混雑を作らない人の移動、効率的な警備などを実現している。
特筆すべきは、データ連携基盤を構築することで、メーカーや管轄の壁を越えた連携が可能になっていること。「カメラのデータを元に警備員に不審な人物を通報できるのですが、今まではカメラは他のメーカーのものとつながらなかったし、警備員はビル管理の担当、われわれはテナントという立場。同じビルでありながら、ステークホルダーが多く、連携が難しかった。データ連携基盤があるからこそ、実現できることは多い」と河西氏は語る。リアル空間とバーチャル空間を連携させたデータドリブンな取り組みは、新竹芝オフィスから、竹芝エリア全体に拡げ、他の都市とも連携していくという。
デジタルインフラ、スマートシティ、地域の再構築などソフトバンクが手がけるDXを通じて目指すのは、次の日本で最重要なデジタル産業の創出とそこを担う人材育成だという。「もはや日本には世界と戦える産業はなかなか残っていない。今後、データで意思決定できる環境を整えることによって、デジタル産業を立ち上げる。そして、そのデジタル産業に携わることで、世界で戦えるデジタル人材を育てていけると考えている」と河西氏は語る。