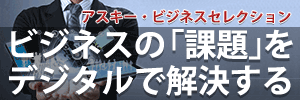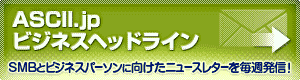Tableauがデータドリブン企業に関する調査を発表、三井住友海上火災保険の事例も
「データドリブンなカルチャー」が危機状況下での企業の命運を分ける
2021年02月18日 07時00分更新
パンデミックでも成長し続けるデータドリブン企業になるには
本調査結果から、国内においても「データドリブン企業とそうでない企業とのデータ格差が拡がりつつある」(佐藤氏)ことは確たるトレンドであり、さらにパンデミックがこのデータ格差の拡大に拍車をかけていることが推察される。パンデミックは企業がもともと抱えていた潜在的な課題、たとえばビジネスの将来の計画、製品/サービスの継続性、人材能力開発の評価と向上などを浮き彫りにし、企業はいやがおうでもこれらに向き合う必要に迫られた。そしてデータ活用が進んでいたデータドリブン企業とそうでない企業の間には明らかな格差が生まれ、拡大しつつある。
それでは、パンデミックでも成長し続けるデータドリブン企業になるには何が必要なのだろうか。佐藤氏は「データを企業の資産として認識し、全社をあげてデータにもとづいた意思決定を行うという文化を社内に醸成していく必要がある」と強調する。そうした企業の事例として、今回の発表会ではTableauユーザでもある三井住友海上火災保険(MS&AD)の取り組みが紹介された。
三井住友海上火災保険は近年、AIをベースにした代理店向けシステム「MS1 Brain」や、災害/事故に関する同社の膨大なデータやノウハウを下敷きにした企業リスク可視化サービス「RisTech」など、データの価値を活かしたビジネスを積極的に展開している。
こうしたデータビジネスを支えているのが同社のデジタル人材であり、社内には以下のようなデジタル人材を育成/認定するプログラムがいくつか存在する。新型コロナウイルスの影響により、オンラインベースに再構築されたコースが多い点も注目に値する。
・デジタル人財認定制度 … 三井住友海上のデジタルトランスフォーメーションを牽引する社員を認定/可視化する制度。いままでにないビジネスアイデアを創出し実現に向けて取り組む「ビジネスデザインコース」、RPAやExcelマクロを活用して業務効率化を実践する「業務プロセスデザインコース」、BIツールやプログラミングによる分析を行い、課題に対するユースケースや仮説を考案する「データ分析コース」などが設けられている。
・MS&ADデジタルアカデミー … 東洋大学情報連携学部(INIAD)と連携したMS&ADグループ専用研修プログラム。「ビジネスデザインコース」と「データサイエンティストコース」が用意されており、2020年度はコロナの影響によりオンライン研修プログラムとして再構築。
・MS&ASデジタルカレッジ from 京都 … 京都先端科学大学と提携したMS&ADグループ専用研修プログラム。2020年度創設で、VRスコープやドローン、ウェアラブル端末などの実機を使用した実習がメイン。完全オンライン研修プログラムとして構築。
・デジタルビデオプラットフォーム … 全社で展開/撮影した動画などを使ったコンテンツをもとに、コロナ禍でも時間や場所を選ばずに自己学習や業務推進を可能にするプラットフォーム。PCやスマートフォンなど私物のデバイスから、24時間365日いつでも制限なく視聴が可能。シングルサインオンなど認証機能が充実しており、直感的に理解しやすい画面設計。
また同社では、Tableauユーザの育成にも力を入れている。
三井住友海上火災保険 デジタル戦略部 業務プロセス改革チーム 課長 横山輝樹氏によれば、2019年4月のTableau導入時における初期ユーザは社内に20名だったが、1年後の2020年2月は82名に、そしてコロナの感染拡大をはさんだ2020年10月には141名まで拡大している。導入当初は従来ツールのヘビーユーザを中心に初期研修を実施し、その研修を受講したユーザに対してTableauライセンスを配布していたが、初期のユーザが中心となって2020年1月には社内に「Tableauユーザ会」が設立され、研修のフォローアップや情報共有サイトでの情報発信などが始まっている。
新型コロナウイルスの感染拡大後(2020年2月以降)は集合型のセミナーや勉強会が開催できなくなったが、かわりにすべてのユーザ会コンテンツをオンライン化/Web化し、Web研修の実施や動画コンテンツの配信、さらにはWebベースのユーザ会や「もくもく会(Tableau操作フォローアップの勉強会)」などが自発的に実施されている。その結果、コロナ禍にあっても研修参加者が減ることはなく、場所/時間を問わずに利用するTableauユーザが大きく増加した。「人材教育という観点からいえば、以前よりも総合的に高い品質の教育環境を提供できている。コロナ禍をチャンスに変えることができたと思っている」と横山氏は振り返る。