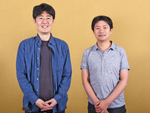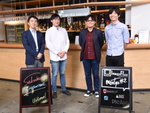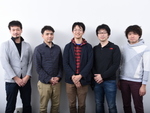さくらの熱量チャレンジ 第38回
いま「お寺のデジタル化」が必須である理由――浄土宗・善立寺 副住職 小路竜嗣さん
「寺院デジタル化エバンジェリスト」に聞く、お寺とデジタルの未来
2019年12月10日 08時00分更新
寺院が直面するさまざまな「危機」を乗り越えるにはデジタル化が必要
寺院がデジタル化を進めるべき理由について、小路さんは、現在の寺院が直面しているいくつかの「危機」について説明してくれた。まず、事務作業に多くの時間を取られている現状がある。
「お寺では、日課である宗教的なお勤め(法務)だけでなく、企業のバックヤード業務のような事務作業も行っています。宗教法人なので、たとえば各種申請書類の作成や郵送、経理作業といったものですね。その間にかかってくる電話には絶対に出なければなりませんし、FAXでの連絡も来ます。会議や研修などの外出、移動も頻繁にあります」
特に善立寺のような“家族経営”の寺院では、1人や2人でこの作業を担わなければならない。他方で葬式の予定は急に入る。家族の病気やケガ、介護への対応といった家庭の用事もこなさなければならない。さらに近年の仏教界では、社会貢献活動なども強く求められるようになっており、そうした時間も必要だ。
つまり、事務作業を効率化/省力化して時間の余裕(バッファ)を作らなければ、家族のための時間、あるいは新たな地域貢献活動や研修、学習などに充てる時間はとても取れないのが現状だという。

こうした忙しさは、僧侶自身の「働き方」にも悪影響を及ぼしている。ニューズウィーク日本語版の記事(2018年)では、1カ月あたりの残業時間が100時間を超える「過労死予備軍」の比率が高い職種のランキングで「宗教家」がトップに挙がった。「このままでは、お坊さんになりたいと考える人自体が減ってしまいます」と、小路さんは危機感をつのらせる。
もうひとつ、寺院の存立基盤そのものにも危機が訪れている。国内人口の減少に伴い、今後25年間で全国約900の市区町村が“消滅”する可能性があると言われているが、全国およそ17万7000の宗教法人(寺院、神社など含む)のうち、そうした“消滅可能性地域”にあるのは全体の約35%、6万法人以上に及ぶという(国学院大学 石井研士教授の試算、2016年)。特に善立寺のように、地域の檀家に支えられているような寺院ではその影響が顕著に表れるだろう。
「実際に、地方ではすでにお寺が減少しつつあります。住職がいないお寺が出てくると、1人が(残ったほかの寺院が)2つ以上の宗教法人を管理することになり、負担はさらに増えます。未来永劫とは言いませんが、今後100年間、地域の菩提寺を存続させていくためにも、デジタル化は欠かせないと考えています」
デジタルのコミュニケーションで場所、地域にこだわらない新たな「縁」を作る
小路さんがデジタル化を進めるべきと考えるもうひとつの側面が、寺院と社会/人々との「コミュニケーション」だ。
善立寺では2018年1月に公式サイトを立ち上げた。もともとは、年2回発行している寺報(檀家に配布する会報誌のようなもの)を掲載したいと考えて始めたという。さらに寺院として、正確さが保証された「公式の情報」を発信することも大切だと考えた。
ただし現在、善立寺がサイトに掲載されているのは、善立寺の歴史や永代供養などの案内、地図や問い合わせ先といった静的な情報だけではない。小路さんはサイト内にWebメディア「Teranova(テラノバ)」を立ち上げ、たとえば自身が行った講演やボランティア活動のレポート記事、さまざまな活動を行う若手僧侶のインタビュー記事なども執筆、掲載している。
地域人口の減少という問題は非常に大きい。小路さんは「善立寺のような地方の小さなお寺は、まずはその厳しい現状を受け入れないといけません。そのうえで、もっと場所や地域にとらわれない『新たなつながり方』で、お寺と縁をつないでくださる方を増やしていくしかないと思います」と語る。そのために、従来どおりの対面のコミュニケーションも、新しいネットでのコミュニケーションも、両方の「窓口」を持つことが大切だと考えている。
「地元の方、特におじいちゃんおばあちゃんの世代とは、これまでどおり対面のコミュニケーションが良いでしょう。ただ、檀家さんでも若い世代の方は都会に働きに出ていて、お寺とのリレーションがない。そこで、新たな接点となるデジタルな窓口の必要性も感じています」
実際に、善立寺の公式サイトを開設してから、サイト経由で「墓じまい」や「永代供養」の相談や問い合わせが来るようになった。しかも、Teranovaの掲載記事を見て「小路さんがどんなお坊さんなのかがわかったので、相談しやすかった」という声は少なくないという。寺院との接点が少ない人が、誰に相談したらよいのか困っている現状は間違いなくある。安心して相談ができる関係を作る、「顔の見える」情報発信は大切だ。
さらに別の側面でも、もっと積極的に情報発信をすべきだと小路さんは語る。
「最近では、さまざまなお寺が積極的に社会貢献活動、ボランティア活動をやっているのですが、その実態が情報発信できていない。“株主への説明責任”ではありませんが、われわれはお檀家さんのご支援でこうした活動ができているわけですから、その成果はきちんとお伝えしなければならないと思うのです」
寺院デジタル化エバンジェリストとしての今後の活動について、小路さんは現在、仲間とともに「お坊さん向けのコミュニティサイト」立ち上げを計画していると話してくれた。全国の寺院が抱える課題や悩みを互いに相談、共有できる場を作ると同時に、その解決に役立つデジタルやテクノロジーを学べる場を作っていきたいと話す。
「困っているお坊さんは全国にいるのですが、特に地方では、そうしたことを学べる機会が少ないのが実情です。また、それを伝える(教える)場も現在のところWebには存在しません。テクノロジーやITにあまり興味のない人でもアクセスできるような何かを作らないといけないな、と考えています」
(提供:さくらインターネット)

この連載の記事
-
第43回
デジタル
「さがみ湖イルミリオン」のIoTアトラクションを生みだした名古屋の燃料配達会社 -
第42回
sponsored
酒田市のスタートアップが目指す「新しき地方ITの道と光」 -
第41回
sponsored
ハッカソン好き技術者が考えた未来のゴミ箱は「自分でお金を稼ぐ」? -
第40回
sponsored
衛星データを民主化するTellus、さくらインターネットから見た舞台裏 -
第39回
sponsored
首里城の3D復元プロジェクトを生んだ小さな奇跡の連なり -
第37回
sponsored
衛星データが使い放題?経済産業省とさくらが描いたTellusへの道 -
第36回
sponsored
宮古島は「エネルギー自給率向上」を目指し、再エネ+IoTをフル活用 -
第35回
sponsored
映画/ドラマ情報の「Filmarks」、画像配信の悩みをImageFluxで解決 -
第34回
デジタル
放射線治療をAIで効率化するベンチャーと京都大学病院の挑戦 -
第33回
sponsored
ガンプラの新たな楽しみ方に挑む! BANDAI SPIRITS/バンダイナムコ研究所/冬寂/フレイム - この連載の一覧へ