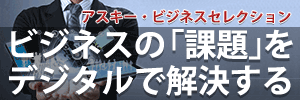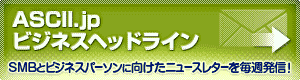歴史の中で生まれた感覚、技術と時代の中で変わる感覚
“サイズ”について意外と知られてないこと
2012年09月28日 09時00分更新
変化するサイズの考え方
標準的なサイズとはなんだろうか? 僕が初めて自分のサイトを作ったときは、幅を480ドットで作った。これは当時、僕が使っていたディスプレー「Apple AudioVision 14 Display」の情報量(640×480ドット)に合わせた。おそらくその時代に普及していたディスプレーの多くがそれくらいの情報量だったはずだ。
それから、世の中に普及するディスプレーのサイズと画素数に合わせて、サイトの幅も「480ピクセル」→「640ピクセル」→「720ピクセル」→「865ピクセル」とリニューアルするごとに増やしてきた。最新のサイトの幅は、「Facebook」の新しいインターフェイス、タイムライン(851ドット)やTwitter(865ドット)のPC用のサイトの横幅を参考にした。
もちろん、ピクセルのサイズ(ドットピッチ)が小さくなる一方で、ディスプレーのサイズは年々大きくなってきているので、印象的な大きさはあまり変わっていないかもしれない。
ディスプレーサイズと解像度
パソコンのディスプレーでは、縦横に表示できる画素(=ピクセル)の数を示すために“解像度”という言葉がよく使用される。
少し混乱しやすいのは、パソコン雑誌やメーカーのカタログ表記では、解像度という言葉が「ディスプレーで表示できる画素の数(ピクセル数)」と「画面に映像をどれだけきめ細かく表示できるか」の2つの意味で使われているためだ。
前者は1280×800ピクセルや1920×1080ピクセルといった形式で、水平・垂直方向に配置された画素の数を表現するもの。文字やアイコンの標準的な画素数はOSごとに決まっているので、表示画素の高いディスプレーであれば1画面に表示できる情報がそれだけ増えることになる。ちなみに、厳密に言うと1つの画素にはRGBなど各色のドットが含まれるので、一般的な液晶ディスプレーでは1ピクセル=3ドットになるが、あまり区別せずに使われている。
後者は本来の意味での解像度と言える。画素ピッチと表現されることもある。画面にあるピクセルの数(=情報量)を画面サイズで割った数値で、1インチ当たりのピクセル数を示す「ppi」が単位として用いられる。
かつてのMacintoshでは、画面の解像度は72ppiに固定されていた。これはフォントのサイズを「10ptなら10pt」と指定した際に、「画面に表示されている文字の大きさ」と「紙に出力した文字の大きさ」が一致するよう配慮したためと言われている。
9インチのモノクロCRTを一体化した初代Macintoshの表示画素数は512×342ピクセル。その後発売された機種でも、しばらくの間は13インチディスプレーなら640×480ピクセル、19インチディスプレーなら1024×768ピクセルという具合に、画素数は画面サイズに比例していた。
ちなみに現在ではMacintoshでもWindowsでもこうした決まりごとはなく、ディスプレーによって画面サイズと画素数の関係はまちまちである。例えば6月に発表された「MacBook Pro Retina Displayモデル」は2880×1800ピクセルで15.4型。画素ピッチは約220ppiと、同じ画面サイズの従来機(1440×900ピクセル/約130ppi)に比べ、1.7倍稠密に映像を表示できる。

この連載の記事
-
第70回
ビジネス
画像使用でトラブル?!クリエイティブ・コモンズ活用術 -
第69回
ビジネス
プロの道具がスゴイ! -
第68回
ビジネス
CASIO「MGC-10」、開発秘話 -
第67回
ビジネス
ドローン少年事件で考えるマネタイズの寿命 -
第66回
ビジネス
スター・ウォーズ コンテンツの成功の7つのポイント -
第65回
ビジネス
アクセスの伸びる写真 ドミナントカラーって何? -
第64回
ビジネス
大塚家具の騒動のネットの反応、会員制の是非 -
第63回
ビジネス
水、火、木、空という、古く新しいコンテンツ echo camp series 2015レポート -
第62回
ビジネス
Apple Watchの未来について妄想してみた -
第61回
ビジネス
今どきのサイバーセキュリティ事情 -
第60回
ビジネス
自動車に参入?Apple周辺のウワサをまとめてみた - この連載の一覧へ